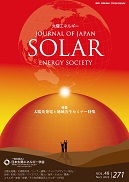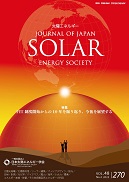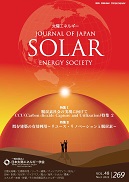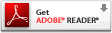【開催案内】電気学会一般公開シンポジウム(日本学術会議連携)
『カーボンニュートラルの時代に『電気』が果たす役割 ~未来につなぐ夢 を語ろう』
(日本学術会議 制御・パワー工学分科会の活動から)(ハイブリッド開催)
——————————————————————–■
【日時】2023年3月15日(水)13:30~17:15
【場所】名古屋大学(東山キャンパス・IB大講義室:名古屋市千種区不老町)
Webexによるハイブリッド開催
【開催趣旨】
日本学術会議制御・パワー工学分科会は,『電気を作る・送る・活かす』に関わる課題を包括的に扱う分科会で,『2050年カーボンニュートラル社会』に向け、活動を展開してきた。その中で得られた知見を広く社会に提供すべく、シンポジウムの前半では,カーボンニュートラルに関わる電力の諸課題を科学的・中立的立場で解説し、後半では、カーボンニュートラル社会を見据え、電気・電子工学が拓く数十年先の夢を語るパネルセッションとする。
【シンポジウム専用サイト】
https://www.iee.jp/blog/taikai2023_symp_h1/
【ポスター】
https://www.iee.jp/wp-content/uploads/2023/02/symp220315_h1.pdf
開会メッセージ:梶田隆章(日本学術会議会長)
登壇者:中川聡子(東京都市大学名誉教授)、大崎博之(東京大学教授)、横山明彦(東京大学名誉教授)、岩崎誠(名古屋工業大学大学院教授)、河村篤男(横浜国立大学寄付講座教授)、佐藤育子(東電パワーグリッド(株)常務執行役員)、永井正夫(東京農工大学名誉教授)、山中直明(慶応義塾大学教授)、千住智信(琉球大学教授)、圓浄加奈子(電気新聞編集局長)
【参加費】無料(本シンポジウムは電気学会全国大会本部企画のシンポジウムで、全国大会一般シンポジウムと異なり、現地参加・リモート参加ともに無料です)
【定員】現地会場は、300名収容可能ですが諸事情を鑑み130人程度に制限させて頂きます。Web参加の場合は,相当数の準備がございます。
【申込】現地参加の場合:事前申し込みは不要です。
リモート参加の場合:以下のサイトから事前申込してください。
(受付期間:2/15~3/8)
https://www.iee.jp/blog/taikai2023_online/
【講演資料】無料にてシンポジウム専用サイトからダウンロードできます(3月初旬公開)。

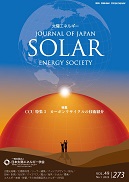
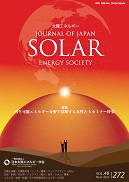 学会誌
学会誌