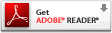開催趣旨: エネルギー作物は、木質バイオマス、廃棄物系バイオマスに続く、新たなバイオマスエネルギー資源として注目されて来ました。これまで、エネルギー作物として、最初にトウモロコシが実用化されましたが、食糧との競合によって大きな問題を引き起こしてしまいます。いま、食糧と競合しないエネルギー作物のひとつとして微細藻類の利用が検討されています。日本太陽エネルギー学会光化学・バイオマス部会では、微細藻類の大量培養によってエネルギー生産を目指す実証的研究を進められている株式会社関電工技術研究所を見学する会を企画しました。この見学会は、研究概要の説明、研究装置の実機紹介、質疑応答を含みます。
主 催:日本太陽エネルギー学会光化学・バイオマス部会
後 援(申請中):日本農芸化学会
協 賛(申請中):日本エネルギー学会、ユーグレナ研究会
日 時:2026年2月20日(金)13時から15時40分
集合場所・時間:JR常磐線神立駅 12:40 (集合後、タクシーに分乗して研究所に向かいます。
神立駅まで東京から特急で1時間、特急を利用しないで2時間です。)
見学場所:株式会社関電工技術研究所(茨城県かすみがうら市下稲吉2673-169)
募集人員:15名(申し込み先着順)
参加費:1,000円(往復のタクシー代等) 現地にて徴収します。
問い合わせ先:日本太陽エネルギー学会 事務局
電話03-3376-6015 FAX 03-3376-6720
E-mail: info@jses-solar.jp
参加登録:こちらからお申し込みください。または参加申込書にご記入のうえ、日本太陽エネルギー学会事務局までE-mail、FAXにてお送りください。
申し込み順に受付書を発送します。
定員に達し次第、参加登録を締め切ります。
投稿者「日本太陽エネルギー学会 Webサイト管理者」のアーカイブ
2025/12/10 【New!】学会誌「Journal of Japan Solar Energy Society (太陽エネルギー)」 Vol.51, No.6 (通巻290号)発刊のお知らせ(会員専用ページではカラー版を閲覧・ダウンロードできます)
学会誌「Journal of Japan Solar Energy Society (太陽エネルギー)」 Vol.51, No.6 (通巻290号)を発刊しました。
今号の特集は「ヒートポンプで利用する再生可能エネルギー『環境熱』の利用拡大と定量化」です。 「研究室紹介」では東海大学建築都市学部建築学科の高橋研究室が紹介されています。
さらに連載エッセイ「それぞれのサンシャイン物語」は、作田宏一さんによる第8回「太陽熱発電 サンシャイン計画との『巡り合わせ』」です。
なお、研究論文・技術報告を除く各記事は発刊1年後から閲覧可能となります。ただし、会員専用ページではカラー版の即時閲覧・ダウンロードが可能です)
目次はこちら。
第20回再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム プログラム公開のお知らせ
第20回再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム(略称RE2026)の12分野フォーラムのプログラムを公開しましたので連絡いたします。皆様のご参加をお待ちしています。
1.URL https://www.renewableenergy.jp/2026/forum.html
2.日程 東京ビッグサイト会議棟
1月28日(水)
10:00-12:30 分科会1(政策・統合概念)グリーントランスフォーメーションGXに向けた政策と取組みの紹介
10:00-12:25 分科会4(環境建築)建築外皮に統合(適用)される再生可能エネルギー最前線
13:30-16:10 分科会2(太陽光発電)太陽光発電、最新展開情報の紹介
13:30-16:35 分科会9(地熱・地中熱)地熱・地中熱の開発や利用の最新情報を発信する
1月29日(木)
10:00-12:30 分科会5(風力)主力電源を目指し、風力発電の現状と今後に向けた最新情報の発信
10:00-12:30 分科会6(バイオマス)バイオマスニッポンから20年を経て新たな展開へ
13:30-16:00 分科会7(水素・燃料電池)水電解及び燃料電池電池の実用化最新技術の紹介
13:30-16:00 分科会8(海洋エネルギー)海洋エネルギー・資源の利用推進と展望
1月30日(金)
10:00-12:30 分科会3(太陽熱利用)熱の脱炭素化に向けた太陽熱利用の促進
10:00-12:30 分科会10(エネルギーネットワーク)カーボンニュートラル化に向けたエネルギーシステムの将来像
13:30-16:00 分科会11(省エネ・ヒートポンプ)ヒートポンプによる低温排熱の活用、並びに省エネ
13:30-16:00 分科会12(水力発電・未利用エネルギー)再エネ普及のキーテクノロジー,エネルギー需給調整としての水力発電
2025/12/04 【New!】脱炭素ソーラーフューエル部会 設立のお知らせ
2025年11月6日に開催されました理事会において、新たに「脱炭素ソーラーフューエル部会」の設立が承認されましたので、お知らせいたします。
本部会では、ソーラーフューエル技術を中心とした脱炭素社会の実現に向け、学術的・技術的な情報交換や関連分野の発展を図ってまいります。
現在、部会員を募集しておりますので、参加をご希望の方は事務局までご連絡ください。
詳細はこちらをご覧ください.
2025/11/28 【New!】関西支部 川崎重工業株式会社様水素関連施設見学会(2025年12月15日)集合時間・集合場所・タイムスケジュール確定のお知らせ
一般社団法人日本太陽光発電学会設立記念講演会(2025年12月11日)開催のお知らせ
一般社団法人日本太陽光発電学会設立記念講演会
日時:2025年12月11日(木) 13:00~19:00
場所:東京科学大学 蔵前会館くらまえホール(〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1)
参加費:講演の部は会員・非会員のいずれも無料
プログラム及び申込先
https://www.j-pvs.jp/event/commemorative_lecture.html
講演の部:13:00-17:00
13:00-13:05 挨拶 大平 圭介(一般社団法人日本太陽光発電学会 会長)
13:05-13:10 御祝辞 日暮 正毅 様(経済産業省資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課 課長)
13:10-13:25 学会紹介 大平 圭介(一般社団法人日本太陽光発電学会 会長)
13:25-14:05 招待講演 山田 宏之 様(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 再生可能エネルギー部 部長)
「再生可能エネルギーの未来と太陽光発電への期待(仮)」
14:05-14:45 招待講演 小坂 優 様(東京大学 先端科学技術研究センター 准教授)
「気候変動の要因と予測(仮)」
14:45-15:00 休憩
15:00-15:40 招待講演 河本 桂一 様(みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 サステナビリティコンサルティング第1部 エネルギービジネスチーム マネジャー)
「太陽光発電搭載自動車の現状と展望」
15:40-16:20 招待講演 森田 健晴 様(積水ソーラーフィルム株式会社 取締役、技術・開発部長(兼)積水化学工業株式会社PVプロジェクト)
「フィルム型ペロブスカイト太陽電池の社会実装に向けた取り組み」
16:20-17:00 招待講演 宮坂 力 様(桐蔭横浜大学 医用工学部、大学院工学研究科 特任教授)
「ペロブスカイト薄膜太陽電池の新材料開発と低コスト化の展望」
2025/11/25【New!】学会設立50周年記念事業 絵画コンテスト受賞者のお知らせ(各作品を掲載しました)
2025年7月11日から2025年9月15日にかけて募集いたしました絵画コンテストの審査結果がまとまり、受賞者を決定しましたのでお知らせいたします。
詳細はこちらをご覧ください。
先進的省エネ技術の開発及びNEV&AIデバイスの市場動向(2025年12月17日)開催のお知らせ
開催日:(講演) 2025年12月17日(水)13時30分~17時20分、(交流会) 17時30分~19時
会 場:芝浦工業大学 豊洲本部棟 阿出川シアター&2408教室(東京都江東区豊洲3丁目7番5)
主 催:一般社団法人スマートエネルギー産業振興機構(略称:社団SEIDA)
共 催:芝浦工業大学 工学部 パワーエレクトロニクス研究室(教授:高見 弘)
定 員:講演会:会場60名、オンライン90名、交流会:40名
参加費:※講演会参加者:社団SEIDA会員、協力法人会員、月刊JETI購読者は各3000円、
学生:1000円、一般:6000円 ※交流会(立食) 参加者は別途4000円
【開催方法】会場とオンラインの併用開催(オンラインはライブ配信とアーカイブ配信になります)
【開催趣旨】近年、インターネット・データーセンター(IDC)は世界規模で激増しており、莫大な情報量
を扱うAIの急速な発展と相まって、必要な消費電力は加速的に増加しています。そのIDC冷却に要する消費電力を抑えることは喫緊の重要課題となっております。次世代型IDCに対応した省エネルギー型冷却システムとして丸和電機株式会社が開発した「 省エネ型小型ターボ圧縮機装置」、及び共同研究者の芝浦工業大学 工学部 パワーエレクトロニクス研究室にて開発した 低ひずみ・低ノイズで高効率駆動が可能なモータ駆動系」を報告します。次に、社団SEIDA・副会長の同大 高見 弘 教授が、長年にわたる省エネ技術研究の一環として開発した「 災害時も電気と湯水が供給できる太陽光とスターリングエンジン複合型移動式電源車」について、その開発成果を報告いたします。
更に社団SEIDAが企画協力しております技術総合誌 月刊JETI」(発行:日本出版制作センター)
に2024年から寄稿連載を行っています新エネ車(NEV)動向を中心とした世界と中国の自動車市場、
及びパワー半導体とAIデバイスの市場分析、それぞれの2026年市場見通しを報告いたします。
第55回日本産業技術大賞 推薦受付(2025年12月末締切り)のお知らせ
日刊工業新聞社日本産業技術大賞事務局から以下の通り日本産業技術大賞推薦の依頼が届いています。
本事業では、応募に際し該当技術に関して産業団体、学会、協会などからの推薦があることが条件となっています。
自薦、他薦構いませんので候補者がいらっしゃいましたら12月末までに事務局まで連絡くださいますようお願いいたします。
詳細はこちらをご確認ください。
日刊工業新聞社のお知らせはこちらをご確認下さい。
https://corp.nikkan.co.jp/p/honoring/nihonsangyogijyutsutaishou
問合せ先:一般社団法人日本太陽エネルギ-学会 事務局
担当:池田
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-44-14
TEL:03-3376-6015 FAX:03-3376-6720
E-mail:info@jses-solar.jp
2025/11/04 関西支部 川崎重工業株式会社様水素関連施設見学会(2025年12月15日)開催のお知らせ
日本太陽エネルギー学会 関西支部では以下のとおり見学会を開催します.
皆様のご参加をお待ちしています.
【関西支部】川崎重工業株式会社様水素関連施設見学会のご案内
1.日 時:2025年12月15日(月」)14:00~16:50
2.見学施設:川崎重工業株式会社
・液化水素荷役実証ターミナル「Hy touch 神戸」(神戸空港島)
・「水素コージェネレーションシステム(CGS)」(ポートアイランド)
3.見学内容:川崎重工業(株)が有する最先端の水素エネルギーの実証試験設備(液化水素ローディング・貯蔵システム,および水素ガス燃焼発電タービン)を見学します.
バスを使用して,神戸空港島とポートアイランドの2か所の設備を訪問します.
4.募集人員:先着27名
5.集合場所:神戸三宮駅東口ラウンドワン三宮駅前店そばの道路にバスを配車しますので14:00までに集合ください.
6.参加費:無料
7.申し込み方法:こちらからお申込みください.または,こちらの申込書に必要事項を記載の上,学会事務局(info@jses-solar.jp)まで連絡ください.
8.交流会:終了後交流会を開催しますので,ご参加ください
・ 鉄板居酒屋 武蔵(兵庫県神戸市中央区加納町4-5-3)
・時間: 17:00~19:00
・参加費:5,000円(税込み,現地徴収)
見学会スケジュール
14:00~14:20 集合場所→ポートアイランド
14:20~15:30 ポートアイランド 水素CGS活用スマートコニュニティ実証地 視察
・水素エネルギーに関する取組みの説明(40分)
・プラントヤード 視察 (20分)
・質疑応答 (10分)
15:30~15:40 ポートアイランド→神戸空港島
15:40~16:10 神戸空港島
・神戸液化水素荷役実証ターミナル 視察
・神戸基地概要ご説明 (30分)
16:10~ 神戸空港島→神戸三ノ宮 バス移動
2025/11/03 学会設立50周年記念事業 作文コンテスト受賞者のお知らせ(各作品を掲載しました)
2025年7月11日から8月18日にかけて募集いたしました作文コンテストの審査結果がまとまり、受賞者が決定しましたのでお知らせいたします。
| 最優秀賞 | 国立津山工業高等専門学校 | 芦田 拓巳 |
| 優秀賞・(株)エヌ・ピー・シー賞・(株)カネカ賞 | 宮城県古川黎明高等学校 | 江良 さくら |
| 入選・英弘精機(株)賞 | 成城学園高等学校 | 峯岸 泰希 |
| 入選・大阪ガス(株)賞 | 名城大学 | 深田 彩心 |
| 入選・(株)関電工賞 | 青森私立山田高等学校広域通信課程 | 千田 立煌 |
| 入選・SOMPOリスクマネジメント(株)賞 | 徳島県立脇町高等学校 | 坂本 梓 |
| 入選 | 国立津山工業高等専門学校 | 柏木 智輝 |
| 入選 | 私立東京薬科大学 | 佐藤 愛玲菜 |
各作品はこちらでご覧になれます。
応用物理学会 有機分子・バイオエレクトロニクス分科会講習会 「ペロブスカイト太陽電池の社会実装への道筋」(2025年11月26日)開催のお知らせ
ペロブスカイト太陽電池は、次世代を担う有力な太陽電池として世界的に注目を集めています。
すでに各地で実証実験が進められ、社会実装への期待が高まる一方で、実用化に向けて克服すべき課題も数多く指摘されています。
とりわけ研究開発のスピードが非常に速いため、情報が錯綜し、現状の課題や方向性が見えにくくなっているのも事実です。
本講習会では、こうした状況を踏まえ、これまでのペロブスカイト太陽電池の開発の歩みを振り返りつつ、現時点で明らかになっている課題を整理・明確化します。
また、産官学が連携して社会実装を加速させるために必要となる視点やノウハウについても紹介し、今後の研究開発や産業応用に役立つ指針を提供します。
日時: 2025年11月26日(水) 10:00-17:25
場所: 東京科学大学大岡山キャンパスディジタル多目的ホール (大岡山西9号館)
申し込み〆切/参加費振込〆切:11月10日(月)
■ 内容問合せ先:
桐蔭横浜大学・柴山直之
E-mail: shibayama@toin.ac.jp
■ 参加問合せ先:
応用物理学会 分科会担当 岡本 晋一
E-mail: divisions@jsap.or.jp
詳細はこちら
表面科学技術研究会2026 「PFAS規制の動向と代替技術の展望」(2026年1月23日)開催のお知らせ
公益社団法人日本表面真空学会 関西支部では、表面科学技術研究会2026「PFAS規制の動向と代替技術の展望」を開催いたします。
皆様のお越しをお待ちしています。
主 催: 一般社団法人 表面技術協会 関西支部、公益社団法人 日本表面真空学会 関西支部
日 時: 2026年1月23日(金)13:00 ~ 17:20
場 所: 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所 森之宮センター 大講堂(大阪市)
ならびに、ZOOMによるオンライン配信
定 員: 会場80名、オンライン100名
参加費: 参加費:2,000円(日本表面真空学会会員及び表面技術協会会員ならびに協賛団体会員) 3,000円(上記以外の一般参加者)
学生:無料
詳細はこちらをご確認ください。
問い合わせ先:(一社)表面技術協会 関西支部 事務局(担当:石川・森) 〒606-0805 京都市左京区下鴨森本町15番地 電話番号:075-781-1107 FAX番号:075-791-7659 E-mail: kansai-office@sfj.or.jp
申し込み締切り: 2026年1月16日(金) 申し込み方法:https://www.jvss.jp/chapter/kansai/hyoumengijutsu2026/ のフォームからオンラインで申込みください。
2025/10/23 ソーラー建築部会「ソーラーアーキテクチャーガイドブック」発刊のお知らせ
ソーラー建築部会では、学会設立50周年を記念してソーラーアーキテクチャーガイドブックを発刊しましたのでお知らせします。
詳細はこちらをご覧ください。
2025/10/23 学会設立50周年記念事業「ソーラーアーキテクチャーガイドブック」発刊のお知らせ
一般社団法人日本太陽エネルギー学会 学会設立50周年記念事業
「ソーラーアーキテクチャーガイドブック」発刊のお知らせ

ソーラー建築部会では、学会設立50周年を記念してソーラーアーキテクチャーガイドブックを発刊しました。
体裁・価格
| 体裁 | : | B5版 約150ページ |
| 価格 | : | 定価 2,750円(内消費税250円)+送料 |
本書は廉価頒布のため学会直販としました。書店では取り扱っておりません。
お申し込みは こちら からまたは購入申込書に必要事項を記載の上学会事務局までお送りください。
収録内容
| 1章:背景と概要 | 4章:ゼロエネルギー住宅 |
| 2章:ソーラーアーキテクチャーデザインの流れ | 4-1 ゼロエネルギー住宅の歴史 |
| 2-1 地域特性に応じた建築設計 | 4-2 ゼロエネルギー住宅のこれから |
| 2-2 地域特性に応じた設備設計 | 5章:設計に活用できる静的・動的シミュレーションツール |
| 3章:要素技術の基礎知識 | 6章:先進事例 |
| 3-1 断熱、気密、防湿 | 団地・街 開発事例 |
| 3-2 換気 | 住宅 開発事例 |
| 3-3 通風・排熱 | 7章:評価 |
| 3-4 暖冷房 | |
| 3-5 太陽熱 | |
| 3-6 住宅用太陽光発電システム | |
| 3-7 熱・光発電複合利用 | |
| 3-8 地中熱利用 | |
| 3-9 蒸発冷却・蒸散冷却 | |
| 3-10 HEMS | |
| 3-11 デシカント空調 | |
| 3-12 コージェネレーション | |
| 3-13 蓄熱(Passive、Active) | |
| 3-14 住まい方マニュアル |
問合せ
一般社団法人日本太陽エネルギー学会
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-26-5
バロール代々木419号室
TEL:03-3376-6015
FAX:03-3376-6720
E-mail:info@jses-solar.jp
【JST】第5回羽ばたく女性研究者賞(マリア・スクウォドフスカ=キュリー賞)の公募開始(12月10日(水)日本時間正午締切)のお知らせ
JSTは駐日ポーランド共和国大使館との共催で、国際的に活躍が期待される若手女性研究者を表彰する「第5回 羽ばたく女性研究者賞(マリア・スクウォドフスカ=キュリー賞)」の公募を開始しました。ぜひ、積極的にご応募下さい。また応募資格のある方にご転送下さい。
マリア・スクウォドフスカ=キュリー:ポーランドが生んだ世界的研究者。31歳でポロニウム、32歳でラジウムを発見し、女性で初めてノーベル賞を受賞、且つこれまでに唯一2つの異なる分野「化学賞」「物理学賞」を受賞。
<表彰内容>
・最優秀賞(1名):賞金100万円、副賞としてポーランドの研究機関への渡航・滞在費
・奨励賞(2名):賞金50万円
(賞金は日本電子株式会社、ポーランド訪問機会は駐日ポーランド共和国大使館および同国科学アカデミーから贈られます。)
<応募要項>
◆応募要件:
・自薦・他薦とも可能。他薦の場合は、本人の了承が必要
・2026年4月1日時点で博士学位取得後5年程度まで※の女性研究者(ポスドクを含む)、大学院生(博士後期課程)、及びこれらに相当する者
※ライフイベント等による研究活動休止期間を勘案する
・科学技術に関連する幅広い研究分野を対象
・国籍:日本、 居所:不問
◆応募期間: 2025年10月1日(水)~12月10日(水)日本時間正午まで
◆応募方法等の詳細:https://www.jst.go.jp/diversity/researcher/mscaward/
★お問合せ
国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)
人財部ダイバーシティ推進室
E-mail: diversity@jst.go.jp
【NEDO】新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業に関する公募開始(2025年11月25日(火)正午締切)について
本事業は、再生可能エネルギーの導入促進・普及拡大に資する研究開発テーマを助成を通じて事業化までを支援するものです。具体的には、本事業には以下の2つの制度があり、貴社の技術段階に応じた支援が可能です。
〔1〕新エネ中小・スタートアップ支援制度
中小・スタートアップ企業を対象とする研究開発や事業化計画の進捗状況等に応じて、5つのフェーズ
(社会課題解決枠フェーズA、社会課題解決枠フェーズB、フェーズC、新市場開拓枠フェーズα、新市場開拓枠フェーズβ)で研究開発に対して助成します。
〔2〕未来型新エネ実証制度
中小・スタートアップ企業及び大企業を対象とする実用化に近い技術を対象に、
再生可能エネルギーの主力電源化の達成に資する技術に早期実用化に向けた実証事業に対して助成します。
※助成率/助成額についての詳細は公募ページをご確認ください。
ご関心をお持ちいただけましたら、以下の公募説明会にぜひご参加ください。
■公募について
・公募期間:2025年10月8日(水) ~ 2025年11月25日(火)正午
〔1〕新エネ中小・スタートアップ支援制度
※本公募のご案内資料は以下URLにてご確認ください。
2025年度第2回「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」(新エネ中小・スタートアップ支援制度)に係る公募について
https://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100439.html
〔2〕未来型新エネ実証制度
※本公募のご案内資料は以下URLにてご確認ください。
2025年度「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」(未来型新エネ実証制度)に係る公募について
https://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100445.html
■公募説明会
• 新エネ中小・スタートアップ向け: 10月15日(水)10時00分~11時00分および10月29日(水)10時00分~11時00分
説明会登録フォームURL:https://forms.office.com/r/kanVnyC3gX
• 未来型新エネ実証向け:10月22日(水)10時00分~11時00分
説明会登録フォームURL:https://forms.office.com/r/mRxyGpmjs3
まずは説明会にご参加の上、ご検討いただけますと幸いです。
<お問い合わせ先>
・説明会申込みに関するお問い合わせ
E-MAIL:jp_cons_new_energy_seeds@pwc.com
・公募内容に関するお問い合わせ
再生可能エネルギー部「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」事務局
E-MAIL:venture-pfg1@ml.nedo.go.jp
【SDC】講演会(2025年11月25日)開催のお知らせ
2025/10/06 2025年度研究発表会のプログラムを掲載しました.
2025年11月2日および3日に明治大学駿河台キャンパスで開催される2025年度研究発表会の講演プログラムを掲載しました。
プログラムはこちら。
2025/10/06 学会誌「Journal of Japan Solar Energy Society (太陽エネルギー)」 Vol.51, No.5 (通巻289号)発刊のお知らせ(会員専用ページではカラー版を閲覧・ダウンロードできます)
学会誌「Journal of Japan Solar Energy Society (太陽エネルギー)」 Vol.51, No.5 (通巻289号)を発刊しました。この号は日本太陽エネルギー学会設立50周年記念特集号となっています。
「研究室紹介」では長岡工業高等専門学校機械工学科エネルギー工学研究室が紹介されています。
さらに連載エッセイ「それぞれのサンシャイン物語」は、小林広武さんによる第7回「大量普及への道を開いた太陽光発電の系統連系技術開発」です。
本号には以下の研究論文が収録されています。
-
- 自然エクセルギー利用システムの最適設計の検討─太陽熱利用システムの計算モデル構築と感度解析─/伊澤康一・宋城基
- 太陽光発電所における需給調整市場の前日計画と不足発生リスク評価/崔錦丹・方雪・界波・大関崇・植田譲
なお、研究論文・技術報告を除く各記事は発刊1年後から閲覧可能となります。ただし、会員専用ページではカラー版の即時閲覧・ダウンロードが可能です)
目次はこちら。
2025/10/02 10月7日開催「 民間団体によるエネルギー長期シナリオを読み解く」講演会終了後のVideo公開のお知らせ
10月7日開催の100%再生可能エネルギー部会講演会 「民間団体によるエネルギー長期シナリオを読み解く」については、講演終了後に参加者限定でVideo公開させていただきます。
当日の参加が困難な方も、参加申込いただければ後日Video視聴のご案内をさせていただきますのでお知らせします。
詳細はこちら
【JST】ムーンショット型研究開発事業における国際シンポジウム(2025年10月30~31日)開催のお知らせ
ムーンショット目標8では、「2050年までに、激甚化しつつある台風や豪雨を制御し極端風水害の脅威から解放された安全安心な社会を実現」を目指し、革新的な「気象制御」技術の研究開発に取り組んでいます。
これまでの研究開発によりシミュレーション上では、豪雨や台風を人間の力で変えられることがわかってきました。
現在は、屋外での実証実験に向けたELSI対応を含めた準備や、気象予測・制御技術の高度化、防災効果の定量化、社会実装に向けた具体的な検討などに一層注力しています。
そこで、気象制御の研究開発に欠かせない、気象学、気象工学、数理科学、人文社会学など多様な分野の専門家を集い、技術的・社会的な課題について議論を深めるため、公開の国際シンポジウムを開催します。
シンポジウムでは、ムーンショット目標8のプロジェクトマネージャーによる進捗の報告や、各分野をリードする世界中から招聘された研究者による講演およびパネルディスカッションを行います。
本シンポジウムが皆さまとの貴重な議論の場となることを願っております。
ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げております。
https://www.jst.go.jp/moonshot/ (ムーンショット型研究開発事業)
https://www.jst.go.jp/moonshot/program/goal8 (目標8)
[会合概要]
会合名:ムーンショット目標8 気象の制御可能性に関する国際シンポジウム 2025
開催日時:10月30日(木)13:00-17:15
10月31日(金) 9:30-15:15
開催場所:御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター(https://solacity.jp/access/)
開催方式:現地参加/オンライン(Zoomウェビナー)
使用言語:英語
URL:https://www.jst.go.jp/moonshot/sympo/20251030/index.html
参加登録URL:https://form2.jst.go.jp/s/ms8-intl-symp2025
参加を希望される皆様は、上記URLから事前登録をお願いいたします。
科学技術振興機構 ムーンショット型研究開発事業部
目標8担当 E-mail:moonshot-goal8@jst.go.jp
【JWEA】第47回風力エネルギー利用シンポジウム 参加登録のご案内
第47回風力エネルギー利用シンポジウムの参加登録についてご案内いたします。関係各位のご参加をお待ちしております。
【開催日時】(プログラムの詳細は決まり次第、学会ホームページ及び同報メールでお知らせ致します。)
2025年11月27日(木) 9時30分~17時 依頼講演Ⅰ・Ⅱ、学会からの報告、ポスター展示
11月27日(木) 17時30分~19時 懇親会
11月28日(金) 9時~17時 一般研究発表、ポスター展示
【開催方法及び会場】
開催方法:会場及びオンライン(Zoomウェビナー)のハイブリッド開催
会 場:ビジョンセンター新橋
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-5-2 内幸町平和ビル
アクセス https://www.visioncenter.jp/shimbashi/access/
会議場名:11/27 依頼講演 18階 1801号室
11/27 懇親会 17階 1702号室
11/28 一般研究発表 16階 1602号室、1603号室、1604号室、1605号室
11/27-28 ポスター発表 17階 1703号室(荷物置き、休憩室としても利用下さい)
11/27-28 関係者控室 16階 1601号室
【参加費】
日本風力エネルギー学会正会員(個人会員/団体会員)、協賛・後援団体 20,000円
会員学生、一般学生、個人会員で70歳以上の方、特別会員 3,000円
一般 25,000円
懇親会(人数制限:130名) 6,000円
【参加登録期間】
9月22日(月) 00:00 ~ 11月21日(金) 17:00
【参加登録方法】
下記の専用サイト「Confit」からお申し込み下さい。
https://jweasympo.confit.atlas.jp/login
※お支払い方法は「バーチャル口座(銀行振込)またはクレジット決済」とさせていただきます。
(お問合せ専用窓口)
○参加登録、参加費支払などに関するお問合せ
運営事務局:(株)メイプロジェクト
メール:sympo_jwea@may-pro.net
電話:03-6667-0922
○論文・ポスター投稿に関するお問合せ
(一社)日本風力エネルギー学会事務局
メール:info@jwea.or.jp
電話:03-6284-2310
2025/09/11 教育委員会による動画教材「学習・教育用ライブラリー/入門編 水力1:私たちの暮らしと水力」(YouTubeおよびスライドPDF)を掲載しました
本学会教育委員会が作成した教育用の教材動画「学習・教育用ライブラリー/入門編 水力1:私たちの暮らしと水力」を掲載しました。
動画はYouTubeチャンネルにて視聴することができます。また、この動画のスライドPDFをダウンロードすることもできます。
皆様、ご活用くださいますようお願いいたします。
【JIE】第13回アジアバイオマス科学会議(11月18日)開催のお知らせ
行事名 第13回アジアバイオマス科学会議
主 催 一般社団法人日本エネルギー学会バイオマス部会
開催日 2025年11月18日(火)
会 場 弘前大学 文京町地区キャンパス創立50周年記念会館(青森県弘前市)
URL https://www.jie.or.jp/publics/index/1046/
連絡先
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-16-9 外神田千代田ビル4F
一般社団法人日本エネルギー学会
TEL.03-3834-6456 E-mail:ueda_jie1921@jie.or.jp
2025年度「第46回猿橋賞」受賞候補者の推薦受付開始(2025年11月30日締切り)のお知らせ
「女性科学者に明るい未来をの会」は、「女性科学者のおかれている状況が必ずしも望ましくない中で、一条の光を投じ、いくらかでも彼女らを励まし、自然科学の発展に貢献できるように支援する」という願いをこめ、1980年に創立されました。この創立の趣旨を継承し、当会は、毎年、自然科学の分野で顕著な業績を収めた女性科学者に賞(猿橋賞)を贈呈しています。賞の選考は、研究の独創性の高さ、発想のユニークさや、今後さらに大きく飛躍できるポテンシャルの高さ、研究分野の発展への貢献度、国際性等の多様な観点を考慮して実施します。また、受賞者が日本国内の若手研究者や、研究者を目指す次世代の担い手の育成に貢献し今後も活躍していただけることを強く期待しています。
第46回猿橋賞の募集を開始いたしました。
ホームページ https://saruhashisho.or.jp/に募集要項を掲載いたしました。
1)対 象 :創立の趣旨に沿って、多様な自然科学の分野で優れた研究業績を収めている女性科学者(ただし、下記の推薦締切日で50才未満の人)
2)表彰内容:賞状、副賞として褒賞金(50万円),1件(1名)
3)応募方法:
【推薦書類の作成】
推薦書は、当会のホームページ https://saruhashisho.or.jp/からダウンロードしたワードファイルに記入した後、PDF形式で保存してください。
【記入事項】
①推薦者(個人・団体、自薦も可)、受賞候補者の略歴
②推薦対象となる研究題目
③推薦理由(A4記入用紙1ページに収まること)
④主な業績リスト(指定は1頁。やむを得ない場合でも追加は1頁まで。)
【添付資料】
主な論文別刷5編以内。添付資料はPDFファイルで作成して下さい。
【送付先アドレス】
saruhashi.office@saruhashisho.jp
saruhashi.office@saruhashisho.or.jp
推薦書(PDFファイル)にはパスワードを付け、添付資料のPDFファイルと一緒に送付してください。推薦書のパスワードは別送付してください。
4)締切は2025年11月30日(必着)
5)第46回の猿橋賞贈呈式は、2026年5月23日(土)、東京都内で行なわれます。
書類は猿橋賞選考のためにのみ用いますが、返却いたしませんのでご了承下さい。
この件についての問い合わせは、下記に電子メールでお願いいたします。
saruhashi.office@saruhashisho.or.jp
【JIE】第21回バイオマス科学会議(2025年11月19日~21日)開催のお知らせ
開催概要
第21 回バイオマス科学会議を,2025 年11 月19日,20日に青森県弘前市にて開催いたします。青森は県全土面積の約3分の2を森林が占め,豊富な木質バイオマス資源を有しており,複数のバイオマス発電所が稼働しています。また,りんご栽培や稲作が盛んであることからリンゴの剪定枝やもみ殻の発電および熱利用も進んでいます。バイオマス利活用が盛んな青森にてバイオマス科学会議を開催できることは意義深く,是非皆様のご参加を賜り,活発にご質疑・ご討論いただけましたら幸いです。交流会,企業展示,テクニカルツアーも計画しておりますので,皆さまのご参加,ご発表を心よりお待ちしております。
開催日:2025年11月19日 (水)~11月21日 (金)
会場:弘前大学創立50周年記念会館
一般社団法人日本エネルギー学会
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-16-9 外神田千代田ビル4F TEL:03-3834-6456
2025/9/8 地域脱炭素・100%RE部会合同シンポジウム 「地域からの脱炭素を加速するために ― 住宅省エネ,再エネ発電から,EV,V2Hまで,横断的パッケージ化を ―」(2025年11月3日)開催のお知らせ
開催趣旨
気候変動対策の一環として、エネルギー構造転換の時代が始まっています.地域の一般市民、中小事業所、公共施設等は、省エネ化と再エネ自家発電等を取り入れ、エネルギー自立を図ることにより、高騰が予想される光熱費の大幅節約と災害時への備えを進めることができます.しかし、従来たくさんの業種にまたがっていて横連携がとれていないために、設計や工事等が二度手間三度手間になるなど、多くの課題が発生しており、合理的な推進ができていません.これらの施策は補助金頼みで進められてきましたが、今後は非能率部分の見直しや設計の統合・パッケージ化によるコスト削減を促進して経済合理性のあるものにする必要があります.
本シンポジウムは、上記の課題に応え、新しい時代を切り開くために、建築(設計、施工、改修)、自動車(BEV、PHV)、エネルギー(再エネ電力、再エネ熱)、調整力(蓄電、蓄熱、V2X)、マイクログリッドなどの関係者を、消費者、地域自治体、関係省庁等へうまくつなぐことを目指しています.
主催: (一社)日本太陽エネルギー学会地域脱炭素部会・100%再生可能エネルギー部会
協賛(予定):(一社)日本エネルギー学会,(一社)エネルギー・資源学会,(一社)電気学会,
(一社) 日本建築学会,(公社)自動車技術会,(一財)省エネルギーセンター,
(一社)環境共創イニシアチブ,(特非)環境エネルギー政策研究所,(公財) 自然エネルギー財団,
(一社) ZEH推進協議会,(一社) 住宅生産団体連合会,(一社) 環境共生まちづくり協会,
(一社) 日本電設工業協会,全日本電気工事業工業組合連合会,(一社)次世代自動車振興センター,
(一社) 電気自動車普及協会,(一社) 日本自動車販売協会連合会,
(一社)太陽光発電協会,再生可能エネルギー協議会
日程: 2025年11月3日(月)11:00~12:05(第1部) 13:00~16:25(第2部)
会場: 明治大学 駿河台キャンパス リバティータワー 7F 1073教室
千代田区神田駿河台1-1 JR中央線お茶の水駅から徒歩3分
参加費: 会員・協賛団体会員2,000円, 一般3,000円
※研究発表会に参加登録される方は無料で聴講できます.
参加方法:こちらの申込サイトまたは参加申込書からお申込みください.
問合せ先:日本太陽エネルギー学会事務局 Tel:03-3376-6015 Fax:03-3376-6720
E-mail:info@jses-solar.jp
プログラム 【第1部:基調講演】
11:00-11:05 第1部開会挨拶 地域脱炭素部会長 弘前大学 伊髙健治
11:05-11:30 なぜ地域で脱炭素が必要なのか
-地域防衛と未来づくりのための地域脱炭素の取組ー
公益財団法人 地球環境戦略研究機関 藤野 純一
11:30-11:45 分散型リソースとしての住宅エネルギーマネジメントとデマンドフレキシビリティ
東京大学 生産技術研究所 岩船 由美子
11:45-12:00 太陽光とEVが拓く未来の暮らし なぜ今、異業種連携が必要なのか?
株式会社再エネ企画 辻 基樹
13:00-13:20 自治体における太陽光発電(または再生可能エネルギー)の普及に向けた取組
東京都建築物環境報告書制度の概要について
東京都環境局 大野大野 公治
【第2部:問題提起・企業フラッシュトーク・パネルディスカッション】
13:20-13:25 第2部開会挨拶 東京農工大学名誉教授 堀尾 正靭
13:25-14:20 企業からのフラッシュトーク(1社7分)
ニチコン(株),(株)ミサワホーム総合研究所,積水ハウス(株),
(株)ヤマダ住建ホールディングス,三菱自動車工業(株),
日産自動車(株),パナソニック(株),(株)REXEV
14:20-14:35 休憩
14:35-16:15 パネルディスカッション
パネリスト 藤野 純一(地球環境戦略研究機関),高口洋人(早稲田大)
岩船由美子(東京大学),辻基樹(再エネ企画)
フラッシュトーク参加各社他
モデレーター 東京農工大学名誉教授 堀尾 正靭
16:15-16:20 閉会挨拶 100%再生可能エネルギー部会長 東京農工大学 秋澤 淳
2025/09/02 【New!】学会設立50周年記念事業「絵画コンテスト」の応募〆切を9月15日(月)に延長します。
 学会設立50周年記念事業の一環として実施中の、小学生から中学生までを対象とし「再生可能エネルギーと未来のくらし」をテーマとした絵画コンテストの応募〆切を9月15日(月)に延長します。
学会設立50周年記念事業の一環として実施中の、小学生から中学生までを対象とし「再生可能エネルギーと未来のくらし」をテーマとした絵画コンテストの応募〆切を9月15日(月)に延長します。
より多くの応募をお待ちしています。
詳しくは以下をご覧ください。
絵画コンテストのお知らせ
2025/08/26 教育委員会による動画教材「学習・教育用ライブラリー/入門編 太陽熱1:太陽熱利用システムの基礎」(YouTubeおよびスライドPDF)を掲載しました
本学会教育委員会が作成した教育用の教材動画「学習・教育用ライブラリー/入門編 太陽熱1:太陽熱利用システムの基礎」を掲載しました。
動画はYouTubeチャンネルにて視聴することができます。また、この動画のスライドPDFをダウンロードすることもできます。
皆様、ご活用くださいますようお願いいたします。
2025/08/21 100%再生可能エネルギー部会講演会 「民間団体によるエネルギー長期シナリオを読み解く」(2025年10月7日)開催のお知らせ
国の第7次エネルギー基本計画が決定されたが再エネの目標値は必ずしも高いとはいえない状況である.不確実性のある将来を見通すには幅広い観点から将来像を考える必要がある.国の議論の元となった将来シナリオだけでなく,各種研究機関や民間団体も将来シナリオを提示している.そこで,今回は民間主体の長期エネルギーシナリオに着目し,再エネの導入見通しの観点から比較することにより,長期シナリオの理解を深める機会とする.
主催:一般社団法人日本太陽エネルギー学会 100%再生可能エネルギー部会
協賛:エネルギー・資源学会,日本エネルギー学会,再エネ熱利用促進協議会,共生エネルギー社会実装研究所,自然エネルギー100%プラットフォーム
日程:2025年10月7日(火)13:00〜17:00
会場:東京理科大学森戸記念館第1フォーラム オンライン併用開催
参加費:会員・協賛団体会員:4,000円,一般:6,000円,学生:1,000円
参加方法:こちらの申込サイトからお申込みください.またはこちらの参加申込書に必要事項をご記入の上,事務局までお送りください.
問合せ先:日本太陽エネルギー学会事務局 Tel:03-3376-6015 Fax:03-3376-6720
E-mail:info@jses-solar.jp
※ご講演のVideoを後日、期間限定・参加者限定で公開いたします.当日の参加が難しい方も参加申込いただければ聴講できますのでご案内します.
プログラム
13:00-13:10 開会挨拶
100%再生可能エネルギー部会長 東京農工大学 秋澤 淳
13:10-14:00 長期エネルギーシナリオで何を目指すのか
~シナリオの目的と使い方~
東京科学大学 准教授 分山 達也
14:00-14:50 効率化と自然エネルギーを中心としたエネルギーシナリオ
~2040年までにエネルギー自給率75%を達成する~
自然エネルギー財団 シニアマネージャー 高瀬 香絵
14:50-15:05 休憩
15:05-15:55 IGES 1.5℃ロードマップ
地球環境戦略研究機関 プログラムディレクタ 田村 堅太郎
15:55-16:45 グリーントランジション戦略シナリオの経済合理性
未来のためのエネルギー転換研究グループ
東北大学 教授 明日香 壽川
16:45-17:00 まとめ
17:00 閉会
【JST/JICA】 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS) 令和8年度 研究提案募集開始(締切:10/20(月)正午)のお知らせ
国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)は、地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)において、令和8年度の研究提案を募集しています。
【募集期間】 令和7年8月19日(火)~ 令和7年10月20日(月)正午
【詳細情報】 https://www.jst.go.jp/global/koubo/index.html
本プログラムは、科学技術と外交を連携し、相互に発展させる「科学技術外交」の強化の一環として、文部科学省・外務省の支援のもと、JSTと国際協力機構(JICA)が連携して実施するものです。
開発途上国のニーズを基に、地球規模課題を対象とし、社会実装の構想を有する国際共同研究を政府開発援助(ODA)と連携して推進します。
本プログラムでは地球規模課題の解決および科学技術水準の向上につながる新たな知見や技術を獲得することや、これらを通じたイノベーションの創出を目的としています。
また、その国際共同研究を通じて開発途上国の自立的研究開発能力の向上と課題解決に資する持続的活動体制の構築を図ります。
(注) SATREPSはODAとの連携事業です。
JSTへの研究課題の応募とともに、相手国研究機関から相手国のODA担当省庁を通じ、日本政府に対する技術協力要請が行われる必要があります。
※ODA要請書の提出期限は10月14日(火)中です。
■公募概要(予定)
*応募要件:
日本国内の大学や研究機関、企業などに所属して、国際共同研究の研究代表者としての責務を果たし、全期間において国際共同研究に従事できること。
その他、責務等も記載していますので、公募要領の記載内容をご理解のうえ応募してください。
*対象分野:
環境・エネルギー/生物資源/防災
(注)感染症分野については、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)で公募が行われております。詳しくは、AMEDの公式サイト(https://www.amed.go.jp/program/list/20/01/001.html)を参照ください。
*研究期間:3~5年間
*予算規模:1課題あたり、1億円程度/年
(内訳)JST:委託研究経費3,500万円程度/年
JICA:ODA技術協力経費 上限3億円/5年間、上限2.4億円/4年間、上限1.8億円/3年間
■公募説明会
オンライン会議システムZoomを利用したウェビナー形式で公募説明会を開催いたします。
説明会参加には、事前登録が必要です。下記リンクより事前登録を行ってください。
※登録時に入力いただくご氏名、ご所属・役職、メールアドレスは、参加登録の確認のみに使用し、他の用途で使用することはございません。
日時: 2025年8月25日(月) 14:00~16:00 (環境・エネルギー/生物資源/防災分野)
登録用URL:https://zoom.us/webinar/register/WN_WwGF3Vb_SIuTnMusunmPng
内容:本プログラムの概要、公募に関するご案内、経費の枠組みなどについてご説明する予定です。
■お問い合わせ先
国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)
国際部SATREPSグループ 担当:土屋、森本
e-mail: global@jst.go.jp 電話: 03-5214-8085
※お急ぎの場合を除き、なるべく電子メールでお願いいたします。
2025/08/19 教育委員会による動画教材「学習・教育用ライブラリー/入門編 建築2:快適な室内温熱環境とは」(YouTubeおよびスライドPDF)を掲載しました
本学会教育委員会が作成した教育用の教材動画「学習・教育用ライブラリー/入門編 建築2:快適な室内温熱環境とは」を掲載しました。
動画はYouTubeチャンネルにて視聴することができます。また、この動画のスライドPDFをダウンロードすることもできます。
皆様、ご活用くださいますようお願いいたします。
【AIST】2026年度産総研イノベーションスクール人材育成コース受講生の募集 (2025年11月25日14:00締切)のお知らせ
国立研究開発法人産業技術総合研究所では、以下のとおり2026年度産総研イノベーションスクール人材育成コース受講生の募集を開始しましたのでお知らせします。
1.事業概要
「イノベーション人材育成コース」は、博士号取得者(募集時取得見込みの方を含む)を対象とした1年間のコースです。期間中は産総研特別研究員(第1号契約職員、ポストドクター)として雇用されます。高度で専門的な知識と技能を活かしつつ社会の様々な課題に挑戦してイノベーションを起こす研究者となることを目指して、ユニークな講義・演習、協力企業での長期研修、産総研での最先端研究に取り組んでいただきます。
2.募集対象
博士の学位を持つ方(2026年3月取得見込み含む)
3.応募期間
エントリー締切:2025年11月25日 14:00締切
4.応募方法
応募サイトより応募してください。
応募サイト:https://unit.aist.go.jp/innhr/inn-s/PD_course/entry.html
5.選考方法及び結果通知
結果は12月下旬以降メールにて順次通知します。
6.本件問い合わせ先
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
イノベーションスクール事務局(募集担当)
メール:school-saiyou-ml@aist.go.jp
2025/08/08 学会設立50周年記念特別講演会・祝賀会の参加申込受付を開始しました.
学会設立50周年記念特別講演会・祝賀会の参加申込受付を開始しましたのでお知らせします.
こちらのサイトからお申込みくださいますようお願いいたします.
特別講演会
日時:11月2日(日) 14:30-17:15
会場:明治大学駿河台キャンパス リバティタワー8階(東京都千代田区神田駿河台1-1)
参加費:無料
祝賀会
日時:2025年11月2日(日) 17:30-20:00
会場:明治大学駿河台キャンパス リバティタワー23階(東京都千代田区神田駿河台1-1)
参加費
一般:8,000円(事前申込)、10,000円(通常申込)
学生:5,000円(事前申込)、10,000円(通常申込)
2025/08/05 学会誌「Journal of Japan Solar Energy Society (太陽エネルギー)」 Vol.51, No.4 (通巻288号)発刊のお知らせ(会員専用ページではカラー版を閲覧・ダウンロードできます)
 学会誌「Journal of Japan Solar Energy Society (太陽エネルギー)」 Vol.51, No.4 (通巻288号)を発刊しました。この号では「海外からの目」「BIPVの現在と今後のゆくえ」の二つが特集されています。
学会誌「Journal of Japan Solar Energy Society (太陽エネルギー)」 Vol.51, No.4 (通巻288号)を発刊しました。この号では「海外からの目」「BIPVの現在と今後のゆくえ」の二つが特集されています。
「研究室紹介」では明治大学理工学部建築学科建築環境工学研究室が紹介されています。
さらに連載エッセイ「それぞれのサンシャイン物語」は、種村榮さんによる第6回「旧工技院名古屋工業技術研究所のサンシャイン計画を含む太陽熱energy R&D」です。
本号には以下の研究論文が収録されています。
- Ni系工業触媒を用いた模擬エタノール発酵液成分からの水素製造に関する技術評価/田島正喜・浅野涼也・田中崚登・髙谷侑翔・矢野裕
- 蓄電池の劣化モデルと制御方法の違いによる蓄電システムの蓄電性能および経済性評価/小川雄気・木村湧哉・松尾廣伸
- 三角錐型太陽集光方式による太陽光発電モジュールの発電電力量評価/河野雅弘・秋澤淳
なお、研究論文・技術報告を除く各記事は発刊1年後から閲覧可能となります。ただし、会員専用ページではカラー版の即時閲覧・ダウンロードが可能です)
目次はこちら。
2025/08/04 関西支部2025シンポジウム(2025年12月10日)開催のお知らせ
日本太陽エネルギー学会関西支部 2025年度シンポジウム
「次世代を担うペロブスカイト太陽電池の開発最前線」開催のご案内
開催趣旨:印刷法で形成できるペロブスカイト結晶薄膜材料は,高い光電変換特性を有し,太陽電池としてはその変換効率が既に約 27%に達しております.そのペロブスカイト太陽電池は実用化間近となっており,大阪万博にも展示され,ニュースにおいて枚挙にいとまがない状態です.
そこで今回の日本太陽エネルギー学会関西支部主催のシンポジウムでは,高名な桐蔭横浜大学・宮坂力教授,岡山大学・林靖彦教授,東京大学・瀬川浩司教授を大阪にお招きし,ペロブスカイト太陽電池の研究開発の最前線と今後の展望についてご講演をいただきます.
奮ってご参加のほど,よろしくお願いいたします.
主 催:日本太陽エネルギー学会関西支部
協 賛:(予定) 応用物理学会,日本化学会,電気化学会,日本建築学会,日本エネルギー学会,日本機械学会,電気学会,日本表面真空学会,光化学協会,日本太陽光発電学会
日 時:2025年12月10日(水)14:00~17:00
会 場:大阪公立大学 文化交流センター ホール室 オンライン併用開催
(大阪市北区梅田1-2-2-600大阪駅前第2ビル6階)
募集人員:会場参加100名(先着順).オンライン参加も可能です.
参加登録:こちらの申込サイトからお申し込みいただくか,参加申込書に記載の上,日本太陽エネルギー学会事務局までE-mail, FAXにてお送りください.
参加費:会員・協賛団体会員3,000円,非会員5,000円,学生(会員,非会員)1,000円(資料代を含む)
申込期限:11月28日(金)
問い合わせ先:日本太陽エネルギー学会 事務局 電話03-3376-6015 FAX 03-3376-6720
E-mail: info @jses-solar.jp
講演プログラム:
0.開場(13:30~14:00)
1. 開会(14:00~14:05) 関西支部長(兵庫県立大学) 伊藤 省吾
2.「電荷輸送層のないペロブスカイト太陽電池の構造設計と特性評価」(14:05~14:55)
桐蔭横浜大学 教授 宮坂 力 氏
—————休憩(5分)————–
3.「添加剤で変える! 高効率・長寿命ペロブスカイト太陽電池の実現」(15:00~15:55)
岡山大学 教授 林 靖彦 氏
—————休憩(5分)————–
4.「ペロブスカイト太陽電池:その常識破りの物理化学と再エネ利用のパラダイムシフト」
(16:00~16:55)
東京大学 教授 瀬川 浩司 氏
5. 閉会(16:55~17:00) 関西副支部長(近畿大学) 澤井 徹
2025/08/04 関西支部研究室(大阪公立大学中百舌鳥キャンパス)探訪(2025年9月22日)開催のお知らせ
関西支部では2025年度の研究室探訪を以下のとおり開催しますのでお知らせします。
ご興味のある方はご予定くださいますようお願いいたします。
見学先:大阪公立大学中百舌鳥キャンパス
見学日時:9月22日(月)13:30~15:30(30分ほど延長の可能性あり)
見学内容(大阪公立大学, 大学院現代システム科学研究科 前田泰昭客員教授に見学内容を調整いただいています)
1)説明(30分)および質疑
・廃棄物からバイオ燃料(BDFとSAF)の製造と利用
・バイオ燃料の酸化安定性と凝固点降下へのUltrafine Bubbles の利用
・超音波反応場の不思議
2)簡単な実演(60分)
・共溶媒法での廃食用油からBDFの製造
・超音波反応場で金ナノ微粒子の調製
・水の超音波分解による過酸化水素の生成か色素の分解
3)製造したSAFのジェットエンジン燃焼試験と排ガス測定
4)溶存酸素のDOメーターでの測定とECD-GCでの測定
参加費:無料
集合場所・時間
・日時:9月22日(月)13:15
・場所:大阪公立大学中百舌鳥キャンパス東門集合
・住所:堺市中区学園町1-2号
・アクセス:https://www.omu.ac.jp/about/campus/access/
地下鉄御堂筋線なかもず駅5号出口から南東へ約1,000m、徒歩13分
南海バスの場合:南海高野線の線路西側バス停より北野田行き府大研究所前
お問い合わせ先
JSES事務局:東京都渋谷区代々木2-26-5 バロール代々木419号室
TEL:03-3376-6015 FAX:03-3376-6720
E-mail:info@jses-solar.jp
第29回スターリングテクノラリー(2025年11月29日)開催のお知らせ
第29回スターリングテクノラリーは11月29日(土)、会場は茨城県立土浦工業高校で開催しますのでお知らせします。
1 大会の目的
スターリングテクノラリーは自作スターリングサイクル機器の性能とアイデアを競う競技会であり,つぎのことを目的とする。
(1) 青少年の科学・工学に対する興味・関心の喚起し,ものづくりセンスを育てる。
(2) 工学・技術の実験場として,スターリング関連技術の発展・向上へ寄与する。
(3) 環境とエネルギー問題を解決するスターリング技術の価値と可能性をアピールする。
2 大会の名称 第29回スターリングテクノラリー
3 開催期日 記録会 2025年11月29日(土) 9:00~16:00
及び会場 会場 茨城県立土浦工業高等学校 〒 300-0051 茨城県土浦市真鍋6-11-20
TEL 029-821-1953 FAX 029-822-6924 https://www.tsuchiura-th.ibk.ed.jp/
4 参加資格 資格を問わない 。
5 競技クラス
( L ) 人間乗車クラス: 一定の走行時間(30分を予定)以内に定められた周回路を何周できるかを競う。
(RC) RCクラス: 一般舗装路面で遠隔操縦により2つのポールを周回して走行。約 50 mを走行する時間を競う。
(HW) お湯熱源クラス:湯と室温との温度差により,はば113mm、長さ5.5mの平坦な周回路を走行させ,3分間の走行距離を競う。
( M ) ミニクラス:加熱源の搭載は自由。平坦な8.8m周回路を走行する速度を競う。(車両の幅105mm以内)。
(MA) ミニ宙返りクラス: 高さ85cmの垂直ループの走行回数を競う。(車高90mm以内)
(MM) マイクロクラス:加熱源の搭載は自由。平坦な約2m周回路を走行。走行距離と車両の小ささを競う(車両の幅35mm以内 )。
( C ) 冷凍機クラス: 大気圧空気を作動ガスとする自作スターリング冷凍機
SC3 DC3V(単三乾電池×2本)を電源とする。3分間以内で吸熱端の温度降下を競う。
SC100 AC100Vを電源とし,3分間以内に規定対象物を10℃温度降下させ,電力消費量[J]の少なさを競う。
6 申込期限 2025年9月30日 当日消印有効
7 主 催 特定非営利活動法人スターリングテクノラリー技術会 https://stirling.jpn.org/
8 後援(予定) 文部科学省,経済産業省,日本工学教育協会,全国工業高等学校長協会,全日本中学校技術・家庭科研究会,スターリングエンジン普及協会,台湾・大同大學,台湾・建国科技大學,台湾・国立秀水高級工業職業学校
9 協賛(予定) 日本機械学会,精密工学会,日本設計工学会,日本太陽エネルギー学会,日本産業技術教育学会,NPO環境とエネルギー,(株)誠文堂新光社,(有)協和合金
10 各 賞 記録賞,アイデア賞 ,奨励賞
※RC,HW,MA クラスの入賞者は全国工業高等学校長協会のジュニアマイスターに申請可。
11 参加費 1台の競技登録につき1,000円 (ただし作品展示,見学は無料)
問い合わせ先
実行委員長 : 小林義行 E-mail: office@stirling-tech.sakura.ne.jp
Tel: 090-1105-9123
スターリングテクノラリー技術会 〒300-0056 茨城県土浦市木田余西台9-34
【JSME】第27回スターリングサイクルシンポジウム(2026年12月13日)開催のお知らせ
一般社団法人日本機械学会エンジンシステム部門では12月13日に明治大学駿河台キャンパスでスターリングサイクルシンポジウムを開催しますのでお知らせします
70th FRP CON-EX 2025(2025年10月29日~30日)開催のお知らせ
名 称 : 第70回FRP総合講演会・展示会
英文名称 : 70th FRP CON-EX 2025
会 期 : 2025年10月29日(水)~30日(木)
展示会場 : 秋葉原UDX (〒101-0021東京都千代田区外神田4-14-1)
講演会 - 4F ギャラリー 、 展示 - 2F アキバ・スクエア
主 催 : 一般社団法人 強化プラスチック協会 70th CON-EX 2025 実行委員会
詳細はこちら
問い合わせ : 一般社団法人 強化プラスチック協会事務局
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目9番3号 第2片山ビル6階
TEL:03-5829-3535 FAX:03-5829-3536 MAIL:frp.con-ex2025@jrps.or.jp
一般社団法人 強化プラスチック協会 https://jrps.or.jp
電話番号:03-5829-3535 メールアドレス:frp.con-ex2025@jrps.or.jp
第20回再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム(2026年1月28日(水)~30日(金))開催のお知らせ
第20回再生可能エネルギー世界展示会&フォーラムを以下のとおり開催しますのでお知らせします。
1.名称: 第20 回再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム(略称RE2026)
2.目的: 2006 年から再生可能エネルギー12 分野を網羅した展示会とフォーラムを毎年開催し、再生可能エネルギー利用の促進を技術・学術面から推進してきました。4 年に1度はフォーラムを国際会議に置き換え実施しております。
3.行事の期間(期日)及び開催場所
〇展示会: 2026 年1 月28~30 日東京ビッグサイト南ホール
〇フォーラム: 2026 年1 月28~30 日東京ビッグサイト国際会議棟会議室 RE2026 ホームページ
12分野のプログラムが確定しました。詳細はこちらからご確認ください。
4.再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム
・エネルギーイノベーション総合展
展示会はエネルギーイノベーション総合展としてENEX など複数の展示会と同時期同場所開催しています。
【JWEA】日本風力エネルギー学会第47回風力エネルギー利用シンポジウム(2025年11月27日~28日)開催のお知らせ
第47回風力エネルギー利用シンポジウムを開催しますのでご案内致します。
詳細は決まり次第、学会ホームページ及び同報メールにてお知らせ致します。
【開催日時】
11月27日(木) 09時30分~17時 依頼講演Ⅰ・Ⅱ、学会からの報告、ポスター展示
11月27日(木) 17時30分~19時 懇親会
11月28日(金) 09時~17時 一般研究発表、ポスター展示
【開催方法及び会場】
開催方法:会場及びオンライン(Zoomウェビナー)のハイブリッド開催
会場:ビジョンセンター新橋、東京都千代田区内幸町1-5-2 内幸町平和ビル
【参加費】
正会員(個人会員/団体会員)、協賛・後援団体 20,000円
学生会員、一般学生、個人会員で70歳以上の方 3,000円
一般 25,000円
懇親会(人数制限:130名) 6,000円
【各種登録期間と登録サイト】
◆演題登録(一般研究発表、ポスター展示) 8月19日(月)~9月30日(金)
※発表者は学会員(個人/団体/学生等の会員)であり、年会費を納入済みであることが条件となります。
10月31日(金)までに必要な手続き(入会、年会費支払い)をお済ませください。
入会申込書:https://www.jwea.or.jp/membership
◆参加登録 9月22日(月)~11月21日(金)
◆演題登録/参加登録サイト https://jweasympo.confit.atlas.jp/login
◆詳細については「PDF」をご参照下さい。
関係各位のご参加をお待ちしております。
問い合わせ先
一般社団法人日本風力エネルギー学会
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-12 KENTビル4階
電話:03-6284-2310 ファックス:03-6284-2320
E-mail:info@jwea.or.jp URL : https://www.jwea.or.jp
2025/08/04 2025年度研究発表会講演発表申込・参加登録の受付を開始しました.
2025年度の研究発表会講演発表の申込および事前参加の受付を開始しましたのでお知らせします。
こちらのサイトからご確認くださいますようお願いいたします。
論文発表申込期限: 9月17日(水)
論文発表受付通知: 9月30日(火)
論文原稿提出期限: 10月15日(水)
事前参加申込期限: 10月22日(水)
2025/08/01 2025年度若手研究発表会奨励賞受賞者のお知らせ
2025年7月31日にオンライン開催しました若手研究発表会の奨励賞受賞者は、発表者12名の内、以下の3名に決定しましたのでお知らせいたします。
No.5 アレイ型MultiPro-CPCの集光系設計方法と太陽集光性能の評価
田邉 壮太(東京農工大学大学院)
No.7 数値流体解析による周期極小曲面構造の熱伝達特性把握
保井 和泉(長岡技術科学大学)
No.8 スパッタ法によるHTL/BaSi2ヘテロ接合型太陽電池の作製
林 洸希(筑波大学大学院)
【環境研究総合推進費】令和8年度新規課題公募概要と説明会開催(2025年8月6日・9月12日)のお知らせ
■「環境研究総合推進費」令和8年度新規課題の公募について
【公募期間】令和7年9月8日(月)~令和7年10月10日(金)
【応募方法】府省共通研究開発管理システム(e-Rad)にて受付
※最新情報は、随時ホームページにて更新いたします。
◆推進費ホームページ 公募情報(令和8年度)
https://www.erca.go.jp/suishinhi/koubo/r08_koubo_1.html
■公募説明会の開催について 第1回 8/6(水)、第2回 9/12(金)
公募開始にあたりまして、「環境研究総合推進費」制度を広く研究者、リサーチアドミニストレーターの皆様に知っていただくため、オンラインでの公募説明会を以下のとおり開催いたします。
○第1回公募説明会(参加登録受付中)
★推進費課題を実施中の研究者様による体験談や、昨年度からの変更点をご説明いたします!
【日時】令和7年8月6日(水)14:00~15:50(予定)
【開催形態】オンライン開催(Webex)
【概要】
・重点課題・行政要請研究テーマ(行政ニーズ)の概要について(環境省環境研究技術室)
・環境研究総合推進費の概要(ERCA)
・研究プロジェクトの設計やマネジメントのアドバイス(プログラムオフィサー)
・採択研究者による体験談
・質疑応答
【対象】「環境研究総合推進費」に興味のある研究者
URA等の研究活動の企画・マネジメント等に携わる方々
【申し込みURL】
https://p-unique.webex.com/weblink/register/r6562b911378d29a53f9d355e6da868a4
【申し込み期間】令和7年8月4日(月)12時まで
○第2回公募説明会
★申請書作成のポイント、行政要請研究テーマの説明等、申請に直結する説明です!
【日時】令和7年9月12日(金)10:30~18:00(予定)
【開催形態】オンライン開催(Webex)
【概要】
・令和8年度新規課題公募の内容(ERCA)
・令和8年度新規課題公募の特徴、申請書作成の留意点等(プログラムオフィサー)
・行政要請研究テーマ(行政ニーズ)の内容(環境省)
・質疑応答
【対象】申請を予定又は検討している研究者
URA等の研究活動の企画・マネジメント等に携わる方々
※第1回と第2回では内容が一部重複いたします。
詳細やご参加のお申込みに関しましては、下記のホームページよりご確認ください。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
◆推進費ホームページ 公募説明会(令和8年度)
https://www.erca.go.jp/suishinhi/koubo/r08_koubo_3.html
————————————————————————
【お問い合わせ先】
(独)環境再生保全機構 環境研究総合推進部 担当:小林、生駒、飯塚、山野、美川
E-mail suishinhi-koubo[AT]erca.go.jp
※メールアドレスの[AT]は@に置き換えてください。
————————————————————————
2025/08/01 【New!】学会設立50周年記念事業「作文コンテスト」の応募〆切を8月18日(月)に延長します。
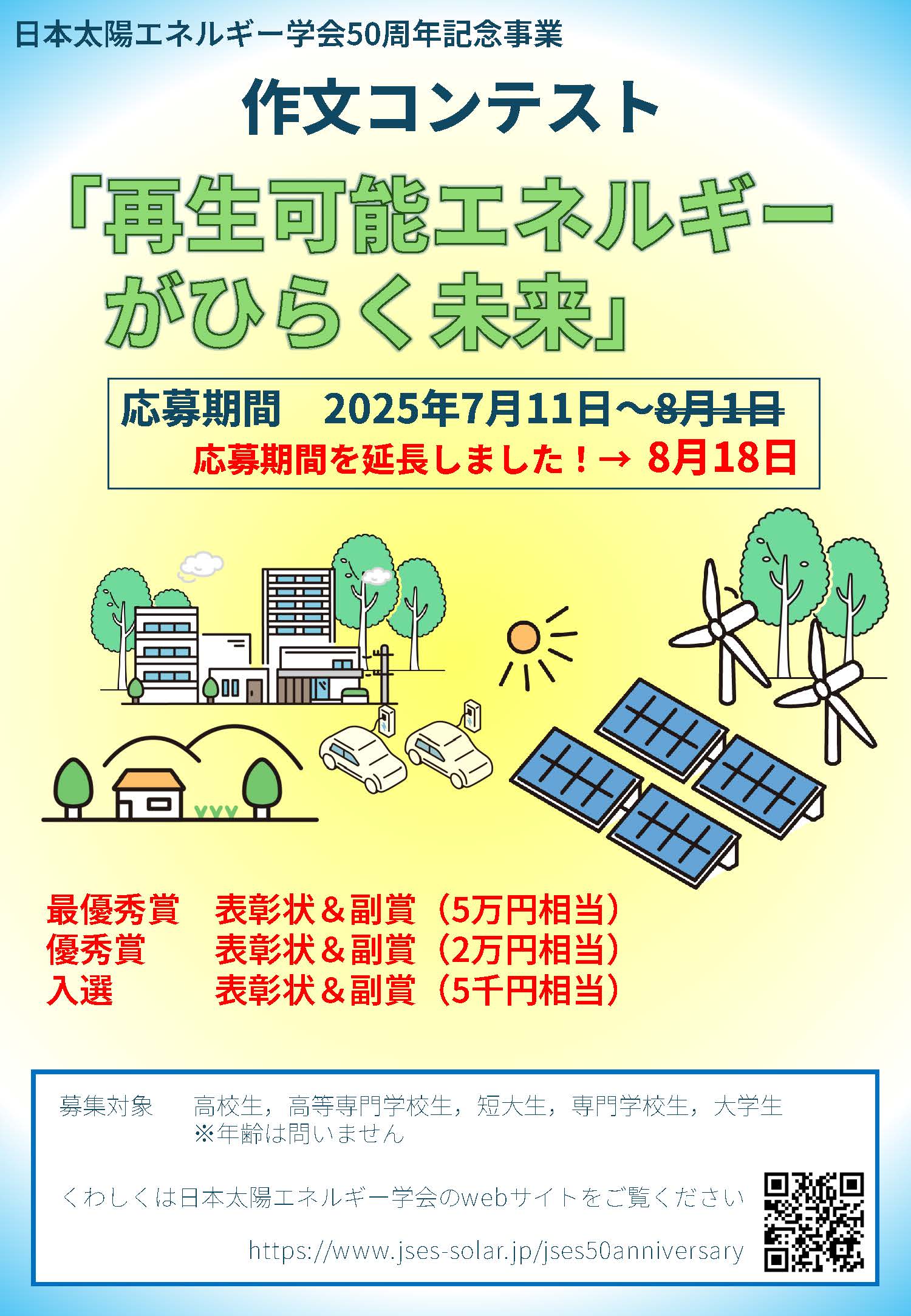 学会設立50周年記念事業の一環として実施中の、高校生から大学生までを対象とし「再生可能エネルギーがひらく未来」をテーマとした作文コンテストの応募〆切を8月18日(月)に延長します。
学会設立50周年記念事業の一環として実施中の、高校生から大学生までを対象とし「再生可能エネルギーがひらく未来」をテーマとした作文コンテストの応募〆切を8月18日(月)に延長します。
より多くの応募をお待ちしています。
詳しくは以下をご覧ください。
日本ヒートアイランド学会第20回全国大会(2025年9月19日~21日)開催のお知らせ
日本ヒートアイランド学会では以下のとおり第20回全国大会を開催しますのでお知らせします。
詳細はこちらをご確認ください。
【日本学術会議】第22回有機合成指向有機金属化学国際会議(2025年9月1日~9月6日)開催のお知らせ
会 期:令和7年9月1日(月) ~ 9月6日(土)[6日間]
場 所:ホテルグランヴィア京都(京都府京都市)
日本学術会議が第22回有機合成指向有機金属化学国際会議組織委員会及び公益社団法人日本化学会と共同主催する「第22回有機合成指向有機金属化学国際会議(The 22nd IUPAC International Symposium on Organometallic Chemistry Directed Towards Organic Synthesis)」が、令和7年9月1日(月)~6日(土)にホテルグランヴィア京都で開催されます。本会議は「生物活性物質や機能性有機材料の環境調和型高効率合成を指向した有機金属化学の新展開 」をメインテーマに、未来を担う若い研究者の国際的交流と研鑽の場となるよう多様なワークショップが企画され、多くの演題が発表されます。18年振り4回目の日本開催となる本会議には、世界44カ国・地域から約800名の研究者等が参加予定で、世界トップレベルの研究者が集結します。 また、本会議期間中に、市民公開講座「炭素と金属で拓く未来社会」をキャンパスプラザ京都で開催します。有機金属化学は、炭素と金属の結合を含む化合物を扱う学問分野であり、医農薬や機能性有機材料の製造から環境・エネルギー・資源・食料などの社会的課題の解決まで、現代社会の様々な場面で重要な役割を果たしています。本講座では、世界トップレベルの研究者である3名の先生方をお迎えし、自然に学ぶ化学の仕組みから、クリーンエネルギーを生み出す人工光合成、さらには「無用の用」を体現するナノ結晶の不思議な世界まで、専門知識がなくても理解できるよう丁寧に解説します。化学に興味のある方、将来の進路を考えている学生の皆さん、そして化学の魅力を感じたいすべての方々のご参加をお待ちしています。
第22回有機合成指向有機金属化学国際会議 市民公開講座
「炭素と金属で拓く未来社会」
日 時:令和7年9月6日(土)13:30 ~ 16:40
会 場:キャンパスプラザ京都 第3講義室
(京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939)
参加費:無料・要事前申込(https://www.kuchem.kyoto-u.ac.jp/orgchem/yorimitsu_lab/Shimin_omcos22.pdf)
※内容等の詳細は以下をご参照ください。
○国際会議公式ホームページ(https://omcos22.org/)
○市民公開講座(https://www.kuchem.kyoto-u.ac.jp/orgchem/yorimitsu_lab/Shimin_omcos22.pdf)
【問合せ先】OMCOS-22事務局
(Tell: 075-753-3985、Mail:omcos22(a)org.kuchem.kyoto-u.ac.jp)
※送信の際には(a)を@に置き換えてください
【日本学術会議】「大災害からの復興と持続的社会のモデルを目指して~半島地域からの問題提起」(2025年8月2日)開催のお知らせ
【開催案内】日本学術会議in石川 学術講演会
「大災害からの復興と持続的社会のモデルを目指して~半島地域からの問題提起」
【日時】2025年8月2日(土)13:30~17:35
【場所】金沢市アートホール(石川県金沢市本町2丁目15番1号 ポルテ金沢6F)
(ハイブリッド開催)
【主催】日本学術会議
【共催】金沢大学
【後援】石川県、北陸先端科学技術大学院大学
【開催趣旨】
令和6年1月に発生した能登半島地震は、“半島”という地域社会に甚大な被害をもたらしました。この大災害を通して、地域の脆弱性や課題が浮き彫りとなり、今後の復興と持続可能な社会の構築に向けた新たな視点が求められています。本会議は、災害からの復興過程で明らかになった課題を共有した上でこれまでの取り組みを検証し、今後必要なことを探ることを目的としています。
【プログラム】
https://www.scj.go.jp/ja/event/2025/378-s-0802.html
【参加費】 無料
【定員】対面:先着250名、オンライン:先着500名
【申込み】事前参加申込制(登録締切:7月30日(水))
下記URLよりお申し込みください。
※定員になり次第、事前申込の受付は終了します。
https://ws.formzu.net/fgen/S12764568/
【問い合わせ先】
金沢大学研究推進部研究企画課
TEL:076-264-6198
E-mail:scj-isk(a)adm.kanazawa-u.ac.jp ※(a)を@にしてお送りください。