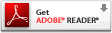2025年度若手研究発表会の講演プログラムが以下の通り決定しましたのでお知らせします。
開催日時:2025年7月31日(木) 13:00 ~ 17:30
会場:オンライン会議室(Zoom)
参加費:会員(無料)一般(3,000円) 学生(無料)
参加申込はこちら
13:00 開会挨拶 会長 若尾 真治(早稲田大学)
13:05 1.低圧直流遮断アークに対するMayrアークモデルの適用に関する研究
愛知工業大学 井戸 楓真
【概要】低圧直流遮断アーク放電に対して,Mayrモデルの適用可否を検討した。Mayrモデルの利用にはアークパラメータであるアーク時定数とアーク損失を推定する必要がある。交流遮断アークに対しては電流ゼロ点近傍の測定データからアークパラメータを推定することが一般的であるが,直流遮断アークについては,アーク電力最大点近傍の測定データを利用することでアークパラメータを推定できる可能性があることを明らかにした.
14:25 2.垂直式太陽光発電と水稲栽培を想定した営農型太陽光発電のシミュレーション評価
弘前大学 舘山 聖真
【概要】両面受光型太陽光パネルを垂直設置した営農型太陽光発電事業が注目されている。我々の開発した営農型太陽光発電シミュレーションプログラムを用いて水稲栽培における太陽光パネルの影響評価を行ったので、これを報告する。
13:45 3.末端に大容量太陽光発電システムが接続された配電系統の電圧 円線図を用いた解析手法
愛知工業大学 青山 知生
【概要】近年再生可能エネルギーの導入が加速しており 特に太陽光発電PV )装置の導入量が増加している。 PV 装置から配電系統への逆潮流電力は 系統電圧の上昇や低下を引き起こすことが知られている。筆者らは,この現象に対してベクトル図による解析を実施してきた。本手法によって単に電圧だけでなく,同時に有効電力や無効電力ひいてはPCS の制御 すべき 範囲について解析できることを明らかにした。
14:05 4.高負荷条件を想定したDCマイクログリッドにおける蓄電システム併設と再エネ利用の有効性検討 愛知工業大学 服部 広歩
【概要】本稿では,直流マイクログリッドにEV急速充電装置を接続した際の影響をシミュレーションし,蓄電池容量による太陽光発電の有効利用を検討した。蓄電池容量を増やすことでPV電力の利用率が向上し,外部電源依存度が低下することを確認した。
14:25 (休憩)
14:35 5.アレイ型MultiPro-CPCの集光系設計方法と太陽集光性能の評価
東京農工大学大学院 田邉 壮太
【概要】本研究は集光器の軸を通る全断面が複合放物面集光器(CPC)形状をとる3次元CPC(MultiPro-CPC)について、複数個並べた際に集光器間に隙間を生じないアレイ型の設計方法を開発することを目的とした。そこで、開口部の形状を長方形・六角形・ひし形として集光器を設計し、東京に設置したときの1年間の集光シミュレーションを行い、受光部面積あたりの集光量の観点で設計要素が集光性能に与える影響を分析した。
14:55 6.ヒトに「心地よさ」をもたらす光環境の季節特性
札幌市立大学大学院 村山 つばさ
【概要】ヒトに「心地よさ」をもたらす光環境の条件は、Kruithof曲線が有名であるが、快・不快の範囲が疑問視されている。筆者らは、ヒトに「心地よさ」をもたらす光環境の条件には、季節特性がありヒトの温熱感覚の要素が含まれると予想した。これまでヒトの想像温度は、外気温に基づく季節特性を有することが明らかになっている。本研究では、秋季・冬季・春季においてヒトに「心地よさ」をもたらす光環境と想像温度の関係を明らかにした。
15:15 7.数値流体解析による周期極小曲面構造の熱伝達特性把握
長岡技術科学大学 保井 和泉
【概要】太陽熱を利用した流体の加熱など、太陽熱利用システムに適用可能な新規熱7.交換構造として、三重周期極小曲面がある。本研究では、その中でも代表的なGyroid型熱交換器を対象に数値流体解析を行い、対流熱伝達性能等を従来のFins構造との比較を実施した.同様のモデルで実験を行った先行研究を参考に、解析結果の妥当性を確認し、性能の評価に加えて温度上昇に伴う熱交換器の熱変形に着目した解析も行った。
15:35 8.スパッタ法によるHTL/BaSi2ヘテロ接合型太陽電池の作製
筑波大学大学院 林 洸希
【概要】本研究では太陽電池材料として優れた特性を有するBaSi2に注目した。先行研究においては同時スパッタ法においてガラス基板上に高品質なn-BaSi2の形成を達成した。そこで本研究では、結晶Si 太陽電池で報告例のあるMoOxをホール輸送層として使用してBaSi2ヘテロ接合型太陽電池の作製を目指した。n-BaSi2と組み合わせる際に最適なMoOxの成膜条件を探索し、太陽電池動作の実証を果たした。
15:55 (休憩)
16:05 9.CNNを用いた画像解析による日射量推定法における理論日射量の利用
福井大学大学院 中村 健人
【概要】一般的にカメラに備わっている自動色調補正機能は無効化することが難しく,自動色調補正機能を用いた画像では日射量推定精度が悪化する。本研究では,畳み込みニューラルネットワーク(CNN)を用いた画像解析による日射量推定において,理論日射量の利用を提案する。理論日射量は,実測日射量および推定日射量を正規化して使用する。その結果,実測日射量の場合は日射量推定精度が向上し,推定日射量の場合は悪化した。
16:25 10.特殊巻線構造多相変圧器を用いた太陽光発電システムの自立運転時における電力品質
愛知工業大学 松永 亜香里
【概要】著者らはこれまでに系統電力を直流給配電システムで使用するための特殊巻線構造多相変圧器の開発を行ってきた。本検討ではこの変圧器を使用し,二次側に太陽光発電システムが接続されたモデルにてPCSの自立運転を行った場合を検討した。特にこのモデルにおいての電力品質について検討をおこなったので発表をする。
16:45 11.住宅用PVの導入拡大に向けた配電系統電圧制約を考慮したアグリゲータによる地域内のPV余剰活用 東京理科大学 岩科 宗純
【概要】住宅用太陽光発電は最大限の導入が目指されている一方で、固定価格買取制度の満了や買取価格低下による売電メリット減少や、逆潮流による系統電圧上昇という課題がある。本研究は、配電系統内に設置するPVシステムと定置型蓄電池の経済的合理性のある導入量の議論に向け、アグリゲータによる管理のもとにこれらを利用する需要家群を想定し、系統の電圧や設置容量を考慮してPVの活用を促進する運用手法を提案する。
17:05 12.太陽光発電の余剰電力を加味した蓄電池運用に関する検討
愛知工業大学 柴田 隼弥
【概要】気候変動問題が国際的に問題視されており、そのため世界的に再生可能エネルギーが増加し、日本ではFIT制度を導入することで、太陽光発電設備を中心に導入された。太陽光発電は分散型電源として活用でき、蓄電設備を導入することで非常時の対策として効果的である。また、太陽光発電では気象、時間帯等の要因で変動性をもつため、蓄電が必要となってくる。以上を踏まえ、本研究では停電、瞬低対策として蓄電池のSOCと太陽光発電の余剰電力を考慮した蓄電池の運用方法について行っている。
17:25 閉会挨拶 学会活性化委員長 山田 昇(長岡技術科学大学)
17:30 閉会

 学会誌
学会誌