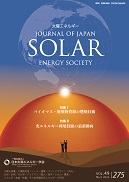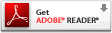一般社団法人日本太陽エネルギー学会
会員各位
2023年度研究発表会専用ページを立ち上げましたので、こちらをご確認いただき、発表の申込、参加申込をお願いします。
2023年度(令和5年度)日本太陽エネルギー学会研究発表会は11月16日~17日に開催を予定しています.昨年に引き続き現地開催を予定していますので,日頃から積み上げられてきた研究成果の発表,並びに研究情報交換に多数ご参加いただきますようご案内申し上げます.
(※COVID-19の感染状況によって開催方法が変更になる可能性があります)
講演発表会:2023年11月16日(木)~17日(金)
会場:大阪府泉佐野市エブノ泉の森ホール(現地開催)
特別講演会:2023年11月16日(木) 15:30~17:00
1.地域新電力におけるため池を活用したオフサイトPPAの意義
(一財)泉佐野電力事務局長 甲田裕武氏
2.泉佐野の3つの日本遺産と世界かんがい施設遺産について
泉佐野市教育部日本遺産推進担当理事 中岡 勝氏
※特別講演会はどなたでも無料で聴講できます.
見 学 会:2023年11月15日(水) 12:30~17:15
参加費:3,000円(酒造見学無し),5,000円(酒造見学あり)
12:30 南海電鉄泉佐野駅(北庄司酒造を見学される方12:20集合)
12:45 北庄司酒造(試飲・お土産を含めた参加費が別途2,000円かかりますので希望者のみの見学とします)
13:20 南海電鉄泉佐野駅(北庄司酒造を見学されない方13:10集合)
13:50 貝の池水上太陽光発電所(三井住友建設による解説)
15:20 犬鳴山七宝瀧寺(ガイド付)
17:15 南海電鉄泉佐野駅 解散
懇 親 会:2023年11月16日(木) 17:30~19:00 エブノ泉の森ホールレストラン泉の森開催場
・奨励賞の選考は例年どおり実施しますので、奮って応募ください。
主なスケジュール
論文発表申込期限: 9月29日(金)
論文発表受付通知: 10月13日(金)
論文原稿提出期限: 10月27日(金)
事前参加申込期限: 11月 5日(日)