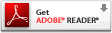会員専用ホームぺーページにて1978年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
投稿者「日本太陽エネルギー学会 Webサイト管理者」のアーカイブ
2023/10/11 学会誌「Journal of Japan Solar Energy Society (太陽エネルギー)」 Vol.49, No.5 (通巻277号)発刊のお知らせ(会員専用ページではカラー版を閲覧・ダウンロードできます)
学会誌「Journal of Japan Solar Energy Society (太陽エネルギー)」 Vol.49, No.5 (通巻277号)を発刊しました。この号では「洋上風力発電の動向・展望」が特集されています。また、「研究室紹介」の連載は「前橋工科大学 環境・デザイン領域 建築設備研究室」と「名古屋大学未来材料システム研究所 システム創成部門ネットワークシステム部」です。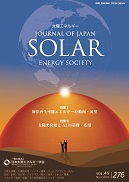
本号には以下の技術報告が収録されています。
- 太陽電池モジュールの自作/山本智弘・清田英夫・赤石崇
(学術論文・技術報告を除く各記事は1年後に閲覧可能となります。ただし、会員専用ページではカラー版の即時閲覧・ダウンロードが可能です)
目次はこちら。
2023/10/04【会員専用HP】1979年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
会員専用ホームぺーページにて1979年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
2023/10/03【会員専用HP】1980年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
会員専用ホームぺーページにて1980年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
公益財団法人ヒロセ財団 第4回ヒロセ賞受賞候補者の推薦について
公益財団法人ヒロセ財団では、2020年より新事業として「情報・通信・電気・電子工学関連分野」に対する顕彰事業「ヒロセ賞」を新設しました。第4回ヒロセ賞の推薦要項等は下記の通りです。JSES会員の方で推薦される方がいらっしゃいましたら、弊学会事務局まで連絡下さい。
1.対象者
情報・通信・電気・電子工学分野において顕著な業績をあげた日本国籍を有する研究者を対象といたします。
ただし、文化勲章受章者、文化功労者、日本学士院賞受賞者はヒロセ賞の対象にはなりません。
2.表彰内容・件数
1賞につき、賞状、賞牌、及び副賞3,000万円を贈呈(1件)
※副賞の使途の制限、及び使途の報告義務はないものとします。
3.推薦者
ヒロセ賞の推薦は、次に依頼いたします。
本財団より推薦依頼を受けた学会、大学、研究機関の長または部局長
4.推薦基準
情報・通信・電気・電子工学分野において顕著な業績を挙げた研究者とし、ヒロセ賞への推薦については、次の基準に基づいてください。
(1)新しい学術を切り拓く優れたものか(研究の独創性)
(2)他分野の研究に影響を与えるか (研究の波及効果)
(3)世の中に役立つものか (研究の有益性)
5.推薦件数
候補者の推薦は、1推薦人につき1件(原則1名)です。
※推薦人の自薦はできません。
6.推薦方法
推薦人は、推薦書に必要事項を記入したPDFファイルを作成し、本財団宛に電子ファイルを提出してください。
7.推薦締切
2023年11月30日(木)締切
※学会事務局からの応募になりますので推薦される方がいらっしぃましたら1ヶ月前までに連絡下さい。
8.選考方法
国内の学会、大学、研究機関の推薦人に対して広く公募し、候補者を募ります。
推薦人から提出された候補者について、財団に設置された選考委員会における選考を経て、理事長に報告し、理事会で決定します。
9.選考結果の通知
選考結果は、2024年2月下旬に、推薦人及び本人に文書で通知します。
10.ヒロセ賞の贈呈
第4回ヒロセ賞 贈呈式は2024年3月23日に都内にて開催いたします。
なお、受賞者には記念講演をしていただきます。
11.提出書類等
(1)推薦書(和文)のPDF形式ファイル
なお、推薦書の様式は、下記よりダウンロードしてください。
Word形式で配布しております。
(2)主要文献3篇のPDF形式ファイル
推薦書の「主要となる文献リスト」に〇印を付した文献3篇
12.推薦書提出先及びお問い合わせ先
公益財団法人ヒロセ財団
〒106-0032 東京都港区六本木1-7-27 全特六本木ビルEast5F
info (at) hirose-isf.or.jp (※ (at) は @ に置き換えて下さい)
2023/09/29【会員専用HP】1981年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
会員専用ホームぺーページにて1981年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
2023/09/27【会員専用HP】1982年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
会員専用ホームぺーページにて1982年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
広島大学教員公募(2023年11月13日締切り)のお知らせ
このたび,広島大学は地球規模課題に対応する融合 研究分野において,広島大学における「優れた大学教員の確保・育成のための方針~若手教員が安心して活躍する大学に~」に基づき雇用する 教員1名 (准教授又は助教) を国際公募します。
この公募により雇用する教員の職名は,採用時の業績審査により,准教授(テニュア(終身在職権)),テニュアトラック教員(准教授,助教)のいずれかに決定します。テニュアトラック教員として雇用された場合で,テニュアトラック期間満了までにテニュア審査に合格することを条件として ,准教授としてテニュア(終身在職権)を取得できる新たなポストとなっています。新たな分野を切り開く研究計画提案のもとに,腰を据えて教育研究に専念していただくことを前提としています。
したがって,採用時の審査においては,それまでの教育研究業績の審査に加え,テニュアトラック期間に留まらず10 年程度の中長期的な研究計画の内容について審査します。テニュア審査においては,その過程の到達度と将来の展望を加味して総合的に審査します。
広島大学は,採用されたテニュアトラック助教に対して スタートアップ 支援経費を措置します。また,メンター教員の配置等により教員が自立して研究活動を行うことのできる環境を整備しています。なお,テニュアが付与されなかった場合に,テニュアトラック期間の満了する日の翌日から 1 年を限度として,特任教員として雇用できる環境も整えています。
広島大学の理念,長期ビジョン,中期目標(https://www.hiroshima-u.ac.jp/about)にご賛同いただき,広島大学の教育研究を背負ってご活躍いただける意欲のある方をお待ちしております。
広島大学長 越智光夫
2023/09/19 日本太陽エネルギー学会・共生エネルギー社会実装研究所 合同シンポジウム「100%再エネ時代に向けて地域と共生する太陽光発電」(2023年10月18日)開催のお知らせ
カーボンニュートラルに向けて太陽光発電の拡大を図り,再エネの増強・CO2排出量の低減を進めることが重要な課題です.一方で,大規模太陽光発電を規制する地域も現れています.FIT/FIP制度後に太陽光発電の実装が定着するためには,地域と共生し,再エネ利用が地域の発展に寄与する社会的仕組みづくりが不可欠と言えます.そこで本シンポジウムでは,太陽光発電をさらに導入するにあたり,地域の産業や社会と再エネをどのように結びつけるか,専門家・実践家の皆様から実践的事例を含めて講演していただき,多角的な視点から問題を議論します.
日程: 2023年10月18日(水)13:30〜16:30
場所: 千代田区立 日比谷図書文化館 大ホール
東京都千代田区日比谷公園1-4
https://www.library.chiyoda.tokyo.jp/hibiya/
ハイブリッド開催予定
主催: 一般社団法人 日本太陽エネルギー学会
一般社団法人 共生エネルギー社会実装研究所
1.プログラム
13:30-13:35 開会挨拶 日本太陽エネルギー学会100%再生可能エネルギー部会長
秋澤 淳(東京農工大学)
第一部:地域と産業への貢献
13:35-13:55 FIT後の太陽光発電による地域発展モデルとは
重藤 さわ子(事業構想大学院大学)
13:55-14:15 ソーラーシェアリングによる地域農業との連携
小山田 大和(合同会社 小田原かなごてファーム)
14:15-14:35 地域エネルギー会社の役割と実践
乾 正博(シン・エナジー株式会社)
14:35-14:55 総合討論
14:55-15:05(休憩)
第二部:さらなる拡大に向けた課題
15:05-15:25 地域と共生する太陽光発電:企業や自治体の取り組み
石田 雅也(公益財団法人 自然エネルギー財団)
15:25-15:45 V2H(ビークルtoホーム)の普及と再エネとの連携
櫻井 啓一郎(国立研究開発法人 産業技術総合研究所)
15:45-16:05 地域と調和する再エネの拡大を考える
安田 陽(京都大学)
16:05-16:25 総合討論
16:25-16:30 閉会挨拶 共生エネルギー社会実装研究所所長
堀尾 正靭(東京農工大学名誉教授)
2.参加費
日本太陽エネルギー学会会員:2,000円
共生エネルギー社会実装研究所関係者:2,000円
一般:3,000円
学生:無料(ただし,会場で学生証を提示して参加の場合)
3.申し込み方法
事前に下記のチケット購入サイトからお申し込み下さい.
(Peatix) https://peatix.com/event/3705931
4.お問合せ
本シンポジウムに関するお問合せは下記までご連絡ください.
共生エネルギー社会実装研究所 事務局長 木科大介
E-mail: jimukyoku@erises.org
2023/09/19 イベントカレンダー機能を追加しました。
JSES HPのホーム画面 最下部に各種イベント情報をカレンダー上に表示する様にしましたのでお知らせします。
イベント情報は JSESのイベント情報や申込の締切り情報、後援・協賛イベント情報、関連団体のイベント情報をカレンダー上に表示していますのでご利用いただきますようお願いいたします。
日本太陽エネルギー学会 広報委員会
2023/09/14【会員専用HP】1983年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
会員専用ホームぺーページにて1983年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
第18回再生可能エネルギー世界展示会(2024年1月31日~2月2日)&フォーラム(2024年1月22日~30日)開催のお知らせ
特定非営利活動法人再生可能エネルギー協議会では第18 回再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム (略称RE2024)を以下の通り開催しますのでお知らせします。
目的: 持続可能な社会を創り上げていくために、2006 年から再生可能エネルギー12 分野を網羅した展示会を毎年、国際会議を4 年ごとに、国際会議の無い年度は12 分野のフォーラムをそれぞれ開催し、今回で18 回目になります。昨年度は国際会議を開催しましたので、今年度は、展示会とフォーラムの年度です。年を追うごとにエネルギーのクリーン化、地球環境保全への必要性、そして脱炭素社会を目指した取り組みが高まっております。展示会では広く一般市民に最新技術や研究成果を公開することを目的にしており、フォーラムでは分野ごとの話題に精通した講師をお招きし最新技術の講演を展開します。再生可能エネルギーと省エネルギーを車の両輪として、ENEX とも共同開催し、脱炭素社会を目指した総合エネルギー展&フォーラムを展開します。SDGsにも貢献していきます。
開催期間(期日)及び開催場所
〇展示会 : 2024 年1 月31 日~ 2 月2 日 東京ビッグサイト東ホール
〇フォーラム: 2024 年1 月22~30 日(12 分野1 系列で土日を除き順次実施、オンラインで開催)
詳細は以下のURLをご確認下さい。
https://www.low-cf.jp/east/index.html
【JST・RISTEX】第7回 RISTEX総合知オンラインセミナー 「学際研究/共創型研究のすすめ」 Special !! ~人文・社会科学は社会の役に立つ?!文化人類学・心理学・哲学の挑戦(2024年1月22日)開催のお知らせ
【開催案内】第7回 RISTEX総合知オンラインセミナー
「学際研究/共創型研究のすすめ」 Special !!
~人文・社会科学は社会の役に立つ?!文化人類学・心理学・哲学の挑戦
社会の具体的問題の解決や科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題ELSIへの対応に資する社会技術の研究開発を推進しているJST-RISTEX(社会技術研究開発センター)は、学際研究/共創型研究を進めるうえでヒントとなる情報を発信・共有するための総合知オンラインセミナーを開催しています。
第7回は、ビジネス界における人文・社会科学の専門知の活用と実践にフォーカスをあて、文化人類学・心理学・哲学の専門知を武器にビジネスの現場で課題解決に取り組んでいるフロントランナー3名をゲストにお迎えし、各分野における取組の実践等についてご講演いただきます。
今回のセミナーは人文・社会科学の新たな可能性について考える特別回です。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
<開催概要>
●開催日時: 2024年1月22日(月)17:00~18:50
●開催形式: オンライン(Zoom)
●定員: 500名(無料・先着順)
●講師: 大川内直子 氏(株式会社アイデアファンド 代表取締役社長)
澤井大樹 氏(株式会社イデアラボ 代表取締役)
吉田幸司 氏(クロス・フィロソフィーズ株式会社 代表取締役社長)
●対象: (1)学際研究/共創型研究に関心がある研究者
(2)研究推進に携わるURA、大学・研究機関・民間企業等の職員、
省庁・助成団体関係者等
(3)人文・社会科学の活用・実践に関心がある学生
●参加申込締切: 2024年1月19日(金)13:00
●詳細・参加申込:
https://www.jst.go.jp/ristex/info/event/20240122_01.html
<本件のお問い合わせ先>
国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)
社会技術研究開発センター(RISTEX)
総合知オンラインセミナー事務局
E-mail: r-info-event@jst.go.jp
表面科学技術研究会2024「カーボンニュートラルを目指して -太陽光発電と風力発電の現状と将来展望-」(2024年1月18日)開催のお知らせ
表面技術協会、日本表面真空学会 関西支部では下記研究会の開催を予定しておりますのでお知らせします。
表面科学技術研究会2024「カーボンニュートラルを目指して -太陽光発電と風力発電の現状と将来展望-」
開催日時:2024年1月18日(木) 13:00 ~ 17:20
場所:地方独立行政法人 大阪産業技術研究所 森之宮センター 大講堂 + オンライン配信(Zoom)
2023/09/06【会員専用HP】1984年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
会員専用ホームぺーページにて1984年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
【JIE】第19回バイオマス科学会議(2023年12月7日~9日)開催のお知らせ
日本エネルギー学会 バイオマス部会では以下の通り第19回バイオマス科学会議を開催しますのでお知らせします。
世界のエネルギー消費量の増加や戦争などの国際情勢に伴う化石燃料の高騰が進む昨今,国内の再生可能エネルギーに対する期待が高まっています。特に,他の再生可能エネルギーとは異なり燃焼利用やガス化など多様な利用方法があり,貯蔵も容易なバイオマス資源の利活用は,2050年のカーボンニュートラル実現に向けて重要な役割を果たすと考えられます。
第19回バイオマス科学会議は,2023年12月7日,8日に秋田市にて開催します。秋田は多くの森林資源を有し,マテリアル利用に向けた木材加工の産業が多く,東北最大級のバイオマス専焼発電所が稼働しています。また,稲作が盛んであることから草本系バイオマスの賦存量も多く,もみ殻の熱利用も進んでいます。バイオマス利活用が盛んな秋田で開催するバイオマス科学会議に是非皆様のご参加を賜り,活発にご質疑・ご討論いただけましたら幸いです。皆さまのご参加,ご発表を心よりお待ちしております。
開催日:2023年12月7日 (木)~12月9日 (土)
会場:にぎわい交流館AU(秋田市中通一丁目4番1号)
アクセス:https://www.akita-nigiwai-au.jp/access
開催方法:現地にて開催。オンラインは実施しません。
【JIE】第11回アジアバイオマス科学会議(2023年12月6日)開催のお知らせ
持続可能な社会の実現に向けてバイオマスの利活用は大きな役割を果たすことが期待されています。様々なバイオマス資源に恵まれたアジア,特に東南アジア諸国では食料と競合しない未利用バイオマスのエネルギー・マテリアル等への転換利用は化石資源代替と環境保全の点からも重要な課題です。このような観点から,日本エネルギー学会バイオマス部会が主導してアジア諸国のバイオマス資源の有効利用等に関して学術的に議論することを目的とした国際会議として,「アジアバイオマス科学会議」を2013年度から開始し、国内外(高知、つくば、新潟、ペナン、仙台、ボゴール、郡山、オンライン2回、タイ・ハイブリッド)でこれまでに10回開催しました。今年度は4年ぶりの国内での対面形式で、12月に秋田市にぎわい交流館AU(あう)で開催いたします。使用言語は英語ですので、留学生の方の研究発表,海外との共同研究の成果公表などに是非ご利用下さい。なお,希望者の発表論文は査読の上,Journal of the Japan Institute of Energy の特集号に掲載の予定です。ご参加、ご発表を心よりお待ちしております。
【第11回アジアバイオマス科学会議】
11th Asian Conference on Biomass Science
主催: 日本エネルギー学会 バイオマス部会
Organized by Biomass division, The Japan Institute of Energy
開催日程:2023年12月6日(水)
会場:秋田市にぎわい交流館AU(あう)
6 December 2023 (Akita, Japan)
ご発表,ご参加をお待ちいたします。
We are looking forward to seeing you through presetantion or participation.
開催案内、発表募集、参加募集、プログラムの日本語版はこちらから
Announcement, call for paper, recruiment for participation and program in English is click here.
【日本機械学会】第25回スターリングサイクルシンポジウム(2023年12月2日)開催のお知らせ
第25回スターリングサイクルシンポジウム ―ポストコロナ社会とスターリングサイクル機器―
【開催日】 2023年12月2日(土)
【会 場】 明星大学 日野キャンパス(コロナウイルス蔓延の状況によっては開催形式が変更になることもあります)
東京都日野市程久保2丁目1−1
【問合せ先】 第25回スターリングサイクルシンポジウム実行委員会
E-mail: stirling2023@jsme.or.jp
詳細は以下のurlからご確認下さい
https://www.jsme.or.jp/event/23-64/
【JWEA】第45回風力エネルギー利用シンポジウム(2023年11月30日~12月1日)開催のお知らせ
第45回風力エネルギー利用シンポジウムを下記の通り開催しますのでご案内致します。関係各位のご参加をお待ちしております。
【主催】
一般社団法人日本風力エネルギー学会
【協賛(予定)】
一般社団法人日本小形風力発電協会、一般社団法人日本風力発電協会(五十音順)
【後援(予定)】
国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、一般財団法人新エネルギー財団、一般社団法人ターボ機械協会、公益財団法人日本科学技術振興財団、一般社団法人日本風工学会、一般社団法人日本太陽エネルギー学会、一般社団法人日本電機工業会、風力発電推進市町村全国協議会(五十音順)
【開催日時】
2023年11月30日(木)9時30分~17時30分 依頼講演、ポスター発表
12月1日(金)9時~17時 一般研究発表、ポスター発表
11月30日(木)17時30分~19時 懇親会
【開催方法及び会場】
開催方法:会場及びオンライン(Zoom ウェビナー)のハイブリッド開催
会場:科学技術館サイエンスホール(地下2階)及び6階会議室
東京都千代田区北の丸公園 2-1
アクセス:https://event-jsf.jp/access
【参加費】
日本風力エネルギー学会正会員(個人会員/団体会員)・協賛・後援団体 20,000円
会員学生・一般学生・個人会員で70歳以上の方 3,000円
一般 25,000円
懇親会(人数制限:80名) 5,000円
【参加登録期間】
9月25日(月)~11月24日(金)
【参加登録方法】
下記の専用サイト「Confit」からお申し込み下さい。
https://jweasympo.confit.atlas.jp/login
※お支払い方法は「バーチャル口座(銀行振込)またはクレジット決済」とさせていただきます。
【お問合せ専用窓口】
専用スタッフが対応させていただきます。
窓口業者名:(株)ソウブン・ドットコム
メール:sympo_jwea@soubun.biz
電話:03-3893-0111
【環境省】令和5年度地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業成果発表会(2024年1月15日)開催のお知らせ
環境省では、「地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業(環境省R&D事業)」において、将来的な地球温暖化対策の強化につながるCO2排出削減効果の高い優れた技術の開発・実証を、民間企業、公的研究機関、大学、自治体等から広く提案を募集し、委託又は補助により実施しております。
この度、この「技術開発・実証事業」について広く情報提供を行い、優れた技術を社会に普及させ、更なる開発・実証を推進するため、成果発表会を令和6年1月15日(月)に開催いたします。
また、12月25日に報道発表がされましたので、その旨お知らせいたします。
【環境省成果発表会ホームページ】
https://www.env.go.jp/press/press_02575.html
成果発表会に関する問合せについては、以下の事務局まで御連絡ください。
<成果発表会事務局>
○ 一般社団法人国際環境研究協会 成果発表会受付係
【メール】:seika2023@airies.or.jp
【日本学術会議】第5回 RISTEX総合知オンラインセミナー「学際研究/共創型研究のすすめ」( 2023年11月30日)開催のお知らせ
■——————————————————————–
【開催案内】 第5回 RISTEX総合知オンラインセミナー
「学際研究/共創型研究のすすめ」
~人文学(者)は何をしたいのか? オープンヒューマニティーズという試み
——————————————————————–■
社会の具体的な問題の解決や科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への対応に資する社会技術の研究開発を推進しているRISTEX(社会技術研究開発センター)は、学際研究/共創型研究を進めるうえでヒントとなる情報を発信・共有するための総合知オンラインセミナーを開催しています。
第5回は、人文学・人文学者の視点にフォーカスをあて、東京大学大学院人文社会系研究科 教授/連携研究機構 ヒューマニティーズセンター 機構長齋藤希史氏をゲストにお迎えし、オープンヒューマニティーズという試みについて御講演いただきます。
皆様の御参加を心よりお待ち申し上げます。
<開催概要>
●開催日時: 2023年11月30日(木)16:00~17:00
●開催形式: オンライン(Zoom)
●定員: 300名(無料・先着順)
●対象: (1)学際研究/共創型研究に関心がある研究者
(2)研究推進に携わるURA、大学・研究機関・民間企業等の職員、
省庁・助成団体関係者等
●参加申込締切: 2023年11月29日(水)13:00
●詳細・参加申込:
https://www.jst.go.jp/ristex/info/event/20231130_01.html
<本件のお問い合わせ先>
国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)
社会技術研究開発センター(RISTEX)
総合知オンラインセミナー事務局
E-mail: r-info-event@jst.go.jp
【FREA】太陽光発電システムの運転データ分析に関する基礎セミナー(2024年1月12日)開催のお知らせ
FREAでは、以下のとおり「太陽光発電システムの運転データ分析に関する基礎セミナー」を開催しますのでお知らせします。
https://www.aist.go.jp/fukushima/ja/pvom/pvom2024/0112.html
〇開催時期:2024年1月12日(金)13:30~16:00
〇開催方式:オンライン
〇講師:講師:東京理科大学 植田 譲 教授(外部講師)
〇プログラム:
13:30~15:30
・太陽光発電システムの発電特性の基礎
・発電量の損失要因
・システム運転データの分析方法
・発電性能評価に利用可能なデータの紹介
・I-Vカーブの分析方法の事例紹介
15:30~16:00 質疑
〇参加申込締切:2024年1月5日(金)17:00
https://forms.office.com/r/Z7i498WcxQ
【JST】大学発新産業創出基金事業における令和5年度提案の募集のお知らせ
【公募開始】大学発新産業創出基金事業における令和5年度提案の募集
「ディープテック・スタートアップ国際展開プログラム」
「スタートアップ・エコシステム共創プログラム」
https://www.jst.go.jp/program/startupkikin
大学等発スタートアップ創出力の強化を目的とした「大学発新産業創出基金事業」において、下記プログラムの公募を開始しました。
●公募期間
【ディープテック・スタートアップ国際展開プログラム】
2023年8月29日(火)~11月30日(木)正午
【スタートアップ・エコシステム共創プログラム】
2023年8月29日(火)~10月26日(木)正午
詳細につきましては、上記の大学発新産業創出基金事業ホームページに掲載している公募要領をご覧ください。
●関連イベントのご案内
提案募集に関連し、以下のイベントを開催いたします。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
①公募説明会
上記2つのプログラムの公募概要を説明いたします。
・開催日時:2023年9月12日(火)15:00-16:10(予定)
・開催形態:オンライン(Zoomウェビナー) 参加無料
詳細は、大学発新産業創出基金事業ホームページおよび以下をご覧ください。
https://form2.jst.go.jp/s/startupkikin2023
②研究者と事業化推進機関のマッチング支援イベント「事業化推進機関PR会」
ディープテック・スタートアップ国際展開プログラムへの応募を検討中の研究者に向けて、ベンチャーキャピタルやコーポレートベンチャーキャピタル、アクセラレータ等の事業化推進機関となりうる機関が事業化の実績や強みなどをPRするイベントを実施いたします。
・開催日時:2023年9月22日(金)10:00-17:00(予定)
・開催形態:オンライン(Zoomウェビナー) 参加無料
詳細は以下をご覧ください。
https://www.jst.go.jp/program/startupkikin/deeptech/pr-event202309.html
<お問い合わせ>
【ディープテック・スタートアップ国際展開プログラム】
JST スタートアップ・技術移転推進部 スタートアップ第1グループ
E-mail:start-boshu@jst.go.jp
【スタートアップ・エコシステム共創プログラム】
JST スタートアップ・技術移転推進部 スタートアップ第2グループ
E-mail:su-ecosys@jst.go.jp
【独立行政法人 環境再生保全機構】「環境研究総合推進費」令和6年度新規課題公募の進捗状況のお知らせ
10月17日に公募を締め切らせて頂き、現在審査中です。 公募の進捗情報は、X(ツイッター)を中心にお知らせしていきますので以下からご確認ください。
1.アカウント名:ERCA 環境研究総合推進費
2.アカウントID: @ERCA_suishinhi
3.URL: https://twitter.com/ERCA_suishinhi
4.発信内容:環境研究総合推進費の公募関連情報
研究成果報告、プレスリリース
研究機関主催のイベント
ERCA主催イベント情報等
■「環境研究総合推進費」令和6年度新規課題の公募のお知らせ
【公募期間】令和5年9月13日(水)13時-10月17日(火)13時
【応募方法】府省共通研究開発管理システム(e-Rad)にて受付
◆推進費ホームページ 公募情報(令和6年度)
https://www.erca.go.jp/suishinhi/koubo/r06_koubo_1.html
■公募説明会を開催します(参加申込受付中)
◆推進費ホームページ 公募説明会(令和6年度)
https://www.erca.go.jp/suishinhi/koubo/r06_koubo_3.html
【AIST】FREA 太陽光発電設備の電気安全・保安に関するセミナー(2023年11月20日)開催のお知らせ
今回は、いつもと少し趣向を変えて、政策の動向についてのご講演をいただくとともに、
太陽光発電事業の実態と課題について参加者の皆様との意見交換を中心とした企画にしています。
ご興味ありましたら、ぜひご参加いただければ幸いです。
————————————————————–
太陽光発電設備の電気安全・保安に関するセミナー
https://www.aist.go.jp/fukushima/ja/pvom/pvom2023/1120.html
○開催時期:2023年11月20日(月)10:00~12:00
○開催方式:ハイブリッド(現地&オンライン【座学部分のみ】)
○講師:経済産業省 電力安全課 課長補佐 丸山 晴生 氏 (外部講師)
〇プログラム:
10:00~10:30【講演】太陽光発電設備に関連する電気安全・保安に関する政策の動向について
10:30~12:00【意見交換】太陽光発電事業の実態と課題について
○参加:無料
〇参加申込締切:2023年11月13日(月)17:00
https://forms.office.com/r/ayMbgTcAEK
2023 白浜ECO-CAR チャレンジ(2023年11月18日~19日)開催のお知らせ
この度、旧白浜空港滑走路を利用したエコカー・イベント【2023 白浜ECO-CAR チャレンジ】を行います。エネルギー事情、原発問題、温室効果ガスなどの課題を抱える日本において、代替エネルギー・クリーンエネルギーの普及が重要視されている中で、2050 年のカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現の可能性をアピールするイベントです。大会では、完全CO2 フリーのソーラーカーや小型バッテリーを使用したエコノムーブなどが⾛⾏いたします。
例年、日本国内では鈴⿅サーキットや秋田県大潟村でエコカー大会が開催されており、数多くの学生チームや一般チームが参加しています。ソーラーカー・エコノムーブは市販⾞ではないため、オリジナル設計かつ手作りで仕上げられます。
自作ができない部品は加工依頼先、サポート・スポンサード企業などとの打合せを通して製作されるため、学生にとっては総合的な社会経験が出来る場でもあります。特に本イベントでは、大会技術員が⾏う⾞検にて学生チームは各部の確認以外にも設計について、改良についてのアドバイスを受けられ、勝ち負けや⾛る性能だけでなく、考え方や作り方に至るまでエンジニア育成にもつながる大会となっています。
<大会概要>
名 称︓ 2023 白浜 ECO-CAR チャレンジ
日 程︓ 2023 年11 月18 日(土)・19 日(日)
会 場︓ 旧南紀白浜空港跡地特設コース(1 周 約2400m)
〒649-2211 和歌⼭県⻄牟婁郡白浜町2926-23
主 催︓ 白浜 ECO-CAR チャレンジ 大会実⾏委員会
※大会当日の様子はYouTube にて配信される予定です。URL は大会公式Facebook ページでご案内します。
<開催部門と⾛⾏内容>
・ソーラーカー部門︓ソーラーパネルを搭載した⾞両による競技で規定時間内に⾛る距離を競う。
・WEM 部門︓通称WEM(World Econo Move)、小型バイクのバッテリーを用いて規定時間内に⾛る距離を競う。
・白浜EVエコラン部門︓新クラス・乾電池40本、小型バイクのバッテリーを用いて規定時間内に⾛る距離を競う。
・その他の⾞両︓主催者が認める、その他のEV ⾞両等
◇総参加チーム数・・・2022 年実績は21 チーム
<大会に関するお問い合わせ先>
白浜ECO-CAR チャレンジ 大会事務局 〒663-8156 兵庫県⻄宮市甲子園網引町1-18
E-mail︓nomnom13@yahoo.co.jp
大会公式Facebook ページ︓ https://www.facebook.com/Shirahama.Eco.Car.Challenge
https://shirahamaecocar.wixsite.com/–ecocar
日本熱物性シンポジウム2023(2023年11月7~9日)開催のお知らせ
第 44 回日本熱物性シンポジウムを,11 月 7 日(火)~9 日(木)の 3 日間に渡り,千葉県習志野市の日本大学生産工学部津田沼キャンパスにて開催致します.
習志野市は,東京から電車で1時間程度の距離の住宅・オフィス街ですが,千葉県の東は銚子,南は館山まで豊かな自然にも恵まれて,千葉県産の農産物と,日本酒も多数の銘柄があり,とても美味しいです.新型コロナは,今後は第5類感染症になる見込みで,講演と意見交換会を4年ぶりに対面で開催いたします.
多くの方々が集まれるように準備いたしますので,皆様の多数ご参加を心よりお待ちしております.
主催 日本熱物性学会
開催日:2023 年11 月7 日(火)~ 9 日(木)
一般講演 特別講演・総会会場:日本大学 生産工学部 津田沼キャンパス39 号館
意見交換会会場:日本大学 生産工学部 津田沼キャンパス39 号館2 階カフェテリア
詳細は以下のURLをご確認ください
HP: http://jstp-symp.org/symp2023/index.html
【AIST】太陽光発電設備の構造安全関係のデモンストレーション(杭基礎の載荷試験)(2023年11月2日)開催のお知らせ
太陽光発電設備の構造安全関係のデモンストレーション(杭基礎の載荷試験)
https://www.aist.go.jp/fukushima/ja/pvom/pvom2023/1102.html
○開催時期:2023年11月2日(木)13:00~16:00(雨天の場合は2023年11月13日(月)に順延します)
○開催方式:ハイブリッド(現地&オンライン【座学部分のみ】)
○講師:一般社団法人 構造耐力評価機構 高森 浩治 氏(外部講師)
〇プログラム:
13:00~14:00 本セミナーの概要説明
14:00~15:30 デモンストレーション(現地&オンライン【座学部分のみ】)
15:30~16:00 質疑応答
○参加:無料
〇参加申込締切:2023年10月26日(木)17:00
https://forms.office.com/r/EZZGTHVYCg
第27回スターリングテクノラリー(2023年11月18日)開催のお知らせ
1 大会の目的
スターリングテクノラリーは自作スターリングサイクル機器の性能とアイデアを競う競技会であり,つぎのことを目的とする。
(1) 青少年の科学・工学に対する興味・関心の喚起し,ものづくりセンスを育成する。
(2) 工学・技術の実験場として,スターリング関連技術の発展・向上へ寄与する。
(3) 環境とエネルギー問題を解決するスターリング技術の価値と可能性を不特定多数に衆知する。
2 大会の名称 第27回スターリングテクノラリー
3 開催期日 2023年11月18日(土) 9:00~16:00
会場 茨城県立土浦工業高等学校 〒 300-0051 茨城県土浦市真鍋6-11-20
TEL 029-821-1953 FAX 029-822-6924 https://www.tsuchiura-th.ibk.ed.jp/
4 参加資格 資格を問わない 。
5 競技クラス
(L)人間乗車クラス: 一定の走行時間(30分を予定)以内に定められた周回路を何周できるかを競う。
(RC) RCクラス: 一般舗装路面で遠隔操縦により2つのポールを周回し,約 50 mを走行する時間を競う。
(HW) お湯熱源クラス:湯と室温との温度差により,はば113mm、長さ5.5mの平坦な周回路を走行させ,3分間の走行距離を競う。
(M) ミニクラス:加熱源の搭載は自由。平坦な8.8m周回路を走行する速度を競う。(車両の幅105mm以内)。
(MA) ミニ宙返りクラス: 高さ85cmの垂直ループの走行回数を競う。(車高90mm以内)
(MM) マイクロクラス:加熱源の搭載は自由。走路幅42mm,約2m平坦な周回路を走行。走行距離と車両の小ささを競う(車両の幅35mm以内 )。
(C) 冷凍機クラス: 大気圧空気を作動ガスとする自作スターリング冷凍機
SC3 DC3V(単三乾電池×2本)を電源とする。3分間以内で吸熱端の温度降下を競う。
SC100 AC100Vを電源とし,3分間以内に規定対象物を10K温度降下させる電力消費量の少なさを競う。
6 申込期限 2023年9月29日 当日消印有効
7 主 催 スターリングテクノラリー技術会 (会長:松尾政弘 埼玉大学名誉教授)
8 後援(予定) 文部科学省, 経済産業省, 日本工学教育協会, 全国工業高等学校長協会,
全日本中学校技術・家庭科研究会, スターリングエンジン普及協会, 埼玉大学,
台湾・大同大學, 台湾・建国科技大學, 台湾・国立秀水高級工業職業学校,
台湾・台北市立南港高級工業職業学校,
9 協賛(予定) 日本機械学会,精密工学会,日本設計工学会,日本太陽エネルギー学会,
日本産業技術教育学会, NPO環境とエネルギー,(株)誠文堂新光社,(有)協和合金
10 各 賞 記録賞,アイデア賞
※RC,HW,MA クラスの入賞者は全国工業高等学校長協会のジュニアマイスターに申請可。
11 参 加 費 1台の競技登録につき1,000円 (ただし作品展示,見学は無料)
問い合わせ先
スターリングテクノラリー技術会 〒300-0056 茨城県土浦市木田余西台9-34
スターリングテクノラリー公式ページ http://www.stirling.jpn.org/
実行委員長 : 小林義行 E-mail office@stirling-tech.sakura.ne.jp
TEL 029-821-1605 FAX 029-826-3523(茨城県立土浦第三高等学校)
【AIST】事業用太陽光発電設備の使用前自己確認の研修(電気関係)(2023年10月30日)開催のお知らせ
事業用太陽光発電設備の使用前自己確認の研修(電気関係)
https://www.aist.go.jp/fukushima/ja/pvom/pvom2023/1030.html
○開催時期:2023年10月30日(月)13:00~17:00
○開催方式:ハイブリッド(現地&オンライン【座学部分のみ】)
○講師:東京電気管理技術者協会 千葉支部長 鈎 裕之 氏(外部講師)
〇プログラム:
13:10~14:10 【座学】事業用太陽光発電設備の使用前自己確認の方法に関する講義
14:10~14:20 実験室に移動、休憩
14:20~15:50 実験室にて試験の実演
15:50~16:00 FREAホールに移動、休憩
16:00~17:00 データのまとめ方に関する講義及び質疑応答
○参加:無料
〇参加申込締切:2023年10月23日(月)17:00
https://forms.office.com/r/72ZC2Y2Dw3
【JST】ムーンショット型研究開発事業における公開シンポジウム(2023年10月29日)開催のお知らせ
科学技術振興機構(JST)では、ムーンショット型研究開発事業の目標8(2050 年までに、激甚化しつつある台風や豪雨を制御し極端風水害の脅威から解放された安全安心な社会の実現)において、これまで進めてきた研究開発についてご紹介するとともに、この研究開発を皆さまと議論しながら進めるための一つの機会として、公開シンポジウムを開催することとなりました。
https://www.jst.go.jp/moonshot/ (ムーンショット型研究開発事業)
https://www.jst.go.jp/moonshot/program/goal8 (目標8)
[会合概要]
会合名:ムーンショット目標8公開シンポジウム2023
2050年の極端風水害の低減に向けて -社会とともに歩む気象制御-
開催日時:10月29日(日)13:00-17:00
開催場所:富士ソフトアキバプラザ5F アキバホール(〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3)
JR秋葉原駅より徒歩2分(https://www.fsi.co.jp/akibaplaza/map.html)
開催方式:現地参加/オンライン(Zoomウェビナー)
使用言語:日本語
URL:https://www.jst.go.jp/moonshot/sympo/20231029/index.html
会合では研究プログラムを構成している8つのプロジェクトの各リーダーからの研究開発の紹介と質疑応答を予定しています。
参加を希望される皆様は上記URLから10月25日(水)12:00までに事前登録をお願いいたします。
(オンライン参加の方の登録はシンポジウム終了まで受け付けています。)
関心をお持ちの皆様のご参加を心よりお待ちしております。
問合せ先:科学技術振興機構 ムーンショット型研究開発事業部
目標8担当 E-mail:moonshot-goal8@jst.go.jp
【強化プラスチック協会】68th FRP CON-EX 2023(2023年10月26日~27日)開催のお知らせ
68th FRP CON-EX 2023(第68回 FRP総合講演会・展示会)
今年は浜松市福祉交流センターで、昨年同様対面式にて開催します。
今回も多数の関連学会・協会の協賛を頂く予定です。コロナによる休止回を含め、第68 回となります。
FRP CON-EX は、繊維強化プラスチック(FRP)業界の活性化を図る総合講演会・展示会です。高強度・高弾性率・軽量・高耐久性を有し、かつ自在な設計ができる材料FRP はユーザーニーズに応えることのできる優れた材料です。今回のCON-EX 2023 でも、特別講演、キーノート講演、招待講演、一般講演、ポスターセッション、展示及び技術交流会を予定しています。是非多くの方のご参加をお願い致します。
【開催概要】
●主 催 一般社団法人 強化プラスチック協会
●会 期 2023 年 10 月26 日(木)、27 日(金)
●会 場 浜松市福祉交流センター(JR 新幹線浜松駅北口より徒歩10 分)
●協 賛 関連学会・協会約 65 団体
【技術交流会】
●日 時 2023 年 10 月 26 日(木)17 時 15 分より
●会 場 ホテルクラウンパレス浜松(開催会場より徒歩13 分、JR 新幹線浜松駅北口より徒歩3 分)
詳細はこちらをご確認ください
【AIST】太陽光発電設備支持物の確認方法に関する研修(2023年10月23日)開催のお知らせ
太陽光発電設備支持物の確認方法に関する研修
https://www.aist.go.jp/fukushima/ja/pvom/pvom2023/1023.html
○開催時期:2023年10月23日(月)13:00~16:00(雨天決行)
○開催方式:ハイブリッド(現地&オンライン【座学部分のみ】)
○講師:一般社団法人 構造体力評価機構 代表理事 高森 浩治 氏 (外部講師)
〇プログラム:
座学:13:00~15:00 使用前自己確認方法:構造関係(オンラインあり)
実技:15:00~16:00 目視確認ポイント
○参加:無料
〇参加申込締切:2023年10月16日(月)17:00
https://forms.office.com/r/5hXL6KqyAc
日本冷凍空調学会年次大会(2023年9月6日~8日)開催のお知らせ
主 催:公益社団法人日本冷凍空調学会
会 期:2023年9月6日(水)~8日(金)
会場:日本大学理工学部駿河台校舎タワースコラ
詳細は以下URLをご確認下さい
https://jsrae-nenji.org/nenji2023/
2023/08/24【会員専用HP】1985年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
会員専用ホームぺーページにて1985年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
[JST/JICA] 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS) 令和6年度 研究提案募集開始(10月23日正午締切り)のお知らせ
国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)は、地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)において、令和6年度の研究提案を募集しています。
【募集期間】 令和5年8月22日(火)~ 令和5年10月23日(月)正午
※公募期間が例年よりも2週間早まりました。
【詳細情報】 https://www.jst.go.jp/global/koubo/index.html
本プログラムは、科学技術と外交を連携し、相互に発展させる「科学技術外交」の強化の一環として、文部科学省・外務省の支援のもと、JSTと国際協力機構(JICA)が連携して実施するものです。
開発途上国のニーズを基に、地球規模課題を対象とし、社会実装の構想を有する国際共同研究を政府開発援助(ODA)と連携して推進します。
本プログラムでは地球規模課題の解決および科学技術水準の向上につながる新たな知見や技術を獲得することや、これらを通じたイノベーションの創出を目的としています。また、その国際共同研究を通じて開発途上国の自立的研究開発能力の向上と課題解決に資する持続的活動体制の構築を図ります。
(注) SATREPSはODAとの連携事業です。
JSTへの研究課題の応募とともに、相手国研究機関から相手国のODA担当省庁を通じ、日本政府に対する技術協力要請が行われる必要があります。
※ODA要請書の提出期限は10月13日(金)中(日本時間)です。
■公募概要(予定)
*応募要件:
日本国内の大学や研究機関、企業などに所属して、国際共同研究の研究代表者としての責務を果たし、全期間において国際共同研究に従事できること。
その他、責務等も記載していますので、公募要領の記載内容をご理解のうえ応募してください。
*対象分野:
環境・エネルギー/生物資源/防災
(注) 感染症分野については、平成28年度より国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)が公募を行っています。詳しくは、AMEDの公式サイト(https://www.amed.go.jp/koubo/20/01/2001B_00069.html ) をご参照ください。
*研究期間:3~5年間
*予算規模:1課題あたり、1億円程度/年
(内訳)JST:委託研究経費3,500万円程度/年
JICA:ODA技術協力経費6,000万円程度/年
■公募説明会(JST、JICA主催)
オンライン会議システムZoomを利用したウェビナー形式で公募説明会を開催いたします。
説明会参加には、事前登録が必要です。下記リンクより事前登録を行ってください。
※登録時に入力いただくご氏名、ご所属・役職、メールアドレスは、参加登録の確認のみに使用し、他の用途で使用することはございません。
日時: 2023年8月29日(火) 14:00~16:00 (環境・エネルギー/生物資源/防災分野)
登録用URL:https://zoom.us/webinar/register/WN_T_1tWdgXTpO1cmKEjkx93g#/registration
内容:JSTとJICAより、本プログラムの概要、公募に関するご案内、経費の枠組みなどについてご説明する予定です。
■お問い合わせ先
国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)
国際部SATREPSグループ 担当:土屋、柳井
e-mail: global@jst.go.jp 電話: 03-5214-8085
【日本機械学会】第16回 新☆エネルギーコンテスト(2023年10月21日)開催のお知らせ
第16回新☆エネルギーコンテスト
詳細は以下のurlをご確認ください。
https://www.jsme.or.jp/event/23-82/
1.開催期日:令和5年10月21日(土)
2.会 場:Web開催,
開催本部:日本大学工学部(福島県郡山市田村町徳定字中河原1番地)
3.主 催
新☆エネルギーコンテスト実行委員会
一般社団法人 日本機械学会 技術と社会部門【日本機械学会分野連携企画 No.32】
4.日本大学工学部機械工学科実行委員会
佐々木直栄(委員長),田中三郎,宮岡大(幹事)
5.主 旨
新☆エネルギーコンテストは、日本機械学会 技術と社会部門が協力するイベントとして、2008年に始められた大学・高専の学生を主な対象とする「エネルギー利用に関する」新しいコンテストです。
第16回(2023年度)を迎える本年度は、10月21日(土)に、昨年度に引き続き、Web開催(開催本部:日本大学工学部)において、日本機械学会 技術と社会部門の主催(日本機械学会分野連携企画 No.51)で開催されることとなりました。
2011年3月11日に発生した東日本大震災の被災地では、電気、ガス、水などの供給が長期間かつ広範囲にわたって停止状態となり、エネルギー自立・自然共生型の住環境の必要性を改めて実感させられることになりました。
そこで、「第16回 新☆エネルギーコンテスト」では、前回に引き続き、エネルギー自立・自然共生型住環境の実現に不可欠な、太陽、風力、地熱、木質系バイオマスなどの新☆エネルギーの有効な利用方法(冷凍、空調、給湯、調理など)のアイディアを提案してもらいます。また、応募対象者に制限は設けないこととし、展示・実演部門とポスター部門の2部門に分けて、新☆エネルギーの有効な利用方法に関するアイディアを広く募集します。
6.エントリー部門
(1)展示・実演部門、(2)ポスター部門
7.問合せ先
〒963-8642 福島県郡山市田村町徳定字中河原1番地
日本大学工学部 機械工学科 新☆エネコン実行委員 宮岡大
TEL:024-956-8810,FAX:024-956-8860(共通)
E-mail:miyaoka.futoshi@nihon-u.ac.jp
【ISEP】4DHフォーラム国際シンポジウム「スマートエネルギーシステムによる熱の脱炭素化の最前線」(2023年10月20日)開催のお知らせ
世界的な脱炭素化の動きの中で地域での自然エネルギー100%への転換が進み始めています。
デンマークなど欧州各国では早くからスマートなエネルギー利用のために地域分散型の地域熱供給などのスマートエネルギーシステムを各地域に導入し、自然エネルギー100%へ向けたエネルギー転換をいち早く進めて来ました。
この国際シンポジウムでは、欧州での先進的な第4世代地域熱供給やスマートエネルギーシステムへの具体的な取り組みについて国際的な第一人者であるHenrik Lund教授から聞くとともに、世界で進む地域エネルギーの脱炭素化への最前線や日本国内での地域の脱炭素化への取り組みなどについて情報を共有し議論します。
日時:2023年10月20日(金)14:00~16:00(13:30開場)
会場:TKP市ヶ谷カンファレンスセンター ホール5C(定員70名)&オンライン(Zoomウェビナー)
主催:NPO法人環境エネルギー政策研究所(ISEP)
共催:一般社団法人 全国ご当地エネルギー協会
協賛:自然エネルギー100%プラットフォーム
後援:一般社団法人日本太陽エネルギー学会
協力:デンマーク大使館
助成:独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金
参加費:無料(要申込)
プログラム・参加申込み:https://www.isep.or.jp/event/14490
なお、4DHフォーラムでのこれまでのセミナー等の資料や録画はこちらのページからご覧いただけます。https://www.isep.or.jp/4dh-forum
プログラム:※変更される場合があります
14:00 開会挨拶 4DHフォーラム座長:中田俊彦(東北大学) 司会:松原(ISEP)
14:10 基調講演「スマートエネルギーシステムと第4世代地域熱供給(4DH)」(仮)50分間
Henrik Lund(オールボー大学 教授)
15:00 パネル討論「熱の脱炭素化に向けた地域の取組み」(仮)(50分間)
コーディネータ: 飯田哲也(ISEP所長)
報告1: 田島誠(ISEP,ORES)「脱炭素先行地域での4DHへの取組み」10分
報告2: 中田俊彦(東北大学) 「地域エネルギー需給データベースと地域での取組み」(仮)10分
報告3: 加用現空(東京都市大学)「PED ”Positive Energy District”への取組み」(仮)10分
ディスカッション
16:00 閉会
【AIST】2023年太陽光発電設備(直流部)の実践的保守技術研修(2023年10月18日)開催のお知らせ
2023年太陽光発電設備(直流部)の実践的保守技術研修
https://www.aist.go.jp/fukushima/ja/pvom/pvom2023/1018.html
○開催時期:2023年10月18日(水)9:00~16:00(雨天の場合は翌日に順延)
○開催方式:現地開催
○講師: 株式会社島電気商会 北川孝太郎 氏(外部講師)
株式会社アイテス 戸田祐介 氏(外部講師)
日本カーネルシステム株式会社 平尾和幸 氏(外部講師)
産総研 再生可能エネルギー研究センター 太陽光システムチーム 主任研究員 加藤和彦
産総研 再生可能エネルギー研究センター 太陽光システムチーム テクニカルスタッフ 池田一昭
〇プログラム:
9:10 ~9:30 保守点検のための安全装備(株式会社島電気商会 北川孝太郎 氏)
9:30 ~10:30 保守点検全般および対地絶縁抵抗測定(産総研 再生可能エネルギー研究センター 太陽光システムチーム 主任研究員 加藤和彦)
10:30~10:40 休憩
10:40~11:10 接地抵抗測定(産総研 再生可能エネルギー研究センター 太陽光システムチーム テクニカルスタッフ 池田一昭)
11:10~11:30 ストリングのインピーダンス測定など(株式会社アイテス 戸田祐介 氏)
11:30~12:00 赤外線カメラ観察(株式会社島電気商会 北川孝太郎 氏)
12:00~13:00 昼休み
13:00~14:00 ストリングの電流-電圧(I-V)特性曲線とその測定(日本カーネルシステム株式会社 平尾和幸 氏)
14:00~16:00 FREA太陽光発電設備を対象とした測定の実演
16:00 閉会
○参加:無料
〇参加申込締切:2023年10月11日(水)17:00
https://forms.office.com/r/aqYZip1hyK
【ウェビナー】問われるバイオマス発電:改定EU再生可能エネルギー指令は森を守れるのか(2023年9月29日)開催のお知らせ
FoE Japanでは、9月29日、EUの再生可能エネルギー指令改正に関し、特にバイオマスに焦点を当てた以下のオンラインセミナーを開催します。
ぜひご参加いただければ幸いです。
——————
【ウェビナー】問われるバイオマス発電:改定EU再生可能エネルギー指令は森を守れるのか
https://foejapan.org/issue/20230831/14197/
2022年9月、欧州議会においてEUの再生可能エネルギー指令(Renewable Energy Directive)の改定案(REDIII)が可決されました。
改定にあたり、森林由来のバイオマス燃料の扱いが大きな焦点となりました。バイオマス燃料の需要拡大が、森林破壊の原因になることが危惧されたからです。製材や丸太などの材を燃料から除外すること、熱電併給ではない発電所については補助金を中止していくこと、一次林の保護やバイオマスのカスケード利用の原則などが盛り込まれました。
その後、欧州議会、欧州委員会、欧州理事会の三者協議で緩和された部分もあり、国際的な環境NGOは、「十分な内容とは言えない」と厳しい視線を向けています。
一方で、日本ではバイオマス発電の拡大に伴い、海外からのバイオマス燃料の輸入が急増しています。しかし、FIT(固定価格買取制度)の事業計画策定ガイドラインにおける持続可能性に関する規定はあいまいであり、森林破壊を回避できるような内容とはなっていません。気候変動や生物多様性の危機が加速する今、私たちに何が問われているのでしょうか。
このたび、欧州ベースのNGO・Fernの森林・気候変動・バイオエネルギーのキャンペーナーであり、REDIIIの議論のモニタリングに取り組んでこられたMartin Pigeonさんをお迎えし、EUの改定再生可能エネルギー指令(REDIII)の概要、その成果と課題についてお話しいただきます。あわせて、欧州の状況をもとに日本のバイオマス発電に関する政策を考えていきます。みなさまのご参加をお待ちしております。
日時:2023年9月29日(金)15:30-17:00
※オンライン会議システムzoomを利用
※同時通訳あり
プログラム(敬称略):
・イントロダクション
・日本のバイオマス発電の問題点(小松原和恵/FoE Japan)
・EU REDIIIの最新情報-成果と課題とは?( Martin Pigeon/Fern)
・コメント(満田夏花/FoE Japan)
・質疑応答
主催・問い合わせ先:国際環境NGO FoE Japan
協力:地球・人間環境フォーラム、バイオマス産業社会ネットワーク、Fair Finance Guide Japan、ウータン・森と生活を考える会
▼詳細・申込はこちら
https://foejapan.org/issue/20230831/14197/
【日本学術会議】国際シンポジウム「持続可能な社会のための科学と技術に関する 国際会議『壊滅的災害に対してレジリエントで持続可能な社会への変革』」
9月7日(木)、8日(金)に「持続可能な社会のための科学と技術に関する国際会議『壊滅的災害に対してレジリエントで持続可能な社会への変革』」を開催します。
【開催趣旨】
国のあり方に大きな変化を与えるような壊滅的災害が生じても、それを乗り越え、より良く復興できる社会へと変容できる力を社会全体が蓄えることが求められています。
本年は関東大震災100周年に当たり、この会議は、震災後100年間に我が国が経験し学んできたことを、巨大地震、津波、巨大サイクロン等で被災した国や地域の経験と合わせて振り返り、国際社会と共有し、伝承し、国際協力の糧とすることを目的としています。
【主催】日本学術会議(国際委員会 持続可能な社会のための科学と技術に関する国際会議2023分科会)
【共催】防災減災連携研究会ハブ(JHoP)、防災科学技術研究所(NIED)
【日時】2023年9月7日(木)10:00-16:40
2023年9月8日(金) 9:30-17:05
※共に日本時間
【使用言語】英語(日英同時通訳あり)
当日はZOOMウェビナー上で質問も可能ですので、ぜひご登録の上、ご視聴ください。
(日)https://www.scj.go.jp/ja/int/kaisai/jizoku2023/ja/index.html
(英)https://www.scj.go.jp/ja/int/kaisai/jizoku2023/index.html
◆参加登録はこちらから(要登録、視聴無料、定員500名)
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6VkPzvKqTWmt1OwpoXciGg#/registration
※本件問い合わせ先
持続可能な社会のための科学と技術に関する国際会議2023運営事務局
(株式会社プライムインターナショナル内)
E-mail:icsts2023@pco-prime.com
営業日・営業時間(月)~(金)10:00-17:00 ※土・日・祝日はお休み
———————————————————————–
2023/08/18【会員専用HP】1986年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
会員専用ホームぺーページにて1986年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
2023/08/16【会員専用HP】1987年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
会員専用ホームぺーページにて1987年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
2023/08/15【会員専用HP】1988年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
会員専用ホームぺーページにて1988年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
2023/08/08 学会誌「Journal of Japan Solar Energy Society (太陽エネルギー)」 Vol.49, No.4 (通巻276号)発刊のお知らせ(会員専用ページではカラー版を閲覧・ダウンロードできます)
学会誌「Journal of Japan Solar Energy Society (太陽エネルギー)」 Vol.49, No.4 (通巻276号)を発刊しました。この号では「海洋再生可能エネルギーの動向・展望」および「太陽光発電とAIの基礎・応用」が特集されています。また、「研究室紹介」の連載は「静岡大学工学部電気電子工学科 松尾研究室」と「公立諏訪東京理科大学機械電気工学科 渡邊研究室」です。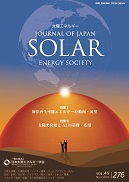
本号には以下の論文が収録されています。
- ヘルシナイト・セリアによるフォームデバイスを利用した二段階炭酸ガス熱化学分解実験/小山佳子・伊藤謙人・太田祥斗・中倉満帆・児玉竜也・Kent J. WARREN・Alan W. WEIMER・松原幸治
(学術論文を除く各記事は1年後に閲覧可能となります。ただし、会員専用ページではカラー版の即時閲覧・ダウンロードが可能です)
目次はこちら。
2023/08/03【会員専用HP】1989年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
会員専用ホームぺーページにて1989年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
2023/08/02 2023年度若手研究発表会奨励賞受賞者のお知らせ
2023年7月28日にオンライン開催しました若手研究発表会の奨励賞受賞者は、発表者11名の内、以下の3名に決定しましたのでお知らせいたします。
No.1 太陽光発電及び電力需要の予測と電力需給結果の関係性について
佐藤聖史(東京大学大学院)
No.6 太陽光発電・蓄電池・電気自動車を連携させたZEH住宅の実証
モデル住宅を対象とした数値シミュレーションによる検討
佐藤 廉(前橋工科大学大学院)
No.11 n-BaSi2膜のデバイス応用に向けた正孔輸送層の探索
青貫 翔(筑波大学大学院)
2023/08/01【会員専用HP】1990年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
会員専用ホームぺーページにて1990年研究発表会の各講演論文のPDFダウンロードが可能になりました。
【JST】ムーンショット型研究開発事業における国際シンポジウム(2023年8月28日)開催のお知らせ
−8月28日(月)に国際シンポジウムを開催します!!(参加登録締切:8月21日(月))−
科学技術振興機構(JST)では、ムーンショット型研究開発事業の目標8(2050 年までに、激甚化しつつある台風や豪雨を制御し極端風水害の脅威から解放された安全安心な社会の実現)の研究開発の現状と今後の方向性について国内外に発信するため、海外の著名研究者を招き、国際シンポジウムを開催することとなりました。
https://www.jst.go.jp/moonshot/ (ムーンショット型研究開発事業)
https://www.jst.go.jp/moonshot/program/goal8 (目標8)
[会合概要]
会合名:International Symposium on Theory of Weather Controllability
開催日時:8月28日(月)10:00ー15:30
開催場所:神戸大学統合研究拠点コンベンションホール
(〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町7丁目1-48)
開催方式:現地参加/オンライン(Zoomウェビナー、YouTube Live)
使用言語:英語
URL:https://www.jst.go.jp/moonshot/sympo/20230828/index.html
今回の会合では、数理科学的、理論的側面から気象制御の可能性を探ることに重点を置いた講演、パネルディスカッションを予定しています。参加を希望される皆様は上記URLから8月21日(月)までに事前登録をお願いいたします。
関心をお持ちの皆様のご参加を心よりお待ちしております。
問合せ先
科学技術振興機構 ムーンショット型研究開発事業部
ムーンショット目標8担当
E-mail:moonshot-goal8@jst.go.jp
【日本学術会議】学術フォーラム「SDGsの達成に資するESDカリキュラムの開発」(2023年8月20日)開催のお知らせ
【日時】2023年8月20日(日)13:00~17:00
【場所】日本学術会議講堂(オンライン配信)
【主催】日本学術会議
【開催趣旨】
国連の持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた取組が広がり、小中高の教科書でも多く取り上げられています。これを成功させるには、多くの国際持続性研究プログラムを束ねるフューチャー・アースとの連携とともに、幅広い環境教育で実績のあるESD(持続可能な開発のための教育)の推進が重要です。そのようなSDGsに資するESDカリキュラムの開発について、研究者や教員の報告を参考に皆で考えましょう。中高生、大学生、一般の皆様も是非ご参加ください。
【プログラム】
https://www.scj.go.jp/ja/event/2023/340-s-0820.html
【参加費】無料
【申込み】要・事前申込み。以下のURLからお申し込みください。
https://form.cao.go.jp/scj/opinion-0231.html
【問合せ先】
鈴木康弘(名古屋大学減災連携研究センター、resilience.nagoya@gmail.com)