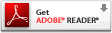幼い頃、窓辺に置かれた小さなソーラーフラワーが私の心をそっとつかんだ。それが「再生可能エネルギー」という言葉につながるとは知らなかった。地球はエアコンが備わっている。太陽は大気や海を穏やかに巡り、植物がCO2を吸収して炭素の循環を整える。しかし、今、そのエアコンは不調をきたしている。大気中のCO2濃度は、産業革命前の1.5倍に相当し、地球の平均気温は1.1℃上昇(WMO.2023)。異常が日常に近付きつつある。このまま進めば、2100年までに気温は最大4.4℃上昇するかもしれない。先日、家庭用エアコンの掃除すると中は真っ黒だった。長年の汚れが、健康被害などのリスクをもたらすと知っていたはずなのに、見ないふりをしていた。地球のエアコンも同じで、CO2の蓄積は、先送りや無関心の代償だ。もちろん、私一人が節電したところで地球規模の課題は解決しない。しかし、大きな誰かだけに委ねていても変化は小さい。蛍が集まりやがて星空を灯すように、小さな種が森を育むように、一つ一つの努力が希望の種を育て、未来を照らす。技術、社会、個人が連動しそれぞれの役割を行うことが必要だ。再生可能エネルギーは、化石燃料のように地球を傷つけず、自然の流れを「借りる」ことで力を得る。たとえば太陽光。長野県の南牧村では、丘の上にたくさんのソーラーパネルが並んでいて、村の電気の一部をまかなっているそうだ。光を受けて、パネルが静かに働く姿は、まるで太陽が「だいじょうぶ。ここにいるよ。」と見守ってくれているようだった。風の力も頼もしい。北海道苫前町では、海辺の風車が強い風をとらえて、地域の暮らしを支えている。再生可能エネルギーの可能性は大きいが、道は平坦ではなく岩や洪水が立ち塞がることも多い。太陽光や風力は天候に左右され、安定供給が難しい。パネルや風車の設置には資金が必要で、地域の反対も時に壁となる。地熱は掘削の技術が、水力は適した地形が求められる。それでも、種は芽吹き、蓄電池のコストは2010年から80%減少し(IEA, 2023)、沖縄では太陽光と蓄電池のマイクログリッドが停電時でも街を灯す。一方で、技術だけでは限界がある。制度の後押しや、企業の意思決定、地域との対話がなければ、 社会に根付かない。たとえば、イオン株式会社は店舗屋上にパネルを設置し、自社で電力の一部を賄っている。こうした動きが加速するには、政府による研究支援や税制の後押しが欠かせない。地域、企業、政府が響き合えば、大きな変化が生まれ、それらは個人から成っている。個人が意識を高め合うことでより強い効果が期待できるだろう。あのソーラーフラワーは、そっと教えてくれた。太陽の光は、ただそこにあるだけで命を動かす力を持つ。風は自由に吹き、地熱は静かに脈打ち、水は絶えず流れる。自然の力は、私たちが耳を傾ければ、地球のエアコンを修復する工具となる。再生可能エネルギーは、CO2を減らす技術を超え、子どもたちに残す未来の選択だ。あの小さな花が示したように、答えはすでに目の前にあり、自然の恵みは作物にとどまらず世界を動かすエネルギーとなる。その光を手に取る時がきている。
HOME >
JSES設立50周年記念事業特設ページ >
日本太陽エネルギー学会設立50周年記念「作文コンテスト」のお知らせ > 入選・(株)関電工賞:千田立煌さん(青森私立山田高等学校広域通信課程)