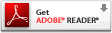資源エネルギー庁が提示している2025年6月版のエネルギー動向によると、(https://www.enecho.meti.go.jp/about/energytrends/202506/pdf/energytrends_all.pdf)石油・天然ガス・石炭等のエネルギーが供給され、電気や石油製品等に形を変える発電・転換部門を経て、私たちが最終的に消費するという流れになっていることがわかる。この際、発電・転換部門で生じるロスも含めた全てのエネルギー量を「一次エネルギー供給」、最終的に消費者が使うエネルギー量を「最終エネルギー消費」という。その差が発電や輸送中のロス等であり、2023年度は約35%が発電等の段階で損失していることになる。
この原因となっているのが一次エネルギー供給である石油や天然ガス、石炭、太陽光、風力、原子力等がそのまま使用されず、と電力や都市ガス、石油製品等の形態に転換されることにある。この損失の要因には以下のものがある。
- 火力発電の熱効率が40%前後。
- 送電線での抵抗によってロスが生まれる。
- 古い発電設備やインフラによるエネルギーの無駄発生。
この課題を解決する鍵が再生可能エネルギーであるといえる。そもそも自然の力を直接利用するため、発電・転換の過程でのロスが少ないという利点がある。例えば、太陽光発電や風力発電は、燃焼を伴わずに電力を生み出すため、熱損失がほとんどない。また、分散型エネルギーとして地域で発電・消費されることで、送電ロスも最小限に抑えられる。
資源エネルギー庁の報告によれば、2023年度の再生可能エネルギーの導入が着実に増加しており、中でも太陽光と風力の伸びが顕著である。また、2025年2月に採択された「第11次電力需給基本計画」では、2038年までに再エネ比率を29%程度に拡大する方針が示されている 。
再生可能エネルギーのもう一つの利点は、地域資源を活用した分散型エネルギー供給が可能である点だ。これにより、地域の自立性を高めることができる。例えば、徳島県では小水力発電やバイオマス発電の導入が進められており、農業用水路や森林資源を活用した地域主導のエネルギー供給が実現している。こうした取り組みは、地域経済の活性化にもつながり、持続可能な社会の構築に貢献することになる。
再生可能エネルギーの普及には、技術革新が不可欠であるが、現在研究されているものに以下のようなものがある。
- ペロブスカイト太陽電池:軽量で柔軟性があり、建物の壁面や曲面にも設置可能。福島県Jヴィレッジに設置され、実証実験が進められている 。
- スマートグリッド:AIやIoTを活用して、電力の需給をリアルタイムで最適化。エネルギーの無駄を減らし、安定供給を実現する。
- 水素エネルギー:再エネ由来の電力で水を電気分解し、水素を製造。燃料電池車や発電に利用され、カーボンニュートラルの実現に貢献する。
これらの技術は、エネルギー転換の効率を高めるだけでなく、エネルギーの多様化と脱炭素化を同時に進める鍵となる。
その他、国立研究開発法人新エネルギ-・産業技術総合開発機構省エネルギー部によると、(https://www.nedo.go.jp/content/100927347.pdf)高温ヒートポンプの研究開発をするにあたって課題となる安価な産業用ヒートポンプシミュレーターの開発が不可欠だが、それが実現に向けて進んでもいる。
再生可能エネルギーがひらく未来は、単なるエネルギー供給の変革にとどまらず、社会全体の構造や価値観の転換をも促すものである。特に、地域分散型のエネルギー供給体制が進むことで、地方自治体や地域コミュニティがエネルギー政策の主体となり、地域の自立性と持続可能性が高まる。これは、災害時のレジリエンス向上にもつながり、電力の途絶による影響を最小限に抑えることが可能となる。
また、再生可能エネルギーの普及は、若者や地域住民の雇用創出にも寄与する。例えば、太陽光パネルの設置やメンテナンス、バイオマス燃料の供給管理など、地域密着型の仕事が増えることで、地方の人口減少対策にもつながる。徳島県のように、農業や林業と連携したエネルギー供給モデルは、地域資源の有効活用と経済活性化の両立を実現している。ただし、専門性をつけなければならないという課題も存在する。こうなると、教育の変革も求めなければならないといえる。現在私は探究活動をしているが、それは糖尿病対策、人権課題解決、赤十字活動、新聞作成による報道、イノベーション教育活動、アントレプレナー養成など多岐にわたる。当然休日などないのだが、50分授業7時間5日間に模試に英検に課題にという従来のものも減ることがない。それでも社会変革を起こしたい、未来を切り開くために努力したいと考えている。ただ、時間がない。その時間の確保、授業内容の精査といったことも必要になってくるといえる。
再生可能エネルギーが単なる「電力の供給源」ではなく、地域社会の活性化、雇用の創出、そして持続可能な未来の構築に向けた多面的な可能性を秘めている以上、教育も含め、政策支援と技術開発を両輪として、地域と連携した取り組みを加速させることが求められるといえる。そしてそれを支えるのが私たち高校生以下の世代であるのだ。