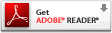(J-Stageへ)
- 期日:2025年11月2日(日),3日(月)
- 会場:明治大学 駿河台キャンパス リバティータワー(〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1丁目1−1)
- 開催概要はこちら
11月2日(日)
学会設立50周年記念特別講演会( 14:30~17:15,1083教室)
- 開会の辞:副会長 太田 勇(ミサワホーム総合研究所)
- 来賓祝辞
- 韓国太陽エネルギー学会 会長 (ビデオメッセージ)
- 日本エネルギー学会 会長 佐藤 康司 氏
- 日本風力エネルギー学会 会長 永尾 徹 氏
- 日本太陽エネルギー学会 第9代会長 藤井 石根 氏
- 会長講演「日本太陽エネルギー学会のこれまでとこれから」 日本太陽エネルギー学会 会長 若尾 真治(早稲田大学)
- 記念事業「作文コンテスト」「絵画コンテスト」について
- 「作文コンテスト」受賞者の発表
- 「絵画コンテスト」投票のお願い
- 特別講演1「気候の危機にどう向き合うか」 東京大学未来ビジョン研究センター 教授 江守 正多 氏
- 特別講演2「環境倫理学入門」 東京大学大学院・新領域創成科学研究科 教授 福永 真弓 氏
- 閉会の辞:副会長 吉永 美香(名城大学)
セッションA1(9:10~10:30):太陽光発電システム(日射・発電評価)
| 1 |
|
土地利用と建物分布からみた小規模野建て太陽光発電の導入に関する一検討 |
| |
|
※加藤丈佳(名古屋大学) |
| |
|
景観や自然災害に十分に配慮した小規模な野建て設備は,太陽光発電の更なる導入拡大のための有効な手段と考えられる.本研究では,土地利用および住宅等の建物分布に関するメッシュ統計データに基づき,建物が存在するエリアに隣接する小規模な野建て設備の導入可能性について基礎検討を行う. |
| 2 |
|
GISと地図情報を活用した都市部の駐車場における広域的なPVポテンシャルの把握 |
| |
|
※荒谷悠汰,植田譲,崔錦丹(東京理科大学) |
| |
|
本研究ではオープンストリートマップの駐車場データを活用し、東京都23区における駐車場の広域的なPVポテンシャルを評価した。都市のPVシステム導入における主要課題である日陰の影響はGIS上でDEMおよびDSMデータを用いて日陰損失補正係数として算出した。GIS解析では考慮できない天候要因には気象庁の日射量から発電量への変換モデルと補正係数を組み合わせ日陰と天候を考慮した発電ポテンシャルを評価する。 |
| 3 |
|
再解析データを利用した機械学習を用いた日射予報モデルの汎用性評価 |
| |
|
※高松尚宏,大関崇,大竹秀明(産業技術総合研究所) |
| |
|
日射予報において、数値予報モデルを入力とした機械学習モデルが利用することで、数値予報モデルの精度を向上させることが可能であることが知られている。しかしながら、機械学習モデルは過去のデータに依存することから、時間経過によりモデルが新しい状況に対応できなくなる陳腐化する可能性がある。本研究では、長期再解析データを利用することで、機械学習モデルの時間経過に対する汎用性を評価することを検討する。 |
| 4 |
|
実用的条件を考慮したANNを用いた太陽光発電電力推定 |
| |
|
※押元真和,脇坂颯,宮原由紀,滝川浩史(豊橋技術科学大学),平塚元久,白坂敬之助(株式会社エイム) |
| |
|
本研究室では,太陽光発電設備における発電量の短期予測を目的としたシステムの開発を進めている。本システムでは,雲影モニタにより予測した水平面日射量および環境変数を入力として,ANN(人工ニューラルネットワーク)により発電電力を間接的に推定する。本研究では,この発電電力推定ANNにおける各入力変数が出力に与える影響を解析し,実運用を想定した条件下での予測精度向上を検討した。 |
セッションA2(10:40~12:20):太陽光発電システム(システム評価)
| 5 |
|
積雪寒冷地におけるコンビニエンスストアの断熱改修に関する研究 その4 太陽光発電によるエネルギー自給率の分析 |
| |
|
※野村彩夏,森太郎,大沢飛智(北海道大学) |
| |
|
2010年度の省エネ法改正によりエネルギー管理は事業場単位から企業全体へと移行し、コンビニエンスストア(以下、CVS)においても省エネの重要性が高まっている。またCVSの新規出店数が減少する現在では既存店舗における省エネルギー対策の強化が求められている。本研究では札幌市のCVSを対象に電力消費量を分析した。またEnergyPlusで壁面に入射する日射量を算出した上で太陽光パネルの発電量を推定し、電力消費量に占める割合を検討した。 |
| 6 |
|
ZEB 認証の都心部建物における周辺建物の日影を考慮した 太陽光発電システムの発電量の検討 |
| |
|
※宋城基(広島工業大学),中塚一喜(三晃空調) |
| |
|
本研究では、大阪市内にあるZEB認証を受けた都市型建築物における太陽光発電システムを対象に、本稿では対象建物の発電実績と周辺建物有無およびパネル傾斜有無による発電量、対象建物の南側隣接建物の高さと距離による発電量ついて検討した。結果の一つとして、周辺建物が存在する現在の条件下では、周囲建物がない場合に比べて年間発電量が約82%低下することが分かった。 |
| 7 |
|
アイランドマイクログリッドにおける簡易拡張手法の効果検証 |
| |
|
※岡村遼斗,松尾廣伸(静岡大学) |
| |
|
既存のアイランド型マイクログリッドの供給能力向上を目的とし、エネルギー効率の良い拡張方法を検討するために、実験用小規模マイクログリッド(PV–DG–BESS)を用いて実験を行っている。タンザニア農村部の負荷想定の下に、PVやBESSの容量追加による拡張、接続構成・負荷配分の変更等を行って、各所の電力を計測し、各ケースにおける電力フロー、総消費電力量、エネルギー損失を評価する。 |
| 8 |
|
複数の太陽光発電所における出力抑制量の推計 |
| |
|
※藤本卓也,原田真宏(大和ハウス工業株式会社) |
| |
|
本研究では,自社で保有する全国28か所の太陽光発電所を対象に,現地の気象データと発電データを用いて出力抑制量を推計した.出力抑制量の推計には総合係数を月ごとに補正する手法を提案し,推計精度の向上を確認した. 2023年度および2024年度の各サイトの抑制量を推計した結果,地域ごとに大きな差が見られ,特に九州電力エリアで最も高い抑制率が確認され,エリア全体と個別の発電所では出力抑制率が最大34%乖離していることを明らかにした. |
| 9 |
|
NotebookLMを用いたプロジェクトベース学習教育に関する一考察 |
| |
|
※藤澤徹(神奈川工科大学) |
| |
|
昨今目覚ましい進歩を遂げている生成AIを用いたPBL教育について検討する。具体的には、指導者の経験や勘にもとづく暗黙知のナレッジベース化と効果的な対話型学習の観点から、マルチモーダル情報の入力による「チャット」「レポート」「フラッシュカード」「テスト」「会話音声」などを活用するアクティブラーニングによってソーラーカーやエネマネなどに適用できる可能性について探る。 |
セッションB1(9:10~10:50):太陽光発電システム(営農型太陽光)
| 10 |
|
遮光実験結果による水稲用営農型太陽光発電シミュレーションの検証 |
| |
|
※舘山聖真,伊髙健治(弘前大学) |
| |
|
水稲用営農型太陽光発電シミュレーションの開発を進めており、過去の遮光実験の報告データを利用して検証を行った。寒冷紗による実験報告では、透過率もしくは遮光率に対する収量変化が報告されている。そこで寒冷紗を半透明太陽電池とみなしてシミュレーションすることで観測値と計算結果の比較を行った。検証した結果、外れ年もあるが概ね整合性が確認された。 |
| 11 |
|
新しい営農型太陽光発電用シミュレーションのアルゴリズムと生成AIを活用した作物成長モデルプラグイン開発 |
| |
|
※伊髙健治(弘前大学) |
| |
|
新しい営農型太陽光発電用シミュレーションでは、日射光線の情報を作物の成長モデルに与えるだけでなく、アメダスなどの観測データを加えて計算できるようにした。これにより、既報の作物学論文の成長モデルに近づけることが可能になり、作目の種類を増やすことが可能になる。コーディングについては生成系AIであるClaudeを用いることにより、プラグイン開発の迅速化をおこなったので、これについて報告する。 |
| 12 |
|
水田設置の小規模営農型太陽光発電事業における発電事業収支に関する分析 |
| |
|
※馬上丈司(千葉エコ・エネルギー株式会社) |
| |
|
2025年度に閣議決定された新たな食料・農業・農村基本計画において、営農型太陽光発電はFITの調達価格低下により以前のような収益が見込めないと記述されている。今後、農地利用における太陽光発電の普及を図るに際して、特に小規模な営農型太陽光発電設備かつ国内農地の過半を占める水田への設置で、どのような条件下であれば農業生産に資するだけの収益が確保し得るのかを分析する。 |
| 13 |
|
営農型太陽光発電設備が水稲に与える影響 |
| |
|
※合原亮一(株式会社ガリレオ) |
| |
|
水田に設置された営農型太陽光発電システムが、稲に与える影響を測定するため、架台下のブロックごとの収量を測定した。仮説に反して、南側や東側/西側などの日射量が多いブロックが必ずしも収量が多くないという結果を得た。稲の生育は積算温度の関数と考えられているため、架台下の温度環境を測定したところ、同じ積算温度になるという結果を得た。しかしブロックごとに収量の違いがあり、その理由を解析した。 |
| 14 |
|
地域での脱炭素化と再生可能エネルギー100%への現状と課題 |
| |
|
※松原弘直(NPO法人 環境エネルギー政策研究所) |
| |
|
地域的エネルギー自給率が100%を超える市町村は200を超えており、地域の脱炭素化の実現に向けて再エネ100%への取り組みが進み始めている。一方、欧州ではエネルギーコミュニティが再エネ指令に含まれ、制度化が進められている。国内ではソーラーシェアリングなどの取り組みが地域主体で進み、脱炭素先行地域として88の提案が選ばれている。そこで、地域での脱炭素化と再エネ100%への現状と課題を分析し、その実現に向けた方策を検討する。 |
セッションB2(11:00~12:20):気象・地球環境
| 15 |
|
全天候下の波長別日射量の簡易推定法に関する研究 その10 波長積分Perezモデルによる波長別斜面日射量の推定 |
| |
|
※上戸一樹,今西拓誇,曽我和弘(鹿児島大学) |
| |
|
本研究は、紫外・可視・近赤外放射を含む任意天候下の波長別斜面全天日射量の推定法の開発を目的とする。既報の水平面波長別全天日射量、水平面波長別天空日射量、法線面波長別直達日射量の推定式と斜面天空日射量を推定する波長積分Perezモデルを組合わせた推定法を検討し、それに基づく斜面波長別全天日射量の推定値の信頼性を検証する。 |
| 16 |
|
全天候下の波長別日射量の簡易推定法に関する研究 その11 波長別Perezモデルによる波長別斜面日射量の推定 |
| |
|
※今西拓誇,上戸一樹,曽我和弘(鹿児島大学) |
| |
|
任意天候化における斜面波長別全天日射量の推定法として、水平面波長別全天日射量・水平面波長別天空日射量・法線面波長別直達日射量の推定式と波長別Perezモデル(Perezモデルに含まれる大気の輝度に関するパラメータと透明度に関するパラメータを波長別に求める斜面天空日射量の計算法)を組み合わせた手法を検討し、波長別斜面全天日射量の推定値の信頼性を検証する。 |
| 17 |
|
波長別全天日射量の直散分離法に関する研究 -晴天指数に基づく波長別散乱比の推定法- |
| |
|
※星原旭陽,曽我和弘(鹿児島大学) |
| |
|
水平面における波長別全天日射量から波長別天空日射量を推定するため、晴天指数に基づく波長別散乱比の推定式を構築し、さらにエアマスおよび可降水量による補正を加えた波長別直散分離法を提案する。本研究では、この手法の推定精度を検証する。さらに、既往のErbsモデルに基づく推定値と比較を行う。 |
| 18 |
|
海洋から大気へ逆流するCO2が加速する地球高温化第2段階の巨大地震誘発メカニズム |
| |
|
※鈴木高広, 鈴木聖生(近畿大学),鈴木陽生(琉球大学) |
| |
|
温暖化がますます加速し、各地で猛暑日が増加した。昨年報告した海から大気へ逆流するCO2の増大が原因であるという仮説を裏付ける事態となった。この影響で増加した地震の発生パターンを調べたところ、日本列島のシーソー運動が地下の加圧マグマを流動させていることが示唆された。 |
セッションC1(9:30~10:50):太陽熱利用I
| 19 |
|
温度成層型水蓄熱槽におけるディストリビュータ近傍の流動性状把握 |
| |
|
※大家滉平(明治大学) |
| |
|
近年の省エネルギー意識の高まりを背景に、水蓄熱槽の効率的運用が注目されている。温度成層型水蓄熱槽では、ディストリビュータからの吹出し流が温度成層を乱して蓄熱効率が低下することが懸念されている。そこで本研究では、温度成層の維持および熱交換効率の向上を目的としたディストリビュータの改良形状の提案を目的に、ディストリビュータからの吹出し気流の特性を実測した結果について報告する。 |
| 20 |
|
太陽エネルギー等を活用した陸上養殖水槽の発明 |
| |
|
※平野祐晟(株式会社Seaside) |
| |
|
養殖において、基本要素が具備されている状況下では、水温の統制は最重要課題である。弊技術は、熱の放射・伝導を用いて、加えた熱を効率よく水温に伝える技術を発明。さらに太陽エネルギーを用い、省電力を実現した。 |
| 21 |
|
業務用建物に導入された太陽熱給湯システムの長期性能分析と改善案検討 |
| |
|
※深田彩心,吉永美香(名城大学) |
| |
|
再生可能エネルギー熱分野において、業務用・産業用の太陽熱利用の拡大が求められているが、実績は多くはなく、その事例情報の公開も十分ではない。そこで本研究では、東京都に建つ国際コンベンションセンターに導入された太陽熱利用給湯システムを対象に、6年間の運転データの分析を行い、性能評価と運転改善の可能性を検討した。 |
| 22 |
|
大気中水分凝集装置の設計と吸着材の基礎実験 |
| |
|
※馬越康平,松尾廣伸(静岡大学) |
| |
|
効率の良い大気中水分凝集装置構築を目的とし、集熱器、シリカゲル槽、顕熱交換器、ペルチェ素子からなる装置を構築中である。本報では、装置の設計と吸着材の基礎実験について示す。シリカゲル(A、B、C型)を室温23~25℃、相対湿度50~70%の環境下で18時間放置、その後55~65℃で6時間加熱を3日間繰り返して重量を測定した結果、A型の放湿量が最も多く、常に6.5g/100g/Cycle以上であった。 |
セッションC2(11:00~12:20):太陽熱利用Ⅱ
| 23 |
|
環境調和型PV/Tソーラーパネルの集熱量の予測精度向上に向けた研究 |
| |
|
※柿澤拓真,寺島康平,長井達夫(東京理科大学) |
| |
|
環境調和型PV/Tソーラーパネルの実用化には集熱量の予測が必要である。現在計算ツールで一般的に使用されている予測式は、簡単のため未知パラメータを定数に近似しているが、実測値と乖離があるため、より精度の良いモデルが必要である。本研究では、未知パラメータを収束計算によって求めることで時々刻々の環境の変化に合わせて集熱量を計算するモデルを作成した。このモデルの精度および、汎用性について報告する。 |
| 24 |
|
PV/Tソーラーパネルと低温再生型デシカント空調機を用いた潜顕分離空調の通年利用に関する研究 |
| |
|
※佐野晴也,寺島康平,長井達夫(東京理科大学) |
| |
|
本研究では、低温集熱で高い集熱・発電効率を発揮するPV/Tソーラーパネルと低い再生温度でも除湿可能な低温再生型デシカント空調機を組み合わせ、太陽電池の廃熱を活かして夏季に除湿を行うシステムの提案を目的としている。本報告では、このシステムにおいて通年でオフィスビルを対象にシミュレーションを行い、従来の太陽熱集熱器とデシカント空調機を組み合わせたシステムに対しての優位性を検証する。 |
| 25 |
|
高性能空気集熱器の集熱板形状と構造に関する研究開発 |
| |
|
※相曽一浩,盧炫佑,楠崇史(OMソーラー株式会社) |
| |
|
NEDOの「高温冷温熱源の面的利用のための超高効率太陽光集熱システムの研究開発」の研究委託事業で新しく集熱板形状とそれに伴う空気集熱器の開発を検討している。本報ではこれまでと違う集熱板形状の特性や集熱器内の設置構造などについて検討結果を報告する。 |
| 26 |
|
バイオガス発電と太陽熱集熱器による統合システムの最適化に関するエネルギー分析 |
| |
|
※伊藤鈴華,森太郎,大沢飛智(北海道大学) |
| |
|
牛の糞尿には強力な温室効果ガスであるメタンや一酸化二窒素が含まれるため、その削減が急務である。本研究では、バイオガス発電を支援するために太陽熱集熱器を組み合わせたシステムを対象とし、エネルギー効率の最適化を目的とする。OpenModelicaを用いて太陽熱集熱器の実測値とシミュレーション値を比較し、モデルの精度検証を行った。 |
セッションD1(9:10~10:50):バイオマス利用
| 27 |
|
放電除草における印加電圧と放電時間のパラメータ依存性と抵抗値に対する影響 |
| |
|
※平野敬祐,松尾廣伸(静岡大学) |
| |
|
特定外来生物であるナガエツルノゲイトウを薬剤不使用の放電除草により駆除することを目的として、実験用に育てたルッコラに対して印加電圧と放電時間をパラメータとし、それらの枯死に及ぼす影響を二元配置分散分析で統計的に調べた。その結果、両者共に値が大きい程に萎凋効果が大きく、特に印加電圧による影響が顕著であった。茎の抵抗値はサンプルの半数が枯死した9kV-90秒の条件では放電前の3.4%に低下した。 |
| 28 |
|
有機薄膜太陽電池を用いたBotryococcusのソーラーマッチングに関する検討 |
| |
|
※小口隼人,渡邊康之(公立諏訪東京理科大学),平野篤(東京電力ホールディングス株式会社),廣井英幸,三角久,堀川豊(株式会社関電工) |
| |
|
都市におけるカーボンマイナスの実現に向けて、微細藻培養への有機薄膜太陽電池(OPV)の適用可能性を検討の検討を行った。本研究では、当該波長域を透過する青色OPVを用い、Botryococcus TEPMO-26株を対象に遮光条件および無遮光条件で培養試験を行い、増殖への影響を評価を行った。 |
| 29 |
|
ロウソクとセルロースの燃焼に於けるススの生成・燃焼反応とそれらの差異 |
| |
|
※塙藤徳(森林総合研究所) |
| |
|
バイオマスの燃焼利用に際しては、健康障害の原因となるススや COの発生を抑制した燃焼方法が重要であるが、ロウソクやセルロースなどの比較的均一な化学構造を持つバイオマス由来物質ですら、その燃焼に於けるススの発生及びその燃焼に関する化学反応に関する報告は著者の知る限り無い。今回は、化学構造の異なるこれらの物質の燃焼様体の差から想定される当該化学反応について報告する。 |
| 30 |
|
大気CO2からメタンを大量生産するバイオメタネーションの高効率化による設備コストの低廉化 |
| |
|
※鈴木高広, 鈴木聖生(近畿大学),鈴木陽生(琉球大学),木村理,田中宏和(フジワラエナジー),廣島大祐(ウォーターエージェンシー) |
| |
|
サツマイモを大量生産しメタンに変換する設備を低廉化すれば、メタン・水素燃料を全量国産化できることをこれまでに報告した。メタン発酵工程において、サツマイモを下水汚泥や牛糞と混合し、メタン生成効率を2倍~3倍に高めることで、発酵槽を大幅に縮小できることを見出した。 |
| 31 |
|
光反応によるバイオメタノール生産に関する検討 |
| |
|
※久保田謙三,森豊,島卓真,堀川翔子,村上伸太郎,原田真宏(大和ハウス工業株式会社),大久保敬(大阪大学) |
| |
|
本研究では,光反応を利用してバイオガスからバイオメタノールを常温・常圧条件下で生産する方法を検討した。これまで100mLフラスコスケールでバイオガス中のメタンガスからメタノールへの変換率を89%まで高めることに成功したことから、5Lおよび100Lの試験機を製作し、スケールアップした場合の変換率を検証した。その結果、5Lおよび100L試験機でも80%以上の変換率であることを確認した。 |
セッションD2(11:00~12:20):建築温熱光環境・都市環境Ⅰ
| 32 |
|
HEAT20 G3適合住宅の性能評価 -群馬県桐生市に建設された戸建住宅における室内環境とエネルギー収支の実測調査- |
| |
|
※三田村輝章(前橋工科大学),新井政広(株式会社アライ),徳永響(株式会社アイ・ピー・イー) |
| |
|
本研究では,群馬県桐生市に建設されたHEAT20 G3に適合する住宅の室内環境やエネルギー収支について評価することを目的として,実測調査を実施した。本報では,2年間にわたる室内温湿度とエネルギー収支の実測結果の他,各季節における冷暖房設備の使用状況と温熱快適性,室内空気質などの測定結果について報告する。 |
| 33 |
|
金属折板屋根の年間日射熱取得に関する詳細計算 |
| |
|
※芝池英樹(建築都市科学ラボ) |
| |
|
倉庫・工場等の屋根は延べ面積が大きく、大部分はガルバリウム鋼板等を加工して製造された金属折板で葺かれることが一般的で、折板形状を精確に考慮した日射熱取得や放射熱損失を知ることは、屋内温熱環境の精算に必要不可欠である。平板傾斜面に単純化した場合との計算結果を比較し、計算誤差の傾向やインパクトを数値評価する。特に、高反射塗料等を表面塗布した場合に、平板で得られる日射反射効果は過大評価されることを示す。 |
| 34 |
|
CFDによる既存体育館の 空調・断熱改修前後の温熱環境評価 |
| |
|
※DENG XIAOHAN,酒井孝司(明治大学) |
| |
|
本研究は川崎市の既存体育館を対象に、CFD解析で断熱改修と空調方式の影響を評価した。 断熱材の追加は温度上昇と分布安定化に寄与し、暖房効率を高めた。また、床下送風と壁面送風を比較した結果、床下送風は上下温度差が小さく、居住域の温度分布が均一で快適性に優れることが確認された。以上より、断熱改修と床下送風方式の併用は快適性と省エネルギーの両立に有効であると結論づけられる。 |
| 35 |
|
CFD解析による自動スライドドアの開閉時間が外気侵入量に及ぼす影響に関する研究 |
| |
|
※XU MINGZE,酒井孝司(明治大学) |
| |
|
夏期冷房時の二重自動ドアを対象に、開閉時間(2–20 s)が外気侵入量と入口空間の温熱環境に及ぼす影響を、非等温・非定常CFDで解析した。評価指標として瞬時侵入風量と室温回復時間を用い比較した結果、開口時間が長いほど侵入量が増え、室温上昇の持続も延びる一方、短時間開閉は侵入抑制と空調負荷の低減に有効であることを示した。 |
ポスターセッション(13:20~14:20)
| P1 |
|
次世代太陽熱発電における金属系潜熱蓄熱体の作製と性能評価 |
| |
|
※池内悠馬,山田航太郎,籏町剛,郷右近展之(新潟大学) |
| |
|
次世代太陽熱発電の金属系潜熱蓄熱体として、Feよりも低融点の相変化材料(粉末)をFe系金属粉末に分散させ、加圧成型により溶解度差利用型の潜熱蓄熱合金を作製した。二種の金属の化学組成、合金の空隙率、Fe容器との高温適合性、塩化物系溶融塩との高温腐食性を調査した結果について述べる。 |
| P2 |
|
二段階熱化学サイクルにおけるBaMnO3系ペロブスカイト酸化物の置換イオンと反応性 |
| |
|
※外山大樹,井上紅,郷右近展之(新潟大学) |
| |
|
太陽日射量が大きい海外のサンベルト地域では、大型太陽集光システムにより~1500℃の高温太陽集熱が得られる。高温太陽集熱のエネルギー転換法として、金属酸化物の酸化還元系を反応媒体にした二段階熱化学サイクルによる水素やCO製造が欧米諸国で研究されている。本研究では二段階熱化学サイクルにおける高い反応特性をもつ反応媒体の開発を目的として、BaMnO3系ペロブスカイト酸化物における熱化学反応性について評価を行った。 |
| P3 |
|
ナノ粒子散乱性媒体による太陽電池の白色化 |
| |
|
※渡辺匠,小西沙良,高橋由紀子,山田昇(長岡技術科学大学),江目宏樹(山形大学) |
| |
|
建物の景観を損なわない建物一体型太陽光発電(BIPV)の需要が高まっている。白色系は建物外壁色として多用されているが、太陽電池表面に適用すると光学損失が大きいという課題がある。本研究では可視光を適度に散乱させてることで、太陽電池の変換効率低下を抑制しつつ白色度の高い層を作成した。 |
| P4 |
|
変調光照射法におけるロックインアンプ出力の理論モデルの妥当性の検討 |
| |
|
※Jiang Hao,小林靖之,駒場千空(帝京大学) |
| |
|
変調光照射法は太陽電池パネル内の対象セルへ変調光を照射し,パネル出力から電流クランプセンサで変調光由来信号をロックインアンプで抽出し対象セルの状態を非接触で推定できる.変調光照射法のロックインアンプ出力からの直接セル電圧とセル並列抵抗成分の定量的推定を目的として,パネル回路のリアクタンス成分を無視したロックインアンプ出力の理論モデルが低い変調周波数での測定結果を説明できることを示した. |
| P5 |
|
Legionella Transmission Investigation Linked to Sunlight Disinfection |
| |
|
※WU HE,大沢飛智,森太郎(北海道大学) |
| |
|
2023年の夏季に、宮城県において冷却塔を発生源としたレジオネラ症の集団発生があった。冷却塔から68万CFU/mLのレジオネラ属菌が検出され(基準値1 CFU/mL)、半径3km以内の23人感染者がいた。
本研究では当時の気象データと大崎市のGIS情報をCFDに導入し,発生源から半径5km以内のレジオネラの分布を計算し、拡散中の紫外線による除去効果を踏まえたリスクを定量的に解析した。 |
| P6 |
|
太陽光発電パネルとポータブル蓄電池を導入した環境共生住宅の住みこなし |
| |
|
※廣谷純子(愛知淑徳大学) |
| |
|
現在、高気密高断熱住宅に太陽光発電パネルを設置することが推奨されているが、主な対象が新築であることや、費用が高額である点が課題である。既存の戸建てや集合住宅で、比較的安価な費用で導入できる手法の開発も重要である。そこで近年普及してきた高性能なポータブル太陽光発電パネルと蓄電池に着目して、それらを日常使している住まい手の実態調査を2025年3月から開始した。今回はその概要と調査結果の一部を報告する。 |
| P7 |
|
電解水由来Cl⁻がCu₂O光触媒の表面化学と安定性に及ぼす影響 |
| |
|
※宮崎拓海(信州大学) |
| |
|
電解水は水素・酸素生成の反応媒体として注目されるが、Cl⁻を含むため光触媒表面の化学的安定性に影響を及ぼす可能性がある。本研究では、Cu₂Oをモデル光触媒とし、Cl⁻濃度・pH・ORPの変化と光照射下における表面変化を追跡する。これにより、Cl⁻が触媒の自己酸化還元挙動や溶解に与える寄与を評価し、電解水を用いた持続的な水素・酸素生成系に向けた基盤知見の獲得を目指す。 |
11月3日(月)
セッションA3(9:30~10:50):水素製造
| 36 |
|
水電解装置と燃料電池の応答性が水素生成型PV電力平滑化制御に与える影響 |
| |
|
※猪山颯志,髙橋明子,重信颯人,伊藤雅一(福井大学) |
| |
|
急峻に変動するPV電力を水電解装置で平滑化するために,水素生成型のPV電力平滑化制御法が提案されている.本研究では,水電解装置と燃料電池を一体化した可逆セルを用いて,上記PV電力平滑化制御法を実施する.水電解装置と燃料電池は,固体高分子型,アルカリ型,固体酸化物型で応答性が異なるため,各方式の応答遅れによる平滑化効果を比較する.平滑化効果は,系統へ逆潮流する電力のLFC領域の変動成分により定量的に評価する. |
| 37 |
|
火力発電機の設備容量低減を目的とした水素貯蔵システムの長期運用計画 |
| |
|
※岡﨑翔太,髙橋明子,重信颯人,伊藤雅一(福井大学) |
| |
|
近年、エネルギーシフトを用いた年間需要の平準化に関する研究が行われている。水素によるエネルギー貯蔵は、蓄電池で行う場合に課題となる自己放電が発生しないため、長期的な貯蔵に適している。そこで本研究では、水素を用いて年間需要の長期変動成分を平準化し、ピーク需要時における火力発電機の設備容量の低減を図る。検証の結果、水素貯蔵システムの導入により火力発電機の設備容量を低減することに成功した。 |
| 38 |
|
マイクロ波を用いたプルシアンブルーおよびその類縁体の合成と三相界面セルを用いたアンモニア電解合成能の評価 |
| |
|
※安田雄俊,城石英伸(東京工業高等専門学校),白石美佳,蒲生西谷美香(東洋大学) |
| |
|
低温常圧下でのアンモニア電解合成は,太陽光などの自然エネルギーを利用した水素キャリア生成法として有望だが,実用に足る触媒がないのが現状である.本研究では多様な物性を有するプルシアンブルー(PB)類縁体に注目し,マイクロ波を用いて鉄亜鉛系PB類縁体を炭素粉末上に担持した触媒を調製した.物性評価はXRDおよび透過型電子顕微鏡により行った,また,アンモニア電解合成能は三相界面を有するハーフセルで評価した. |
| 39 |
|
水熱合成によるg-C₃N₄/KB複合体を炭素担体としたFe/N/C型非白金系酸素還元触媒の開発 |
| |
|
※岡部継,城石英伸(東京工業高等専門学校),野村晃敬(物質・材料研究機構) |
| |
|
本研究では,Ketjenblack(KB)とg-C₃N₄を水熱合成による複合化により高活性なFe/N/C型非白金系酸素還元触媒の開発を目的とした.TEM観察の結果,球状のKBとシート状のg-C₃N₄が非常に良く絡み合った構造をしており,複合化が成功したことが示された.本物質を担体とした触媒の電気化学測定を行った. |
セッションA4(13:00~14:20):エネルギーシミュレーションⅠ
| 40 |
|
寒冷地を考慮した家庭用エアコン暖房で利用する環境熱の定量化に関する研究 |
| |
|
※渡辺康介,山本博巳(東北大学) |
| |
|
脱炭素社会に向けて、暖房器具を、環境熱を利用することによって、投入した電力の数倍の温熱を供給できるエアコンを用いることが重要となる。だが、一次エネルギー消費量における暖房の比率が高い寒冷地では、家庭におけるエアコンの負荷分担率は低い。そこで、寒冷地を考慮に入れて、環境熱利用量の定量化を行う。 |
| 41 |
|
九州地域の太陽光発電の出力抑制に関する施策の経済価値と分配構造 |
| |
|
※福家信洋(神戸大学),大橋和彦(一橋大学) |
| |
|
太陽光発電の急速な普及により出力抑制が増加しているが、その経済的価値や便益・負担の分配構造に関する研究は限定的である。本研究は、九州地域の2016~2020年度の市場価格と需給データを用いて出力抑制電力を評価した。分析の結果、便益は太陽光発電事業者や小売事業者に偏り、費用負担は需要家に集中する構造が確認された。本研究は、出力抑制電力の分離計測と低価格取引を可能にする制度設計の必要性を指摘する。 |
| 42 |
|
地域類型による市町村の脱炭素、再エネ大幅拡大と省エネ設備・断熱・省エネ車導入 |
| |
|
※歌川学(産業技術総合研究所) |
| |
|
市町村における再エネ普及、省エネ機械・車・断熱建築普及によるエネルギー需給変化、CO2排出削減効果、光熱費削減・経済効果について、自治体の類型(工業都市、都市型など)の違いを考慮し報告する。 |
| 43 |
|
一般廃棄物処理実態調査結果を用いたごみ量とごみ質の変化状況の把握 |
| |
|
※木全美翔,吉永美香(名城大学) |
| |
|
最終処分場の残余年数が限られる中、廃棄物削減は喫緊の課題である。また、可燃性ごみの焼却による排熱・発電利用は再生可能エネルギーとして今後の活用拡大が期待されている。これらの観点から、ごみ量やごみ質の変化傾向の把握は基礎資料として重要といえる。そこで本研究では、環境省が公開している平成10年度から令和5年度までの一般廃棄物処理実態調査結果を基に、容器包装リサイクル法によるごみ減量効果を明らかにする。 |
セッションA5(14:30~15:30):エネルギーシミュレーションⅡ
| 44 |
|
電力需給調整を目的とした重力蓄電装置の設計 |
| |
|
※松岡佑典,松尾廣伸(静岡大学) |
| |
|
数日から数カ月の中長期に渡るエネルギー貯蔵を目的に、自然放電が無く低コストな重力蓄電装置を設計した。日本国内での設置を想定し法令・規格への適合を行った.また、設計手順を体系化することで、実機構築への基礎設計を効率化した。標準仕様として吊り上げ高さ30 mに対し、ウエイト質量11.2 tの規模を策定した。同仕様では1 kWを32分間出力可能であり、推定往復効率は58 %であった。 |
| 45 |
|
シミュレーションによる砂充填型蓄熱槽の伝熱解析及び寸法設計 |
| |
|
※牧田佳士,松尾廣伸(静岡大学) |
| |
|
砂充填型蓄熱槽最適化のため、長さ20m、充填層直径3m、断熱材厚さ5mの円筒形蓄熱槽の同心軸に熱源と集熱配管を配置し、最大60kW、最高1200℃で12時間加熱し、入口空気279℃、5m/s一定で12時間放熱する蓄放熱サイクルシミュレーションを行った。充填層内の非温度変動部を減縮し充填層1.68m、断熱材3.56mとすることで、1サイクル集熱量を同程度に保ちつつ蓄熱槽体積を54%削減できた。 |
| 46 |
|
深井戸の上水汲み上げにかかる負荷電力のデマンドレスポンス制御 |
| |
|
※平田陽一(公立諏訪東京理科大学),藤森岳肇(茅野市) |
| |
|
まずは一例であるが、茅野市のある水源では、地下80mに30kWのポンプを入れて、配水池の水位を 見ながら随時汲み上げている。市内では、漏水や断水などを検知することを目的とし、水源や貯水 池の入りや出において、流量をセンシングしており、まずはそのデータを元に配水池のインフラを 想定して、どの程度の制御によりDRが可能か試算してみることとした。配水池の容量に余裕があれ ば、需要電力を昼より深夜に移動させることができる。 |
セッションA6(15:40~17:00):ZEB・ZEH
| 47 |
|
ヒートポンプを核としたスマートコミュニティに関する研究(その19) 予測モデルが HEMSの蓄エネルギーシステム最適化制御に与える影響に関する研究 |
| |
|
※田邊匠,劉洪芝,党柏舟,葛隆生,長野克則(北海道大学) |
| |
|
ZEBでは年間一次エネルギー消費量収支ゼロに加え、エネルギー自立度最大化も重要である。これには蓄エネルギー設備導入や高精度日射量予測は欠かせない。本研究では日射量予測手法がエネルギー自立度や購入電力料金に及ぼす影響について検討を行った。予測手法は、天候別にクラスタリングを行った上で1日毎にLSTMで予測を行うClosed loop型と毎時の実測値で予測更新するOpen loop型、そしてCNNとLSTMを組み合わせた3通りである。 |
| 48 |
|
宮城県川崎町でZEHを目指す宿泊施設の地域エネルギー活用状況 |
| |
|
※水澤隆良,武樋孝幸,早川佳孝(長岡工業高等専門学校),中安祐太(東北大学) |
| |
|
宮城県川崎町にZEHを目指す宿泊施設がある。ZEHのためには、主に高断熱高気密であること再生可能エネルギーを利用することすることが必要である。また地域の持続可能のためにエネルギーの地産地消が求められる。そこで本報ではこの宿泊施設における地域エネルギー活用状況を報告する。 |
| 49 |
|
パッシブデザインを活用した木造戸建て住宅のエネルギー性能評価に関する研究(第三報) 太陽光発電と蓄電池によるエネルギー自立の評価 |
| |
|
※持田正憲(武蔵野美術大学),西川豊宏,本坊雅樹(工学院大学) |
| |
|
実際の太陽光発電量と電力需要の関係を踏まえ、年間を通じたZEH(エネルギー自立率100%)の達成を目的として、冬期の暖房負荷が大幅に削減されるパッシブハウスにおいて、太陽光発電量・蓄電池設備とエネルギー自立の関係を明らかにする。 |
| 50 |
|
寒冷地におけるLCCO2マイナス住宅の入居後経年評価(その6)給湯設備の交換によるエネルギー消費量比較 |
| |
|
※金政一(兵庫県立大学),太田勇,東山純也(株式会社ミサワホーム総合研究所) |
| |
|
寒冷地である旭川市に建つLCCO2マイナス住宅において実居住環境のもとで通年実測を行っている。給湯設備の交換を行い、また居住者の変更に伴うそれに伴う各用途別エネルギー消費量および給湯設備機器の効率を分析し、設備機器の改修および住居スタイルによるエネルギー消費量の差異を検討した。 |
セッションB3(9:30~10:50):太陽光発電システム(応用技術Ⅰ)
| 51 |
|
避難所機能を備えた学校におけるレジリエンスを考慮したマイクログリッドの最適設備容量 |
| |
|
※香村崇斗,松尾廣伸(静岡大学) |
| |
|
避難所機能を備えた学校(延床(学校全体)5600m²、避難所収容300人)を対象に経済性とレジリエンスを考慮した最適設備容量を検討した。平常時・非常時負荷を想定し、20年間の経済性と72時間連続非常時負荷供給率を電力授受シミュレーションで評価した。経済性からPV68kW・蓄電池0kWh、レジリエンスから蓄電池17kWhを最適とし、両者を統合してPV68kW・蓄電池17kWhを最適設備容量とした。 |
| 52 |
|
電圧円線図を用いたPV装置制御による配電線路電圧逸脱の抑制 |
| |
|
※青山知生,雪田和人,七原俊也,津坂亮博(愛知工業大学),松村年郎(名古屋産業科学研究所) |
| |
|
本研究では、末端に大容量のPV装置のみが接続されるような配電系統において、PV装置の力率と逆潮流電流を適切に調整することで、PV装置連系点の電圧だけでなく、その線路上の電圧も適切な範囲に入るようなPV装置制御条件について、電圧円線図を用いて、定量的な検討を行った。 |
| 53 |
|
都市エネルギーを活用した電気自動車普及手法に関する研究 |
| |
|
※呉濟元,村田泰孝(崇城大学),姜在元,洪銅基(九州大学) |
| |
|
本研究は、都市の余剰エネルギーを活用し、電気自動車(EV)の普及を促進する手法を検討した。EV充電インフラ不足や電力系統への負荷といった課題に対し、余剰電力によるEV充電、Vehicle-to-Grid(V2G)戦略、需要分布を踏まえた最適なEV充電ステーション配置モデルを提案した。シミュレーション分析により、都市エネルギーとの統合活用が環境負荷低減に有効であることを示した。 |
| 54 |
|
太陽光発電システム導入におけるグリッド構成の一検討 |
| |
|
※雪田和人(愛知工業大学) |
| |
|
太陽発電システムに関して交流系統と直流系統の系統構成について検討した。 |
セッションB4(13:00~14:40):太陽光発電システム(応用技術Ⅱ)
| 55 |
|
非常用蓄電池を併設した避難施設での太陽光発電利用による経済性向上に関する基礎的検討 |
| |
|
※岩下希,若尾真治(早稲田大学),五十嵐郁瑛,菊池恵,中村祐喜(株式会社NTTドコモ) |
| |
|
本研究では、非常用蓄電池を備えた避難施設における太陽光発電システムの運用法を扱う。具体的には、平常時における電力基本料金の低減を目的としたピークカット制御の導入を検討する。避難施設となっている小中学校は、典型的な負荷パターンを取ることが想定される。本稿では、リアルタイム制御を避け、過去データを基に充放電スケジュールを作成する実用的かつ簡便な手法を提案し、シミュレーションと実証試験により評価を行う。 |
| 56 |
|
PV大量導入系統における高圧契約実需要家群の実需要推定に関する基礎的検討 |
| |
|
※宮﨑良祐,若尾真治(早稲田大学),Tumenbayar Byambadorj,石橋一成,鈴木大(東京電力ホールディングス株式会社),小泉僚平(東京電力パワーグリッド株式会社) |
| |
|
PVが系統に大量導入された現在、系統の実需要推定を精度よく行うことは重要課題である。これまで筆者らは、実需要データやPV出力データの大量な実測値から基本波形を抽出し、実需要推定を行う手法を開発してきた。本研究では、高圧契約の需要家が多いPV大量導入系統での実需要推定を目指す。抽出した基本波形を用いて見かけ上の需要を模擬し、その結果等に基づき実負荷を推定する手法を提案する。 |
| 57 |
|
アグリゲータによる配電系統電圧制約を考慮したPV余剰の蓄電池への割り付けによる地域内活用 |
| |
|
※岩科宗純,崔錦丹,植田譲(東京理科大学) |
| |
|
住宅用太陽光発電は最大限の導入が目指されている一方で、FITの満了や買取価格低下による売電メリット減少や、逆潮流による系統電圧上昇が課題である。本研究は、分散型PVシステムと定置型蓄電池の経済的合理性のある導入量検討に向け、アグリゲータによる管理のもとにこれらを利用する需要家群を想定する。そ
の上で系統の電圧や設置容量を考慮してPVの余剰を蓄電池に割り付け、PV活用を促進する運用手法を提案する。 |
| 58 |
|
太陽電池モジュールの排出量予測に基づくリサイクル装置のLCA評価 |
| |
|
※中村湧真,重信颯人,髙橋明子,伊藤雅一(福井大学),大関崇(産業技術総合研究所),津野裕紀(産業技術総合研究所/合同会社PVSQマネジメント) |
| |
|
将来、太陽電池モジュールが大量に廃棄されると予測され、課題である。そこで、リサイクル装置が導入されつつあるが、必要量や、環境への影響はよく分かっていない。本研究では、太陽電池モジュールの排出量予測に基づき、リサイクル装置の導入台数を3パターン想定し、処理可能量がどのように変化するかを示す。さらに、リサイクル装置導入による環境負荷をライフサイクルアセスメント(LCA)を用いて定量的に評価・比較する。 |
| 59 |
|
100%ソーラー発電で走る電気自動車は登場するのか? |
| |
|
※藤澤徹(神奈川工科大学) |
| |
|
この命題への解答は「するかしないかは考え方と条件による」といえる。本検討では競技用ソーラーカーの省エネ・創エネ性能の観点と、市販車(例えばプリウスPHEV+PV)のような観点、近年研究が進むPVEVや無充電EV等の観点から考察を試みる。住宅用太陽光発電システムと家庭用蓄電池(電気自動車)という観点および設備利用率(または太陽依存率)についても考慮する。誤解や過度の期待、思い込みの壁にも可能な範囲で議論したい。 |
セッションB5(14:50~16:10):太陽光発電システム(測定・検出技術)
| 60 |
|
低日射条件下におけるストリング故障検出のための機械学習アルゴリズムの比較 |
| |
|
※山田魁真,石倉規雄(米子工業高等専門学校) |
| |
|
本研究は、天候が悪い地域における太陽光発電システムを対象とし、低日射条件下での故障検知を目的とする。3モジュールのストリングを2つ用いて、一方を正常、他方を部分的影により発電性能が低下したストリングとして1ヶ月分の発電データを収集した。日射量100W/m2以下におけるデータを用いて回帰分析および決定木分析を基にした機械学習モデルを構築し、アルゴリズム毎の性能を比較した。 |
| 61 |
|
自己バイアス法による太陽電池ストリング対地絶縁抵抗測定時間短縮方法の検討 |
| |
|
※風間拓朗(光商工株式会社/筑波大学)/加藤和彦(産業技術総合研究所/筑波大学) |
| |
|
自己バイアス法は太陽電池モジュールストリングの正負極端を別々に測定抵抗で接地して得る2つの測定電流を用いて絶縁抵抗を算出するため、たとえば60秒値を得るには少なくとも120秒の測定時間が必要である。本研究では、自己バイアス法にローパスフィルタを付加した測定回路と太陽電池モジュールストリングの対地等価回路を数値計算を用いて解析することにより測定時間短縮の可能性を検討した。 |
| 62 |
|
PVストリング絶縁抵抗測定での開放法における測定手順について |
| |
|
※池田一昭,加藤和彦,大関崇(産業技術総合研究所) |
| |
|
PVストリングの絶縁抵抗測定において、ストリング極間を短絡せずに測定する開放法では、正極側から測定する手順がガイドライン等によって推奨されている.絶縁性の不備やセルストリング断線を有するストリングにおいて負極側を測定すると、太陽電池セルやバイパスダイオードを故障させる可能性があることが理由として挙げられているが、そのような事象は発生せず、負極側からの測定に不都合がないことを示す. |
| 63 |
|
インピーダンス計測によるバイパス回路故障検出技術 |
| |
|
※河村健一,小山優都,森功樹,西川省吾(日本大学) |
| |
|
本研究の目的は太陽電池ストリング単位でインピーダンスを計測することにより,ストリング内で発生している異常状態を早期に検出し,太陽電池の安全性・発電性能を高く維持する技術を確立することである.本稿ではバイパス回路の開放故障と短絡故障が太陽電池ストリングのインピーダンス特性に与える影響について報告する. |
セッションC3(9:30~10:50):建築温熱光環境・都市環境Ⅱ
| 64 |
|
寒冷地の公営住宅における夏季の熱中症危険度に関する研究 |
| |
|
※中野芳則,斉藤雅也,西川忠(札幌市立大学) |
| |
|
本報では、築年が最も古い札幌市営住宅である もみじ台団地(1971-72 年築)を対象に、2023 年と 2024 年の夏季に実施した室内温湿度測定および居住者アンケート調査に基づき、熱中症の発症リスクについて考察する。 |
| 65 |
|
夏季における住宅熱環境と居住者の水分補給についての人体エントロピー収支解析 |
| |
|
※深田悠平(島根大学),高橋達(東海大学) |
| |
|
本研究では、居住者が熱中症を発症する場合における水分補給の有無とエアコン冷房、放射冷房を使用した場合における人体エントロピー収支に与える影響について、以下のことを明らかにした。
非冷房空間で水分補給を行わない場合、コア温度39℃に達する時刻の積算エントロピー生成は68.1J/Kと最も低くなる。このことは、非冷房で水分補給なしの場合が、最も周囲環境と熱的平衡状態に近づいていることを表している。 |
| 66 |
|
里山環境下にある古民家を改修した木造建築における温熱環境評価 (第三報) 換気設備による空気の循環と外気負荷 |
| |
|
※本坊雅樹,西川豊宏(工学院大学),丸谷博男(株式会社エーアンドエーセントラル), 持田正憲(武蔵野美術大学) |
| |
|
本研究は、里山にある古民家を改修した木造建築を対象に、広縁の開閉や改修後 に導入された換気システム運転の最適化を検討し、室内の温熱環境と建物の熱的 な性能を評価するものである。本報では、換気システムによる外気と室内空気の 循環に着目し、給気・循環経路に沿って、温度推移と外気負荷について報告す る。 |
| 67 |
|
寒冷地における外断熱・二重通気工法住宅の冷暖房効果に関する実測調査~空気循環と蓄熱が室温に与える効果~ |
| |
|
※岨手俊郎,細谷浩二(株式会社カネカ),高橋達(東海大学) |
| |
|
寒冷地において木造軸組工法を基礎から外張り断熱し、外皮の室内側通気層を床下と小屋裏と連通させた空気循環機能を持たせた戸建て住宅において、蓄熱性能と空気循環効果について実測調査を行い、室内側通気層を保有することによるエネルギーフローと室内熱環境への影響を検証した。 |
セッションC4(13:00~14:20):建築温熱光環境・都市環境Ⅲ
| 68 |
|
「心地よさ」をもたらす光環境の季節特性の解明 −札幌における四季を通じた実験的検討− |
| |
|
※村山つばさ,斉藤雅也(札幌市立大学) |
| |
|
光環境の快・不快の判断基準として照度と色温度の関係を示すKruithof曲線が広く参照されているが、季節特性や温熱感覚などの影響が十分に考慮されていない。本県有では、季節ごとの感覚特性を反映する「想像温度」の概念を導入し、札幌における四季の実験を通じて快適な光環境の条件を検討した。その結果、Kruithof曲線の不快領域においても「快適」とする申告が多く、従来の評価基準の再検討が求められることが示唆された。 |
| 69 |
|
札幌市円山動物園「オランウータンとボルネオの森」の冬季の熱環境と動物行動 |
| |
|
※斉藤雅也,小野日大,本田直也(札幌市立大学),大野宏之(札幌市円山動物園),松本渉(大建設計),鈴鹿新平(札幌市) |
| |
|
本研究は、札幌市円山動物園「オランウータンとボルネオの森」における冬季の室内熱環境を実測し、動物福祉の観点から快適性と行動の安定性を支える環境設計の妥当性を検証した。放射暖房と置換換気により室温22~23℃、湿度60%前後を維持し、CFD解析の結果と概ね一致し、自然な採食・休息・遊戯行動が確認された。 |
| 70 |
|
PLATEAUデータを活用した屋外気流解析に関する研究 |
| |
|
※田中郁也,酒井孝司(明治大学) |
| |
|
国土交通省主導の都市デジタルツイン実現プロジェクト「PLATEAU」では、3D都市モデルが公開されている。本研究では新校舎建設によって風環境が懸念されている明治大学生田キャンパスを対象に、「PLATEAU」から用いた3D都市モデルを用いてCFD解析を行う方法を検討した結果を報告する。 |
| 71 |
|
樹木・芝生で緑化された駐車場の夏季熱環境緩和効果に関する実測調査 |
| |
|
※高橋達(東海大学) |
| |
|
樹木などで緑化された駐車場があれば、駐車台数が減るが、ヒートアイランド作用を低減し、駐車場での熱中症発生を抑制することが期待される。本研究では、緑化した駐車場の熱環境緩和効果を定量的に把握した。その結果、以下のことがわかっ た。1)緑化駐車場の気温はアスファルト駐車場より4~6℃低くなっている。2)樹木を車2台分の間隔で列植することにより、駐車場のほぼ全体が緑陰になっている。 |
セッションC5(14:30~15:30):太陽電池セル・モジュールⅠ
| 72 |
|
多結晶Ge薄膜の高品質形成と近赤外分光感度の実証 |
| |
|
※前田真太郎,石山隆光,末益崇,都甲薫(筑波大学) |
| |
|
多接合型太陽電池の低コスト化には、赤外光を吸収可能なGe層をガラスやプラスチックなどの汎用基板上に形成する技術が求められる。しかし、粒界やアクセプタ欠陥によりキャリアが散乱・消滅し、光電流は得られていない。本研究では、固相成長とエピタキシャル成長を組み合わせて、厚膜化と大粒径化の両立に成功した。その結果、アクセプタ欠陥を従来の1/10にまで低減させ、赤外分光感度を初めて実証した。 |
| 73 |
|
電界カーテンを用いた月レゴリス除去におけるコロナ帯電の影響評価 |
| |
|
※本庄由樹,西村亮(鳥取大学) |
| |
|
月面での太陽光発電には、レゴリスが太陽電池表面に堆積し、発電効率が低下するという課題がある。このレゴリスの除去方法として、電界カーテンによる除去方法に着目した。研究では、月面での利用を想定し、減圧タンク内においてレゴリスと成分および粒径がほぼ同等な模擬レゴリスを使用し、月レゴリスを正・負にコロナ帯電させた場合と無帯電の場合とで、除去効率にどのような差が生じるかを実験的に比較検討している。 |
| 74 |
|
機械的メタマテリアルによる軽量樹脂PVモジュールの熱応力低減 |
| |
|
※谷本智哉,渡邉傑,山田昇(長岡技術科学大学),佐藤大輔(宮崎大学) |
| |
|
太陽電池の応用拡大には軽量化が重要であり、ガラスを用いない樹脂系モジュールが注目されている。しかし樹脂は熱膨張率が大きく、温度変化に伴う応力や反りによる耐久性低下が課題となる。本研究では、熱膨張を抑制した機械的メタマテリアルをモジュールのバックカバーに適用した。シミュレーション及び実験の結果、従来材と比較して応力と反りが抑制され、信頼性向上の可能性が示された。 |
セッションC6(15:40~16:40):太陽電池セル・モジュールⅡ
| 75 |
|
日射光を利用したPL観察によるペロブスカイト太陽電池の故障検査方法 |
| |
|
※高野和美(株式会社アイテス),有松健司(東北電力株式会社) |
| |
|
ペロブスカイト太陽電池は実証実験が進み、来年には商業発電が予定されている。しかしながら、シリコン結晶型太陽電池に比べて耐久性が懸念されている。そこで、ペロブスカイト太陽電池を簡便に検査する方法として、太陽光を利用するPL検査方法を紹介する。 |
| 76 |
|
光無線給電に向けた1000nm帯用InGaAsP光電変換素子への太陽光照射の影響 |
| |
|
※青貫翔,落合夏葉,鈴木優紀子,柏倉一斗,鳥海陽平,髙橋円(NTT株式会社),大下隆也,田畑琴菜,山田丈翔,西岡賢祐,荒井昌和(宮崎大学),鈴木淳一,青山怜央,内田史朗(千葉工業大学),赤羽浩一(情報通信研究機構) |
| |
|
ドローンなどの移動体への光無線給電が注目され,光無線給電向けの光電変換素子の高効率化の研究が行われてきた。光無線給電のアプリケーションには屋外での利用も想定される。しかし,光電変換素子への太陽光の影響は検討されていない。そこで本研究では,長距離伝送に適した1000 nm帯向けのInGaAsP素子を作製し,レーザー光と太陽光を同時入射して特性を評価した。光無線給電の屋外利用における高効率動作に向けた指針を報告する。 |
| 77 |
|
太陽電池出力変化の一般化に向けた検討 |
| |
|
※増田幸治 |
| |
|
フィールドでの長期稼働時あるいは環境試験における太陽電池出力変化について直接議論されることは少ない。本研究ではある仮定の下でこれが微分方程式で表されることを示し、実際の用途に適した形での公式化を試みる。またここで導入するパラメータの挙動から、これらが劣化モードや耐久性を直接定量的に表すものであることを示し、本研究が太陽電池の長期信頼性評価に資するものであることを紹介する。 |
セッションD3(9:10~10:50):省エネルギー建築設備Ⅰ
| 78 |
|
大型施設におけるPV/Tソーラーパネルを用いた給湯・冷暖房システムの運用に関する研究 |
| |
|
※平井悠生,寺島康平,長井達夫(東京理科大学) |
| |
|
本研究は、発電と同時に集熱を行うPV/Tソーラーパネルと、低温熱源を利用して冷水を生成するエジェクタ冷凍サイクルを組み合わせることで、冷房需要にも対応可能な給湯・空調システムの構築を目的とする。さらに、このシステムを年間を通じて安定した冷房需要がある大型施設に導入し、従来の太陽光発電システムと比較した際のPV/Tパネルの優位性や、当該システムとの適合性が高い建物用途を明らかにする。 |
| 79 |
|
躯体一体型水蓄熱を導入した住宅用PV/Tソーラーパネルシステムに関する研究 |
| |
|
※關真弥,宮田悠平,寺島康平,長井達夫(東京理科大学) |
| |
|
太陽光発電と太陽熱集熱を同時に行うPV/T ソーラーパネルは低温での集熱によって集熱・発電効率が上がるが、大容量の蓄熱装置を要する。躯体一体型水蓄熱システムは熱容量の大きさや施工の容易さに優れ、これらを組み合わせることで太陽エネルギーの更なる活用が期待される。そこで、躯体一体型水蓄熱システムでの太陽熱利用による床暖房システムを検討した。本システムと他の蓄熱材との室内環境・省エネ性能比較について報告する。 |
| 80 |
|
大学講義棟の地中熱利用空調システムに関する研究-(その2)夏季・冬季のエネルギー・エクセルギー評価─ |
| |
|
※伊澤康一(福山大学),宋城基(広島工業大学) |
| |
|
大学講義棟で使用されている地中熱利用空調システムを対象にして,前報で検討した夏季に加えて冬季も含めた年間について,実測値に基づいてエネルギー評価・エクセルギー評価を試みた結果を報告する。特に,空調機コイル熱負荷(熱源装置供給熱量)から熱源装置投入電力を見積り,延いては発電所へ投入される化石燃料エクセルギーを概算することによって全体システムを包括的に評価した。 |
| 81 |
|
散水装置を備えたエアコン室外機の熱交換性能の実測 |
| |
|
※善方枝美華,酒井孝司(明治大学) |
| |
|
近年の酷暑に伴う外気温上昇によるエアコンの性能低下が懸念されている。対策として、室外機に散水装置を設け、蒸発潜熱により性能低下を抑制する方法が提案されている。散水による効果は、散水量や散水方法によって変化することが予想されるが、実測例が少なく、不明な点が多い。そこで、本研究では、CFDへの散水モデル適用を目的に、エアコン室外機に散水装置を設置し、実測を行った結果について報告する。 |
| 82 |
|
間接蒸発冷却と冷房室排気の複合によるエアコン冷房の性能向上に関する試み -室外機と外気ダクトにおける間接蒸発冷却への冷房室排気活用- |
| |
|
※南雲茜(日東商事株式会社), 高橋達(東海大学) |
| |
|
本稿では、エアコン室外機と外気ダクトにおける間接蒸発冷却に対して比較的低温で低湿の冷房室排気を供給することによって、外気導入ダクトでは外気負荷の削減効果を、エアコン室外機では間接蒸発冷却による使用電力の削減効果を拡大する実験・数値計算を行った。その結果、以下の結果が得られた。1)室外機吸混み部の散水ユニットに、冷房室排気を混合率75%で供給した場合、エアコンの使用電力量は最大で20%減少した。2) 外気導入ダクトの間接蒸発冷却は冷房室排気を混合率100%で供給すると、外気顕熱負荷の25~30%を除去できる。 |
セッションD4(13:00~14:20):省エネルギー建築設備Ⅱ
| 83 |
|
公営住宅に適用したダイナミックインシュレーション窓の性能評価に関する研究-改修条件の違いによる室内環境および経済合理性に関する分析- |
| |
|
※木村秀斗,三田村輝章(前橋工科大学), 大浦豊,藤園武史,岡村大輔(三協立山株式会社) |
| |
|
ダイナミックインシュレーション窓は二重窓内部に通気することで、換気しながら高断熱を実現する窓システムである。本研究では、これを公営住宅の断熱改修として適用し、その改修効果について実測調査や数値シミュレーションから検討を行ってきた。本報では引き続き、数値シミュレーションにより各改修条件下における室内温熱環境と冷暖房負荷の算出を行い、経済合理性を分析した結果について報告する。 |
| 84 |
|
温度差換気の非定常CFD解析に関する基礎検討 |
| |
|
※YANG JUNXI(明治大学) |
| |
|
吹き抜け空間では,温度差に誘起される浮力換気により,低エネルギーで効果的な排熱経路を形成できる。自然通風を主体とする建築において,各種モデリング仮定の下で得られる換気量Qを適切に評価することは,初期設計や省エネ評価において不可欠である。本稿では一般的な戸建住宅スケールの吹き抜けモデルを用い,建物外部に滞留する余剰熱を排除するための外部風速Uの設定方針とその根拠。建物内部の二階床の位置の違いが換気量に及ぼす影響に関する比較検討を行う。 |
| 85 |
|
光透過型真空断熱材の長期断熱性能に関する実験的検討 |
| |
|
※木村奏人,葛隆生,松井孝遥(北海道大学), 関根賢太郎,張本和芳,渡邉深雪(大成建設株式会社),長野克則(苫小牧工業高等専門学校) |
| |
|
今行っている加速試験と真空センサーによる内部圧力の測定の結果 |
| 86 |
|
光透過型真空断熱材の真空封止後の断熱性能を向上させる製造プロセスの検討 |
| |
|
※松井孝遥,木村奏人,葛隆生(北海道大学), 関根賢太郎,張本和芳,渡邉深雪(大成建設株式会社) |
| |
|
窓に貼ることで使用できる透明な真空断熱材の開発を目指している。住宅の冷暖房によるエネルギー消費を抑えるためには、特に窓の断熱性能の向上が重要だが、既存の断熱設備は、高性能なものは高価であり、安価なものは十分な性能が得られないという課題がある。そこで、簡単に施工でき、かつ安価で高い断熱効果を発揮し、明るさを損なうことなく室内環境を維持できる、全く新しい透明な真空断熱材の実現を目指して研究に取り組んでいる。 |
セッションD5(14:30~15:50):省エネルギー建築設備Ⅲ
| 87 |
|
太陽電池パネルの日射遮蔽効果に関する研究 第7報 PVパネルの内部発熱を考慮した伝熱モデルの検討 |
| |
|
※村田泰孝(崇城大学) |
| |
|
既報にてI-Vカーブを測定結果から同定し、等価回路を用いることで内部発熱を評価した。この結果を用いて、太陽電池パネルの日射遮蔽効果を評価するための伝熱モデルを検討し、測定結果との比較を行った。 |
| 88 |
|
光熱放射環境を調整するためのパッシブ手法及び放射型冷暖房・上下配光型照明を備える空間の室内環境把握に関する実験研究 その1.パッシブ手法及び放射型冷暖房・上下配光型照明を備える空間の概要と室内光環境の立体的空間分布の実測結果 |
| |
|
※浅田秀男,二村宏康(愛知淑徳大学),渡邊絵理香(元愛知淑徳大学) |
| |
|
愛知淑徳大学長久手キャンパスに2025年3月に竣工した建築実験棟には、光熱放射環境を調整することを目的としたパッシブ手法及び放射型冷暖房・上下配光型照明を備える教室兼環境実験室が作られた。本報ではまず当該教室に設置されたパッシブ手法と天井パネル型放射冷暖房システム、有機EL光源を用いた上下配光型電灯照明の概要について述べ、次に、室内光環境を実測し立体的空間分布について考察した結果について述べる。 |
| 89 |
|
光熱放射環境を調整するためのパッシブ手法及び放射型冷暖房・上下配光型照明を備える空間の室内環境把握に関する実験研究 その2.天井パネル型放射冷暖房システムによる夏期の放射冷房時の室内温熱環境及び熱放射環境の立体的空間分布の実測結果 |
| |
|
※二村宏康,浅田秀男(愛知淑徳大学),渡邊絵理香(元愛知淑徳大学),若林大聖,田島昌樹(豊橋技術科学大学) |
| |
|
環境実験室には、天井パネル型放射冷暖房システムが備えられている。ここでは夏期の放射冷房時において、外付けルーバーとLow-e複層ガラスにより極力日射熱取得を減らした上で、天井パネル表面温度を高めにして冷たくない柔らかい涼しさの創出を目指した。本報告では、室中央のグローブ温度が同じ場合で天井パネル表面温度が低め・中間・高目の場合の温熱環境及び放射環境の立体的空間分布を実測に基づき考察した。 |
| 90 |
|
水素エネルギーを利用した地域エネルギー自立性評価 |
| |
|
※水野敬太,太田勇(株式会社ミサワホーム総合研究所),新垣賢一朗(沖縄科学技術大学) |
| |
|
天候や季節に左右される変動性の高い太陽光発電システムと、安定的に電力を供給できる純水素燃料電池システムを組み合わせることで、建物や地域全体における持続的なエネルギー自立を目指す。本報では、シミュレーション解析と実証実験を通じて、各システムの必要容量を検討するとともに、太陽光・水素それぞれのシステム由来のエネルギー利用実態を評価し、エネルギー自立に向けた知見について報告する。 |
セッションE1(11:00~12:00):地域脱炭素部会・100%再生可能エネルギー部会合同シンポジウム 1073室
地域からの脱炭素を加速するために -住宅省エネ,再エネ発電から,EV,V2Hまで,横断的パッケージ化を-」基調講演
| E1 |
|
なぜ地域で脱炭素が必要なのか -地域防衛と未来づくりのための地域脱炭素の取組- |
| |
|
藤野純一(公益財団法人 地球環境戦略研究機関) |
| E2 |
|
分散型リソースとしての住宅エネルギーマネジメントとデマンドフレキシビリティ |
| |
|
岩船由美子(東京大学 生産技術研究所) |
| E3 |
|
太陽光とEVが拓く未来の暮らし なぜ今、異業種連携が必要なのか? |
| |
|
辻 基樹(株式会社再エネ企画) |
セッションF1(13:00~13:20):地域脱炭素部会・100%再生可能エネルギー部会合同シンポジウム 1076室
基調講演
| E4 |
|
自治体における太陽光発電(または再生可能エネルギー)の普及に向けた取組 東京都建築物環境報告書制度の概要について |
| |
|
大野公治(東京都環境局) |
セッションF2(13:20~14:20):地域脱炭素部会・100%再生可能エネルギー部会合同シンポジウム 1076室
問題提起
| E5 |
|
企業からのフラッシュトーク(1社7分) |
| |
|
ニチコン株式会社,株式会社ミサワホーム総合研究所,積水ハウス株式会社,ヤマダ住建ホールディングス,三菱自動車工業株式会社,日産自動車株式会社,パナソニック株式会社,株式会社REXEV,他
|
セッションF2(14:50~16:20):地域脱炭素部会・100%再生可能エネルギー部会合同シンポジウム 1076室
パネルディスカッション
- モデレーター 堀尾 正靭(東京農工大学名誉教授)
- パネリスト 藤野 純一(地球環境戦略研究機関)
- パネリスト 高口 洋人(早稲田大学)
- パネリスト 岩船 由美子(東京大学)
- パネリスト 辻 基樹(株式会社再エネ企画)
- パネリスト ほか、フラッシュトーク参加各社